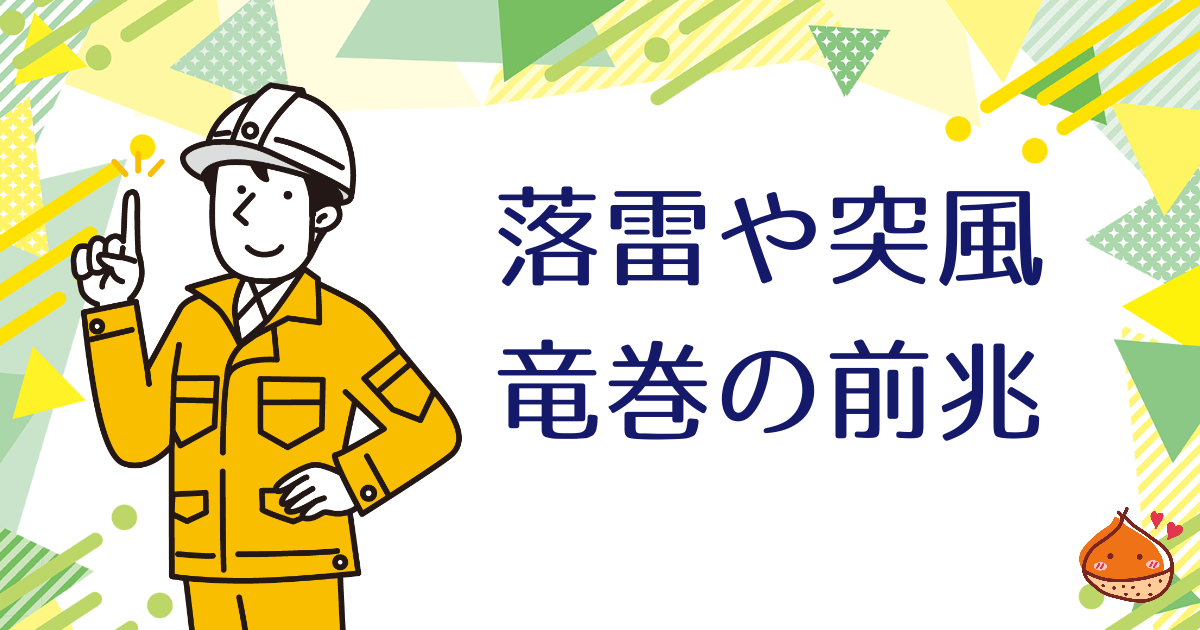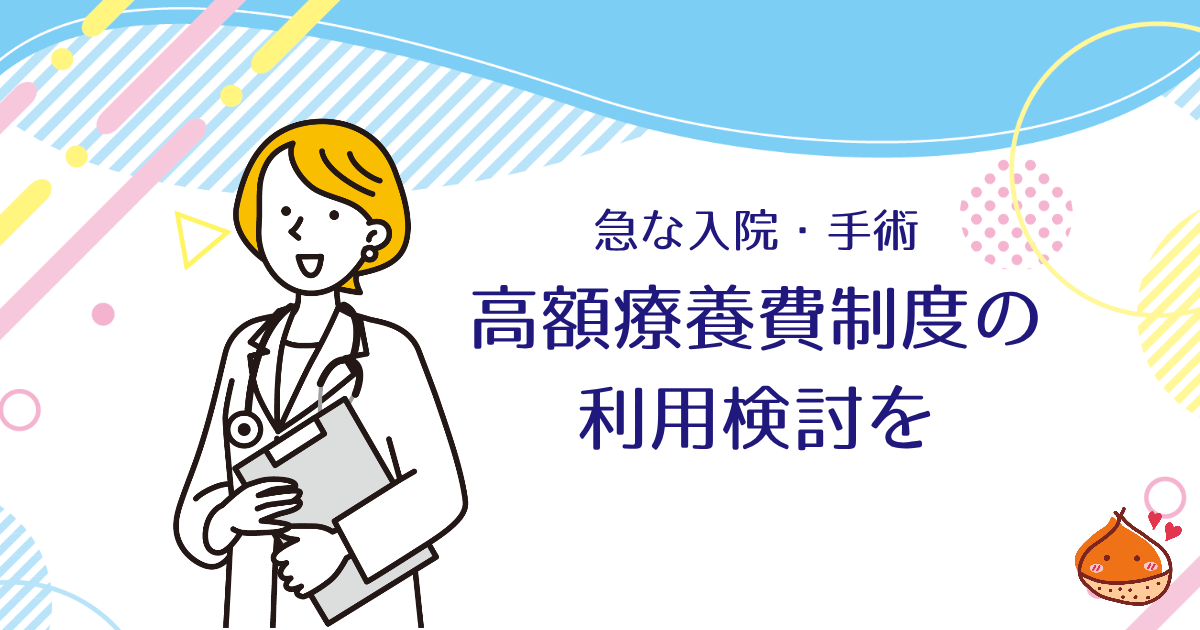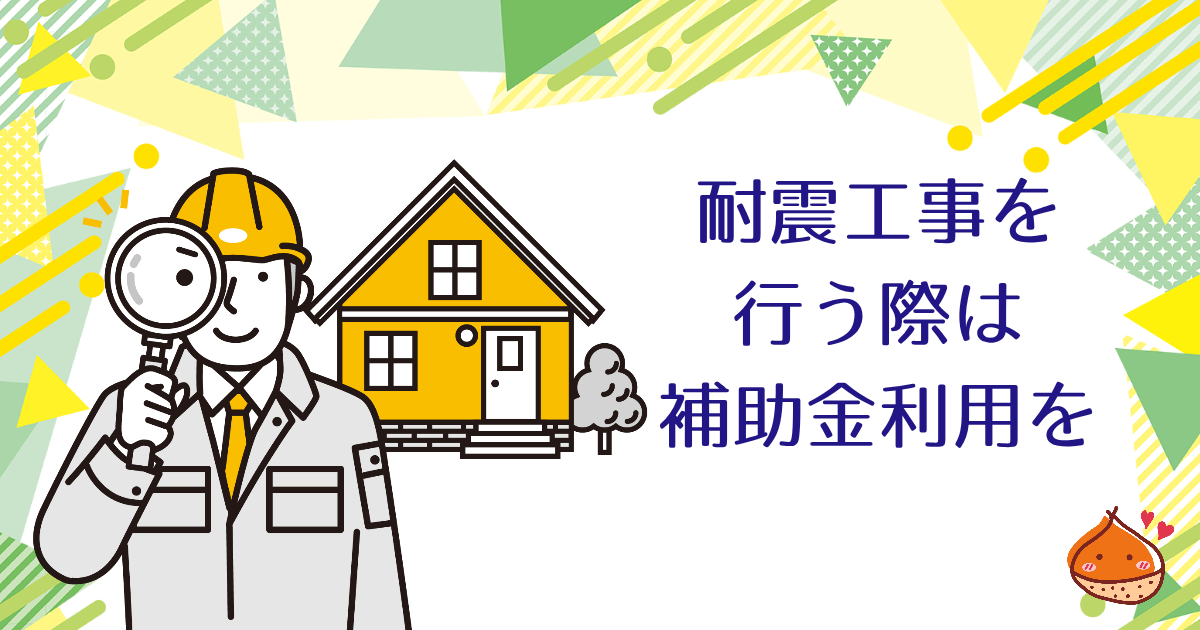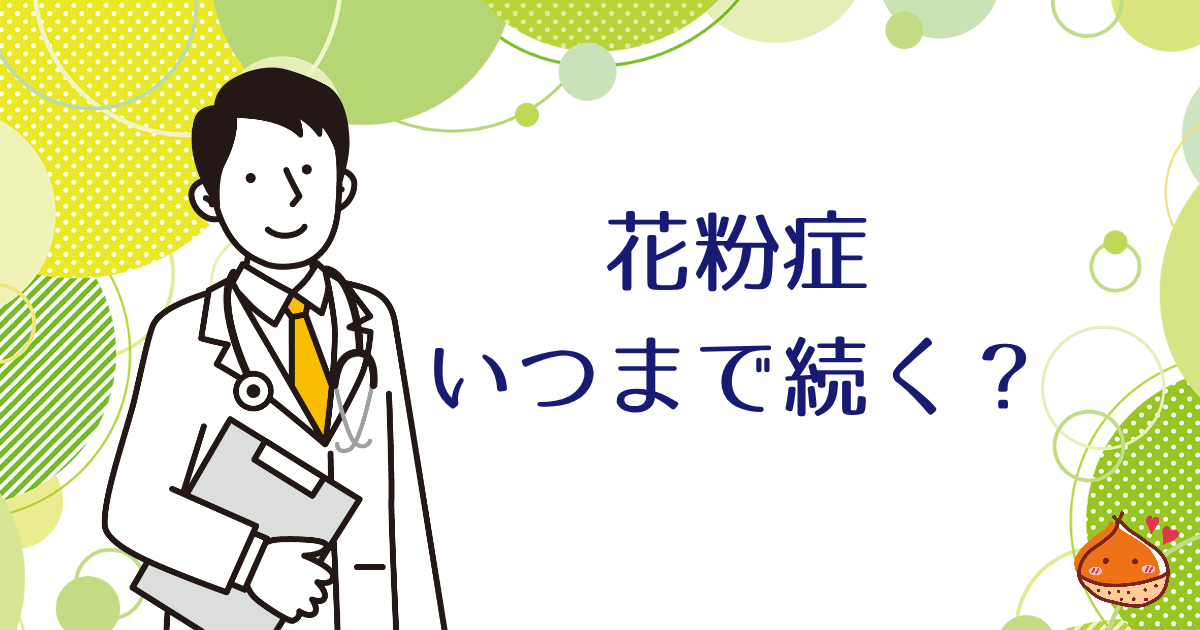
毎年のようにやってくる花粉シーズン。「今年はいつまで続くの?」「もうそろそろ終わりじゃないの?」——そんな声が、あちこちで聞こえてきます。目のかゆみ、鼻づまり、くしゃみ…。マスクや薬で対策していても、終わりが見えないとつらいものですよね。
気温の変化や冬の降雪量の影響で、花粉の飛散時期や量にも地域差が出ています。早めにピークを迎える地域もあれば、例年より長く続くところも。つまり「いつまで我慢すればいいのか?」は、今年こそ知っておきたいポイントです。
この記事では、花粉飛散量の予測や地域別のピーク時期、そして今すぐできる花粉対策をわかりやすく紹介します。
春の空気を気持ちよく感じるために、正しい知識と早めの準備で、この季節を少しでも快適に乗り切りましょう。
2026年の花粉飛散量の予測
スギ・ヒノキ花粉の飛散量は「やや多め」の予想
2026年の花粉飛散量は、東海から北海道にかけて前年よりやや多めになる見込みです。特にスギ花粉は猛暑の影響を受けて、花芽の形成が活発になった地域が多く、例年比で120〜150%程度の地域もあります。
引用:ウェザーニュース 2026年春の花粉飛散予想 全国的に平年を上回る予想 東北北部では過去10年で最多に匹敵来年2026年春の花粉飛散量は、北日本と東日本で2025年を大きく上回る予想で、全国的に平年(2016〜2025年の平均飛散量)よりも多くなる見込みです。特に東北北部では、平年比で200%を超える地域もあり、過去10年で最多に匹敵する大量飛散になるとみています。
https://weathernews.jp/news/202510/010076/(参照:2025-10-06)
もっと詳しく知りたい!という方は、日本気象協会・ウェザーニュースが公開している2026年の花粉飛散予測をご覧ください。
飛散ピークは2月〜4月 長期化の可能性も
花粉シーズンは、2月上旬〜4月下旬が中心となります。スギ花粉は2月中旬に飛び始め、3月中旬にピーク、4月からヒノキ花粉が優勢になる見込みです。
ただし、気温の上昇が早かった地域ではスギとヒノキのピークが重なるため、例年以上に症状が強く出る可能性があります。
花粉症の方は、2月前半から薬を服用し始める「先手対策」がおすすめです。
気象条件が花粉量に与える影響

花粉量は「前年の夏の気温」と「冬の寒さ」で大きく変わります。夏は全国的に暑く、日照時間が長かったため、スギが多くの花芽を作り、翌年は花粉が増加傾向になっています。
つまり、「前年の夏が暑い」「冬が暖かい年」は要注意。これらの条件が重なると、飛散量が増え、期間も長引くというわけです。
花粉症はいつまで続く?時期の目安

スギ花粉:2月〜4月中旬
日本で最も多くの人が悩まされる花粉といえば、やはりスギ花粉です。例年2月上旬から飛び始め、3月中旬にピークを迎え、4月中旬まで続くのが一般的です。特に関東・近畿では飛散量が多く、風の強い日や乾燥した日は注意が必要。
症状は鼻水・くしゃみ・目のかゆみなど典型的なものが多く、2月に入る前からの早めの対策が効果的です。
スギ花粉のピークを過ぎても、ヒノキ花粉が続くため、「4月まで長引く」と覚えておきましょう。
ヒノキ花粉:3月〜5月上旬
スギの次に多いのがヒノキ花粉で、3月中旬〜5月上旬にかけて飛散します。特に4月の新年度シーズンにピークを迎えることが多く、スギ花粉が落ち着いたと思ったらまた症状が出てきたという方は、ヒノキが原因かもしれません。
スギより粒子が細かいため、鼻の奥や喉まで入り込みやすく、咳や喉の違和感が出る人も。
花粉症の期間を短くするためには、スギの時期から連続的なケアを続けるのがおすすめです。
イネ科花粉:5月〜7月
イネ科の花粉(カモガヤ・オオアワガエリなど)は、春が終わる5月ごろから飛び始めます。公園や河川敷、道路の草むらなど身近な場所に多く、散歩中にも症状が出ることがあります。
スギやヒノキほど大量には飛びませんが、局所的に濃度が高いため注意が必要です。
ピークは6月前後で、梅雨入りとともに減少しますが、地域によっては7月まで続くことも。
「春が終わったのにまだ鼻がムズムズする」という場合、イネ科が原因の可能性があります。
ブタクサ花粉:8月〜10月
秋の代表的な花粉症の原因がブタクサです。8月中旬〜10月ごろまで飛散し、特に9月がピーク。スギより粒子が小さく、気管支や肺まで入り込みやすいのが特徴です。
そのため、くしゃみや鼻水だけでなく、咳や息苦しさといった喘息に似た症状が出る人もいます。
ブタクサは道端や空き地など、生活圏の中に多く生えているため、秋の散歩や通勤時もマスク対策が欠かせません。
実は秋も油断できない!秋の花粉症とは
「花粉症=春」と思われがちですが、秋もアレルギー症状が出やすい季節です。ブタクサやヨモギ、カナムグラなどの雑草が原因で、鼻づまり・目のかゆみ・のどの違和感が現れます。
また、秋は夏の疲れや寒暖差で免疫バランスが崩れやすく、症状が悪化することもあります。
春の花粉が終わっても油断せず、秋にもマスク・洗眼・うがいの習慣を続けるのがポイントです。
これを読んでいて思った方もいるでしょう。「花粉って、ほぼ1年中飛んでるじゃん!」
はい、そうなんです。花粉症に加えてハウスダストなどのアレルギーを持っている人は本当に1年中アレルギーに苦しむことに・・・。
ですが、ご自身が何のアレルギーを持っているのか把握できれば対策も何かあるはず。まずは医療機関でアレルギーの検査を受けることからはじめてみませんか。
花粉症の症状を悪化させる生活習慣
マスクを外しての外出時間が長い
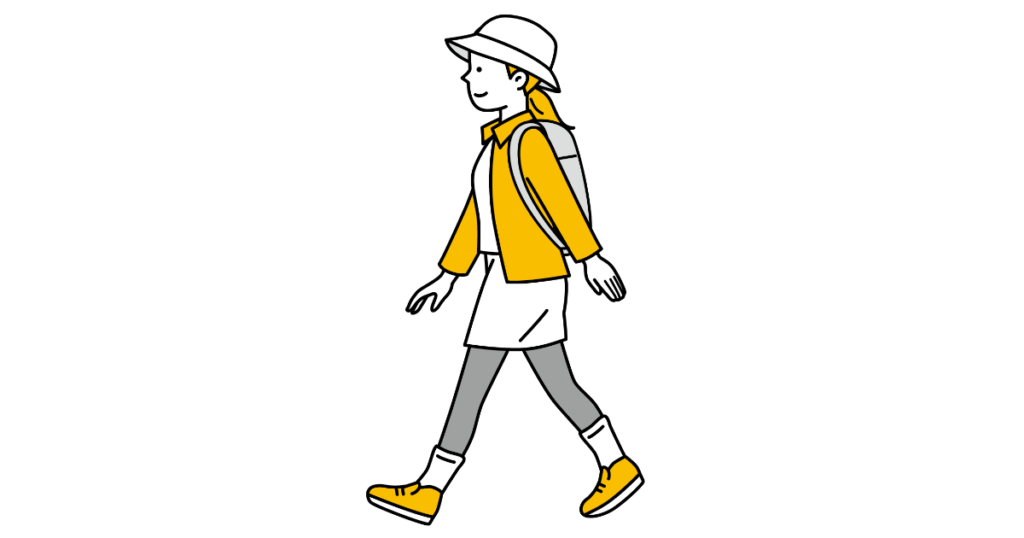
花粉が多く飛ぶ日は、マスクを外しての外出が症状悪化の大きな原因になります。特に風が強い日や晴天の日中は、花粉が空気中に舞いやすく、短時間でも吸い込む量が増えることがあります。
マスクをしていないと、鼻や喉の粘膜に直接花粉が付着し、アレルギー反応が強く出やすくなります。
人の少ない場所でも、なるべく外ではマスクを着用し続けることが重要です。
また、マスクの内側にワセリンを薄く塗ると、花粉の侵入をさらに防げます。
部屋干しをしていない
洗濯物を屋外に干すと、花粉が繊維にびっしりと付着します。
それを取り込むことで、家の中に花粉を持ち込む結果になり、夜になっても症状が治まらない原因に。
特に寝具やタオルなど、顔に近いものは部屋干しを徹底しましょう。
どうしても外に干したい場合は、花粉の少ない午前中(早朝)に限定し、取り込む前に軽くはたくことがポイントです。
部屋干しの際には除湿機やサーキュレーターを併用すると、乾燥時間を短縮できます。
帰宅後すぐにシャワーを浴びない
外出中に髪や肌、衣服には大量の花粉が付着しています。
帰宅後すぐにシャワーを浴びず、リビングや寝室に入ってしまうと、花粉を家中にまき散らしてしまうことになります。
顔や手を洗うだけでなく、髪の毛にも花粉が多く付いているため、できれば入浴して洗い流すのがベスト。
すぐにお風呂に入れない場合は、少なくとも顔・手・うがいを徹底しましょう。
上着を玄関先で脱いでおく習慣も効果的です。
睡眠不足やストレス

睡眠不足やストレスは、免疫バランスを乱し、アレルギー反応を強める原因になります。
特に睡眠が浅いと、体が十分に回復できず、花粉に対する過敏反応が出やすくなることが知られています。
また、ストレスによって自律神経が乱れると、鼻の血流が悪くなり、鼻づまりや頭痛を感じやすくなります。
十分な睡眠と規則正しい生活を意識するだけでも、症状の軽減につながります。
花粉症シーズンこそ、「休むこと」も立派な対策です。
花粉症対策の基本
マスク・眼鏡の活用(花粉カット率の高い製品を選ぶ)

花粉症対策の第一歩は、体内に花粉を入れないことです。
市販のマスクでも「花粉カット率99%」などの高性能タイプを選ぶと、吸い込む花粉量を大幅に減らせます。
また、顔にすき間ができない立体型マスクや、不織布素材のものがおすすめ。
さらに「花粉対策用のメガネ」を併用すると、目への付着も防げます。
通常のメガネよりもフレームが大きく、顔にフィットする設計のものが多く、涙目やかゆみの軽減に効果的です。
顔まわりをしっかりガードすることで、外出時の不快感がぐっと減ります。
空気清浄機の活用とフィルター掃除の重要性
室内でも油断は禁物。花粉は窓の開閉や衣類の持ち込みで簡単に入り込みます。空気清浄機を稼働させることで、室内の花粉濃度を低く保つことが可能です。
特に「HEPAフィルター」搭載タイプは、花粉や微粒子をしっかりキャッチしてくれる優れもの。ただし、どんな機種でもフィルター掃除や交換を怠ると効果が半減します。
1〜2週間に一度は掃除機でホコリを吸い取り、定期的な交換を忘れずに。
玄関付近や寝室など、花粉を持ち込みやすい場所に置くのがおすすめです。
服装(毛足の短い素材を選ぶ)
外出時の服装も、花粉対策の大きなポイントです。ウールやフリースのような毛足の長い素材は花粉が付着しやすいため、避けるのが賢明。
代わりに、ポリエステルなどのツルツルした素材を選ぶと、花粉が付きにくく、落としやすいです。上着は玄関で脱ぎ、部屋に持ち込む前に軽くはたく習慣をつけましょう。
帽子をかぶるのも有効で、髪への花粉付着を防げます。
おしゃれを楽しみながら、素材選びで花粉をブロックするのがポイントです。
外出後のケア(洗顔・うがい・鼻うがい)

帰宅後は、まず体についた花粉を取り除くことが最優先です。手洗い・うがいはもちろん、顔や目のまわりの花粉も洗い流しましょう。
特に「鼻うがい」は、鼻の奥に溜まった花粉を除去でき、鼻づまりやくしゃみの緩和に効果的です。市販の専用洗浄液を使えば、痛みも少なく簡単にできます。
また、髪にも花粉が多く付着しているため、できるだけ早めの入浴がおすすめ。
「帰宅後すぐのケア」=その日の症状を軽くする一番の近道です。
花粉症に強い生活習慣を身につけよう
睡眠をよくとる・適度に運動をするなどして正常な免疫機能を保つ
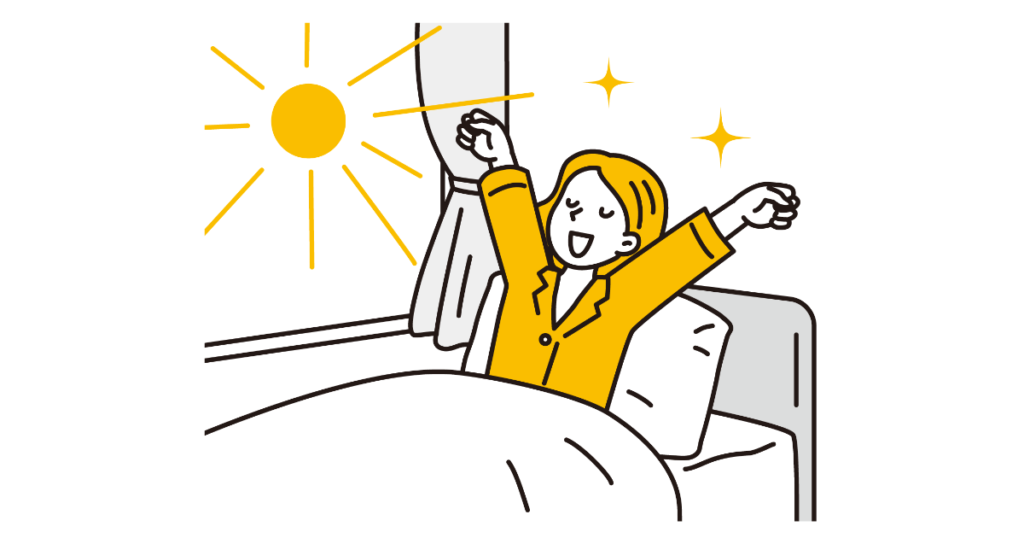
花粉症は、免疫バランスが乱れることで過剰に反応してしまうことが原因の一つです。睡眠不足や過労が続くと、体の防御機能が低下し、花粉に敏感に反応しやすくなります。
十分な睡眠を取り、規則正しい生活リズムを保つことが基本です。また、軽いウォーキングやストレッチなどの運動も、血流を改善し免疫の働きを整えます。
激しい運動ではなく「気持ちよく体を動かす」程度が理想です。体温を上げて代謝を良くすることで、花粉症のつらい症状を軽減する効果も期待できます。
ストレス解消にもつながるため、毎日のリズムに取り入れてみましょう。
健康的な生活が、結果的に「花粉に強い体」をつくります。
鼻やのどの粘膜を正常に保つために、タバコや過度の飲酒は控える

花粉症の症状は、鼻やのどの粘膜が敏感になっている時に悪化しやすい傾向があります。喫煙は粘膜を直接刺激し、炎症を起こしやすくするため、症状を重くする原因になります。
また、アルコールを摂取しすぎると血管が拡張し、鼻づまりや目のかゆみを悪化させます。「お酒を飲んだ翌日に鼻が詰まる」という人は、特に注意が必要です。
鼻やのどの健康を守るには、禁煙・節酒を意識することが大切です。水分をしっかりとり、加湿器などで室内の湿度を保つのも効果的です。
乾燥を防ぐことで、花粉が粘膜に付着しにくくなり、症状の緩和につながります。
早めに花粉症の薬を服用する・医療機関へ受診も検討する

花粉症は「症状が出てから対処する」よりも「出る前に抑える」方が効果的です。症状が出始める前から抗ヒスタミン薬などを服用しておくと、反応を軽く抑えられます。
市販薬でも効果を感じにくい場合は、医療機関での相談をおすすめします。
病院では症状に合わせて、眠気が出にくい薬や点鼻薬などを処方してもらえます。
「毎年つらい」と感じている人こそ、早めの受診が大切です。
医師のアドバイスを受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質が大きく向上します。また、アレルゲン検査を受けることで、自分の花粉の種類を正確に把握できます。
適切な薬と対策で、花粉シーズンを穏やかに乗り切りましょう。
加入している保険組合や会社によっては補助金も
辛い花粉症、通院したり市販薬を買ったり、お金と時間がそこそこかかります。
症状の酷さは人それぞれなので「3ヶ月は薬を飲み続けているよ・・・」という方もいらっしゃるかも。花粉の飛散期間が長ければそれだけ服薬の期間も長いはず。しんどいですよね。
加入している保険組合や勤めている会社によっては、花粉症に対して補助金を出しているところもあります。
花粉症は、QOLを低下させてしまう辛いアレルギー症状です。もしも活用できるのであれば、利用してくださいね。
まとめ
花粉症対策は、薬やマスクだけではなく、日々の生活習慣の積み重ねがとても重要です。
しっかり睡眠をとり、体を適度に動かして免疫のバランスを整えることで、花粉への過剰反応を抑えることができます。
また、喫煙や飲酒を控えて鼻やのどの粘膜を守ることも、症状の軽減につながります。
そして、花粉が飛び始める前から薬を飲み始める「早めの対策」がポイントです。
「今年こそ花粉に負けない!」そんな前向きな気持ちで、健康的な日々を送りましょう。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
ウェザーニュース 2026年春の花粉飛散予想 全国的に平年を上回る予想 東北北部では過去10年で最多に匹敵
https://weathernews.jp/news/202510/010076/(参照:2025-10-06)
日本気象協会 tenki.jp 2026年 春の花粉飛散予測(第1報) 東日本と北日本は例年の1.3~2.5倍 今夏の猛暑が影響
https://tenki.jp/pollen/expectation/(参照:2025-10-06)
政府広報オンライン 花粉症で悩む皆さま! 早めの治療や予防行動を!
https://www.gov-online.go.jp/article/201102/entry-8208.html(参照:2025-10-06)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
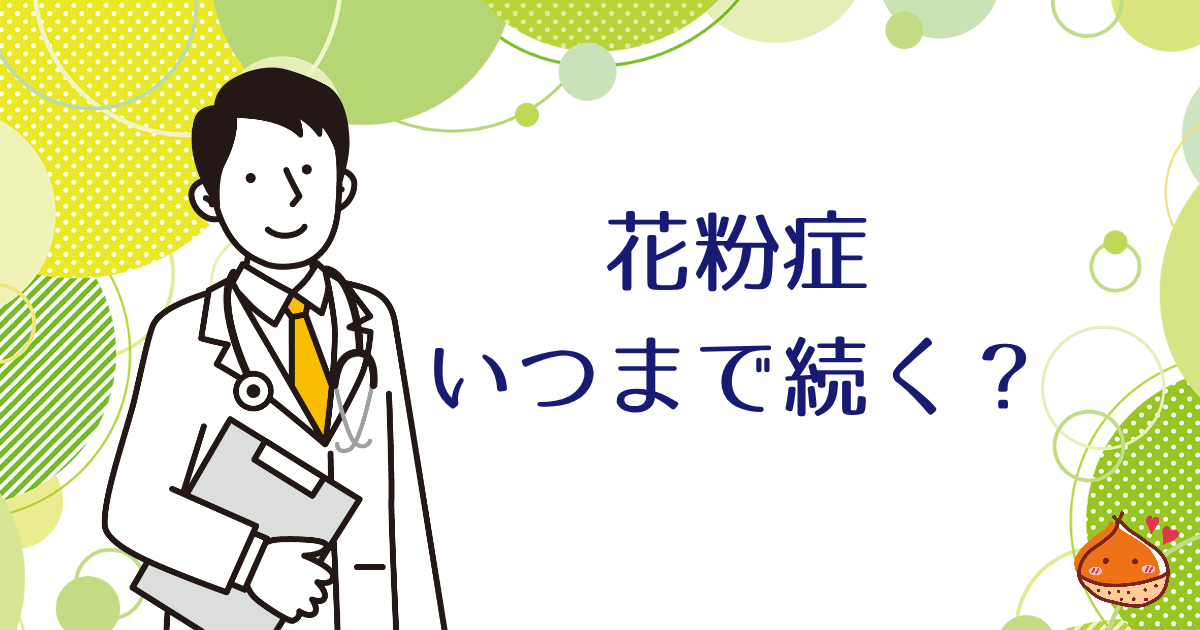
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。