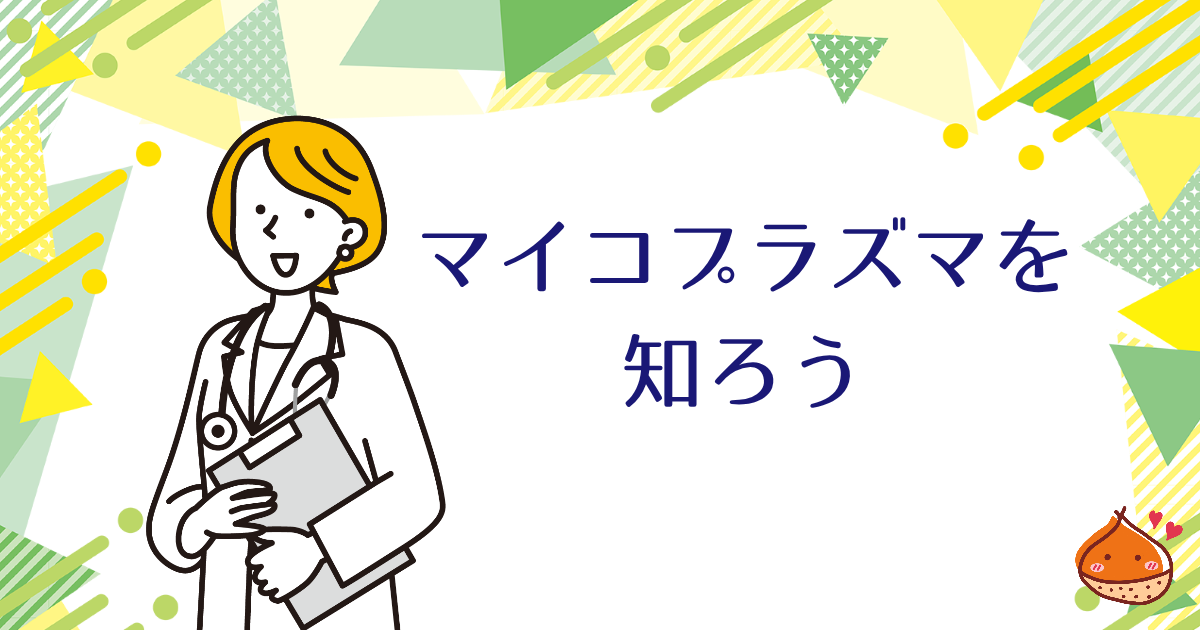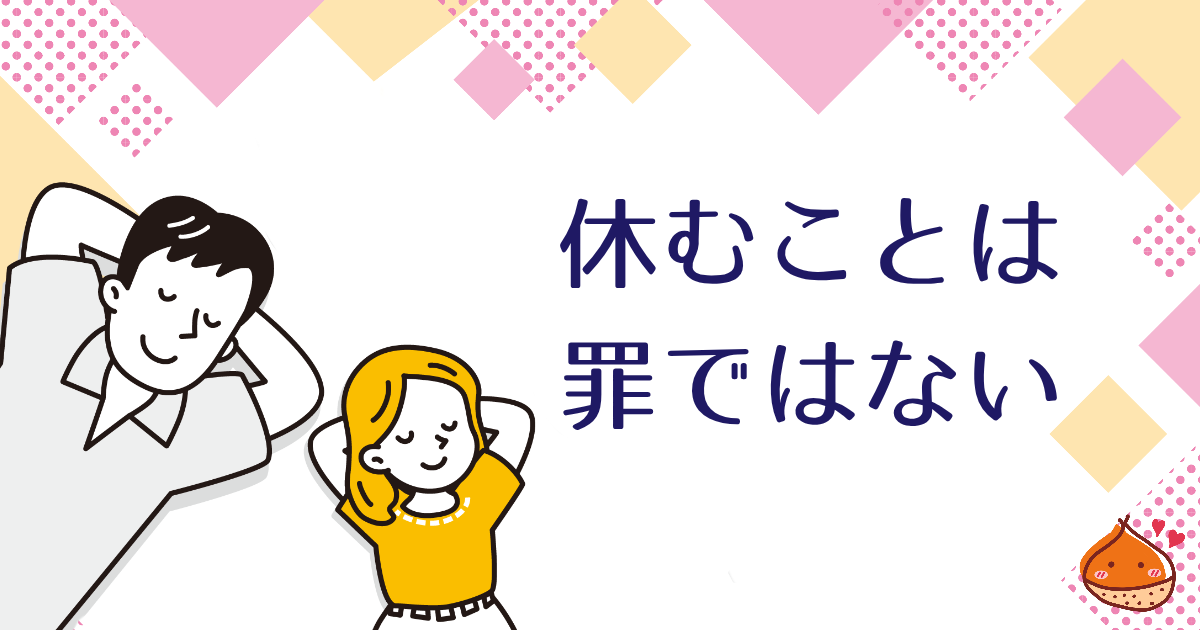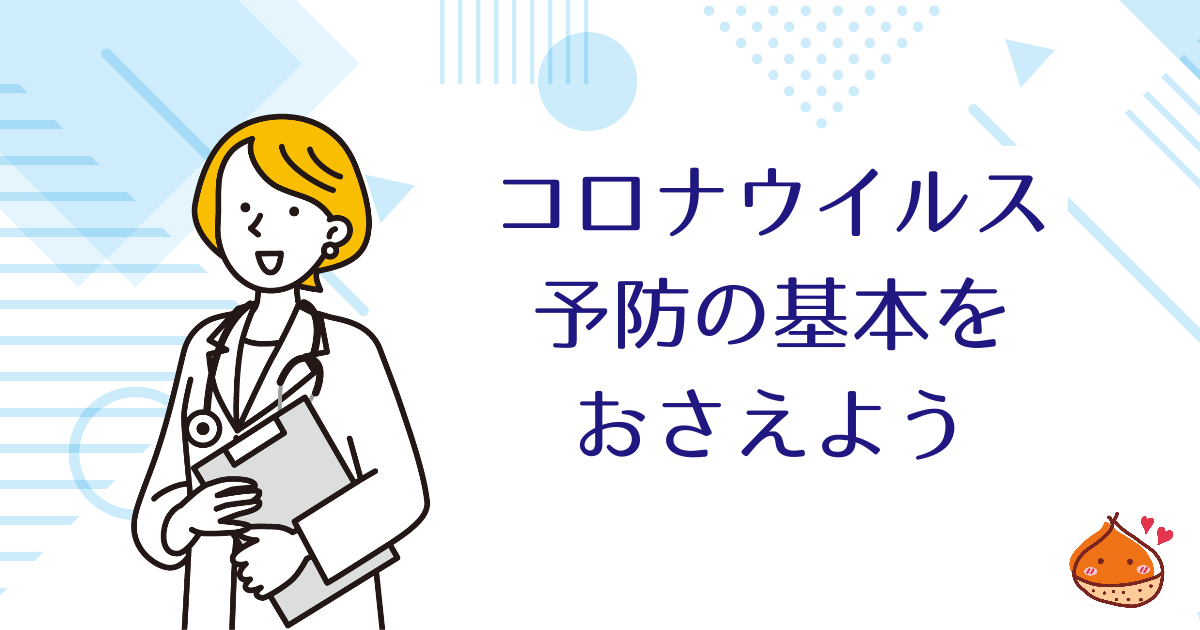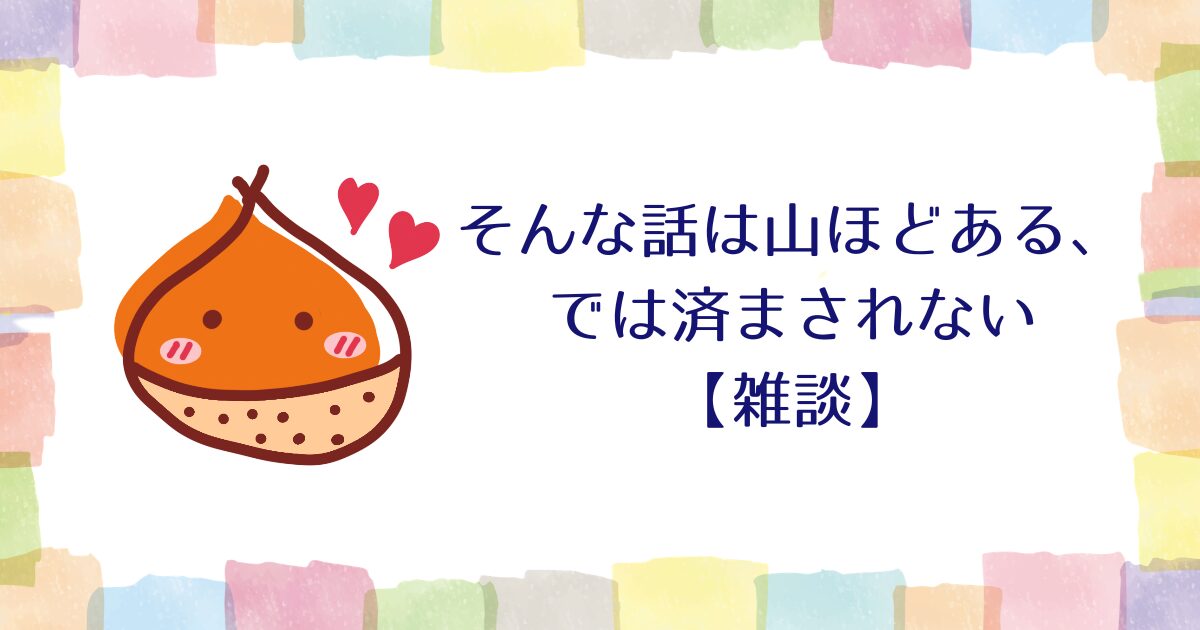私たちの体調を知るうえで、一番身近で基本となるのが「体温」です。
発熱は風邪やインフルエンザ、さらには重大な病気のサインになることもあります。
家庭に体温計がない、または壊れたまま放置しているという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
体温を正しく把握できなければ、病気の見極めや受診の判断も遅れてしまいます。
また、人によって平熱には差があるため、自分や家族の普段の体温を知っておくことがとても大切です。
この記事では、体温測定の重要性や体温計の選び方・使い方をわかりやすく紹介していきます。
なぜ体温を測ることが大切なのか
体温を測ることは、健康管理においてもっとも基本的で大切な習慣のひとつです。
人の体温は常に一定に保たれているように見えますが、実際にはわずかな変動があります。その変動の背景には、感染症や炎症といった体内での異変が隠れていることがあります。
特に「発熱」は、体がウイルスや細菌と戦っているサインであり、体の防御反応でもあります。
体温を測ることで、こうした異変をいち早く察知することが可能になります。平熱を普段から知っておけば、ちょっとした変化にも敏感に気づくことができます。
例えば、自分の平熱が36.5度の人が37.2度になった場合、それだけでも体に何らかの負担がかかっている証拠になります。
逆に、平熱がもともと低めの人にとっては、37度でも「微熱」以上の意味を持つこともあります。また、子どもや高齢者は体温の変化に特に注意が必要です。
子どもは体温調節機能が未発達で、発熱しやすい特徴があります。高齢者は逆に体温上昇が目立ちにくく、感染症を見落としやすい危険があります。
どちらの場合も、日常的な体温チェックが健康を守る重要な手段となります。
体温を測る習慣は、体調不良の早期発見につながります。病気が進行する前に医療機関を受診する判断材料にもなります。
さらに、感染症の拡大を防ぐためにも「体温チェック」は社会的な意味を持っています。自分自身の体を守るだけでなく、周囲への配慮にもつながるのです。
毎日の健康管理において、体温計はもっとも身近なツールのひとつです。「なんとなく元気だから大丈夫」と思わず、体温を確認する習慣を持つことが大切です。
小さな数字の変化が、大きな健康リスクを教えてくれることも少なくありません。
体温計の種類と特徴
体温計にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や使いやすさがあります。
もっとも一般的なのは デジタル体温計 で、短時間で測定でき、表示も見やすいため家庭用として広く普及しています。脇の下や口内で使用できるタイプが多く、日常的な体調チェックに適しています。
次に、耳式体温計 は耳の中(鼓膜付近)の温度を測定するもので、数秒で結果がわかります。小さな子どもはじっとしていられないことが多いため、素早く測れる耳式は特に便利です。
ただし、耳垢や測定の角度によって誤差が出ることがある点には注意が必要です。
最近よく使われているのが 非接触式体温計 です。
おでこにかざすだけで測れるため、感染対策の場面で重宝されています。接触せずに測れるので衛生的ですが、環境や距離によって正確さに差が出ることがあります。
これから新しく体温計を選ぶ場合にはデジタル体温計がもっともおすすめです。
正しい測り方
体温を正しく測るためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。
まず、毎日同じ時間帯に測定することで比較がしやすくなります。特に、朝起きてすぐや夜寝る前など、安静な状態で測ると基準が作りやすいです。
体温は測定する部位によって差が出ます。
一般的には わきの下 が家庭でよく使われますが、口内 のほうがやや高めに出る傾向があります。
また、耳式体温計 は鼓膜付近の温度を測るため、より迅速に測定できます。
ただし、測定の前に注意したいこともあります。
運動直後や入浴直後 は体温が一時的に上がってしまうため、正しい数値が得られません。食事や飲み物を摂った直後の口内測定も誤差が出るので避けましょう。
測定中はなるべく動かず、落ち着いた状態で測ることが重要です。
体温計の表示が安定してから結果を確認しましょう。毎回記録しておけば、自分の平熱や体調の変化に気づきやすくなります。
平熱と発熱の目安
体温には個人差があり、平熱は36.0~37.0℃程度と幅があります。そのため、自分自身や家族の平熱を把握しておくことがとても大切です。
平熱が低めの人は36.0℃前後で安定していることもありますし、やや高めの人は37.0℃近くが通常の場合もあります。
つまり、他人と比べるのではなく、自分の基準を知ることがポイントです。
体温が37.5℃以上になると、多くの場合「発熱」と判断されます。学校や職場でも、この数値を目安に出席停止や出勤見合わせが求められることがあります。
さらに、38℃以上になると、感染症や炎症などの可能性が高まり、日常生活に支障が出やすくなります。
この場合は、早めに医療機関の受診を検討すると安心です。
ただし、高齢者や子どもは体温が急に上がることも多く、数値以上に体調の変化を重視することが必要です。「顔色が悪い」「ぐったりしている」などの様子があれば、すぐに対応しましょう。
体温は数字だけでなく、その人の平熱や体調の変化とあわせて判断することが重要です。
防災・非常時にも重要
災害時や停電などの非常時には、生活環境が大きく変化します。
特に避難所生活では、多くの人が集まるため、体調確認が欠かせません。体温計があれば、発熱の有無を早く察知し、感染症の拡大を防ぐことができます。
コロナやインフルエンザなどの感染症対策にも、体温チェックは必須です。
避難所では「咳をしている」「体調が悪そう」といった人を迅速に把握することが重要です。
その際、数値として体温を示すことは、周囲や医療関係者への説明にも役立ちます。また、体温は熱中症や脱水症状の兆候を判断する指標にもなります。
高齢者や子どもは体温変化に気づきにくいため、特に注意が必要です。非常用バッグに体温計を入れておくことで、いざというときに安心感が得られます。
軽量で電池持ちのよいデジタル体温計を選んでおくと便利です。
防災の備えとして「水・食料」だけでなく、体温計も必需品に加えておきましょう。
日常生活用具給付等事業の給付活用を
厚生労働省では、日常生活用具給付等事業を行なっています。
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者などの方に対して、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与しています。
電気式たん吸引器、盲人用体温計など用具の支援を受けられますので、対象の方はぜひ活用を検討してくださいね。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
まとめ
体温を測ることは、体調を知るためのもっとも基本的で確実な方法です。
発熱は体の異変を知らせるサインであり、早期に気づくことで重症化を防ぐことができます。
平熱を把握しておけば、ちょっとした変化にも敏感に気づけます。
また、災害時や避難所生活でも、体温計があれば感染症の拡大を防ぐ大きな助けとなります。
水や食料と同じように、体温計は一家に一台必ず備えておきたいアイテムです。
日常の体調管理はもちろん、非常時の命を守る準備にもつながります。
健康を守る第一歩として、今日から体温計を活用してみませんか。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。