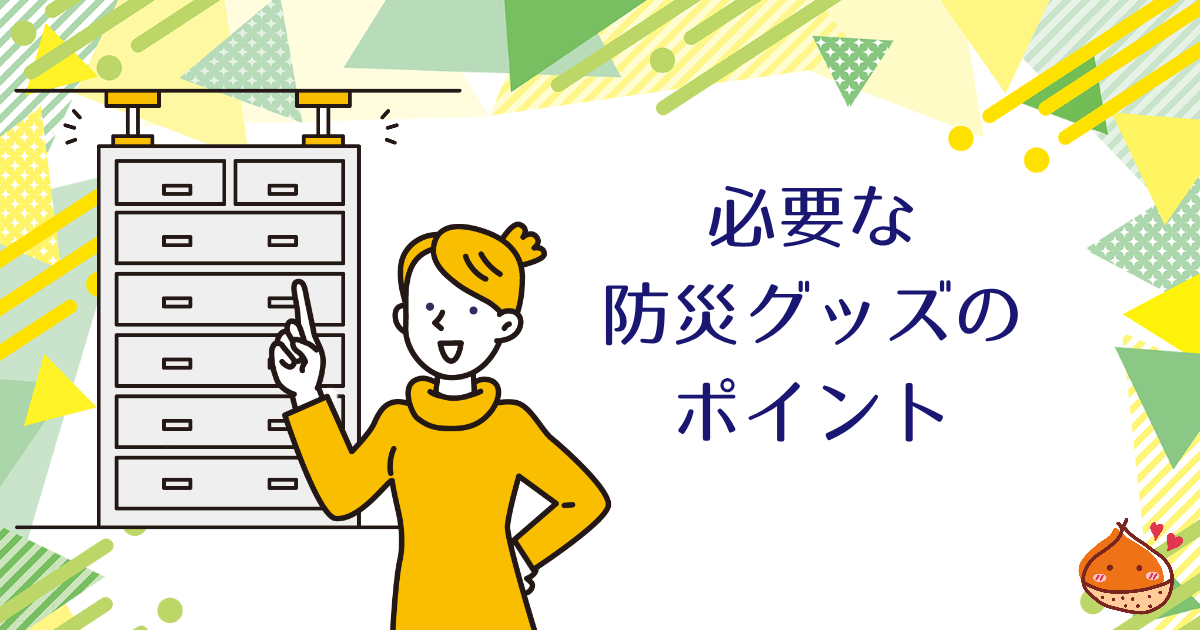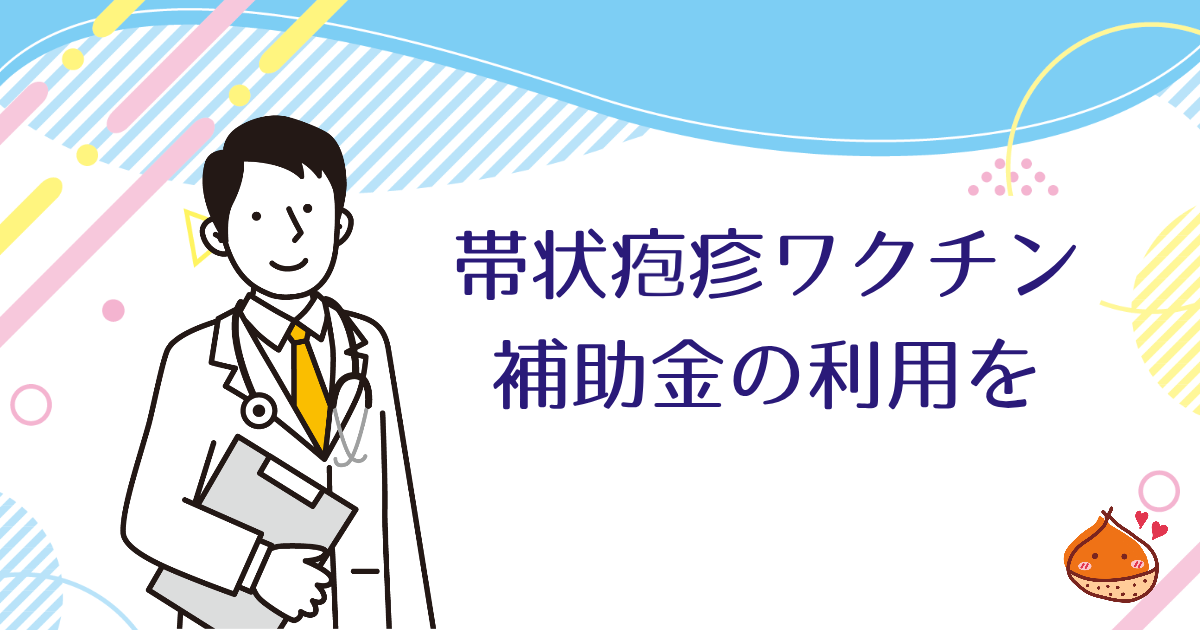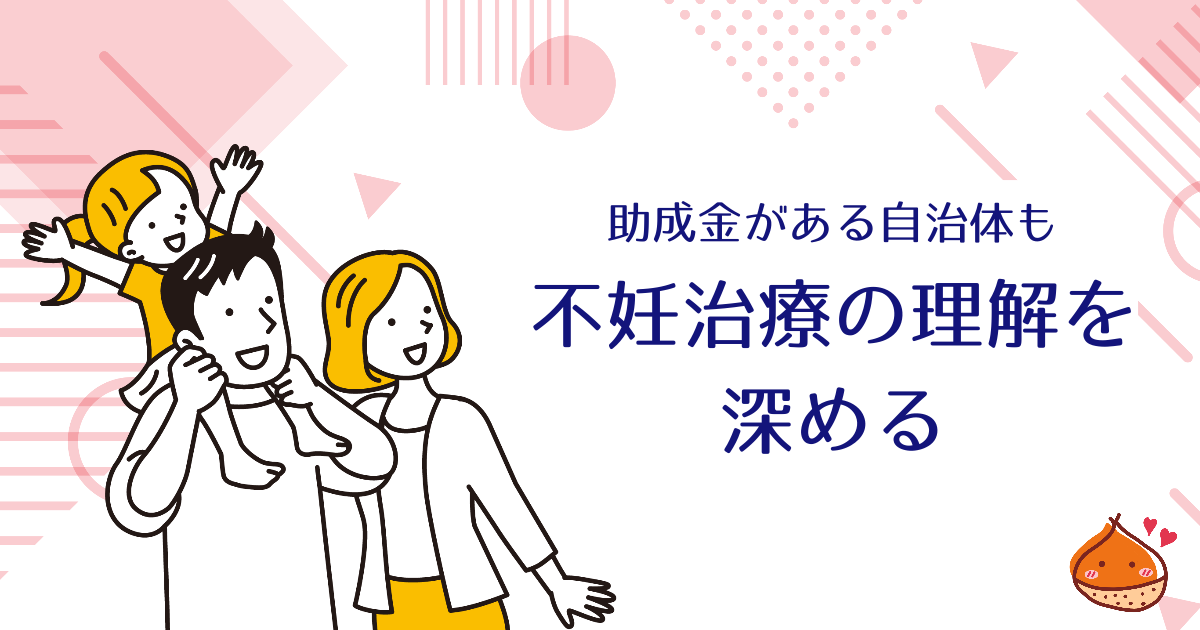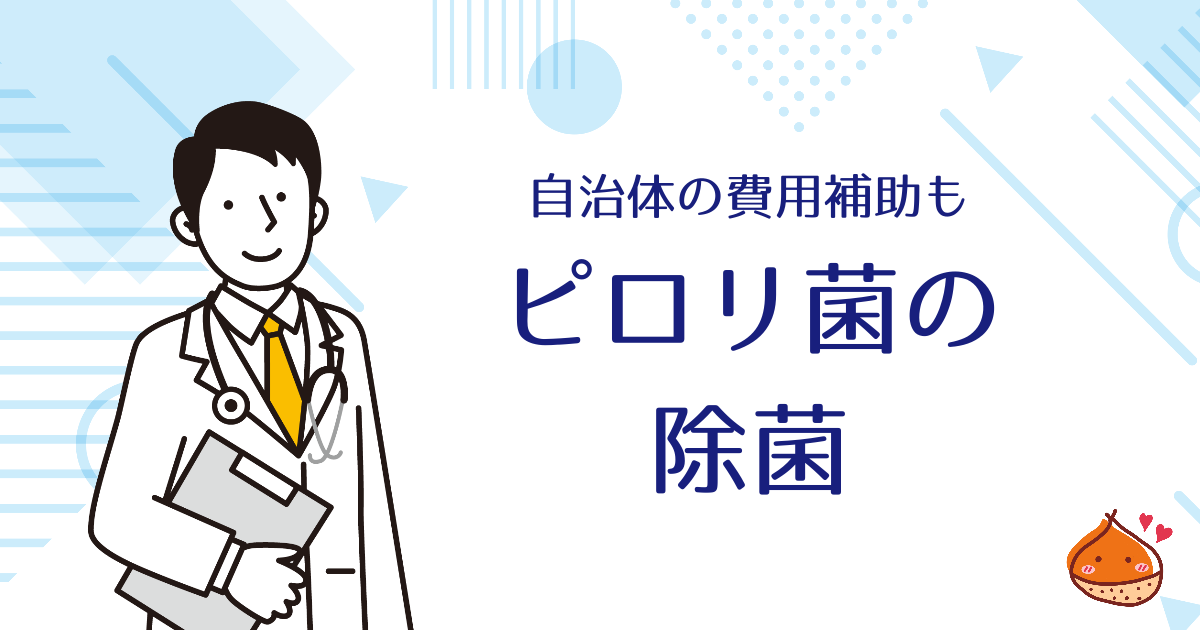
日本人の胃がん患者さんの99%以上に、実は「ピロリ菌」という細菌が関与していることをご存じでしょうか。
「遺伝だから仕方ない」と思っている方もいますが、そうではありません。
ピロリ菌を除菌することで、胃がんのリスクを大きく下げられることが明らかになっています。
しかも検査や治療は、健診やクリニックで比較的簡単に受けられる時代になりました。
「自分は元気だから大丈夫」と思っている人ほど、知らないうちに感染しているケースもあります。
放っておくと慢性的な胃炎や潰瘍につながり、最終的にがんのリスクを高めてしまいます。
だからこそ、早めの検査と除菌がとても大切です。
この記事では、ピロリ菌と胃がんの関係、検査・治療の流れ、そして生活習慣でできる予防法についてご紹介します。
ピロリ菌の基礎知識
胃の中に住みつく細菌で、胃酸に強い性質を持つ
ピロリ菌は、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」という細菌です。
通常、多くの細菌は強い胃酸の中では生きられません。
しかしピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を作り出し、胃酸を中和する力を持っています。
この働きによって、胃の粘膜に住みつくことができるのです。ピロリ菌が胃にとどまると、粘膜が慢性的に刺激を受けます。
その結果、慢性胃炎や胃潰瘍、さらに胃がんのリスクが高まります。「胃の中に細菌がいる」というのは不思議ですが、実際に日本人の多くが感染している現実があります。
感染経路(主に幼少期に家族間での経口感染)
ピロリ菌は主に幼少期に感染すると考えられています。
大人になってからの新規感染は非常に少ないとされています。感染経路の代表例は、家族間での食べ物の口移しや、同じ箸やスプーンの共有です。
特に衛生環境が整っていない時代や地域で、感染が広がりやすい傾向がありました。水や食事を介しても感染する可能性があります。
近年の日本では感染率は減っていますが、40代以上では感染者が多いのが実情です。
つまり「子どもの頃に感染し、そのまま大人になった」という人が多いのです。
感染しても自覚症状がないことが多い
ピロリ菌に感染していても、多くの人は自覚症状がほとんどありません。
胃の粘膜で炎症が進んでいても、痛みや違和感が出ないことが珍しくないのです。そのため「健康だと思っていたのに、健診で初めて感染が分かった」というケースもよくあります。
自覚症状がないまま慢性胃炎が進行すると、将来的に胃潰瘍や胃がんのリスクが高まります。
また、胃の不調があっても「ただの胃もたれ」と思って放置されることも多いです。ピロリ菌感染の有無は、血液・尿・便・呼気検査などで調べることができます。
「無症状=安心」ではないことを知っておくことが大切です。
ピロリ菌と胃がんの関係
慢性的な胃炎や胃潰瘍の原因に
ピロリ菌は胃の粘膜に定着し、炎症を引き起こす性質があります。
その結果、慢性胃炎が長く続くことになります。炎症が進行すると、胃の防御機能が弱まり、胃酸の影響を受けやすくなります。
これが胃潰瘍や十二指腸潰瘍の大きな原因になるのです。
実際、潰瘍を繰り返す患者さんの多くからピロリ菌が検出されます。ピロリ菌は「胃のトラブルの温床」といえる存在なのです。
除菌を行うことで、潰瘍の再発率は大きく減少します。
長期間感染が続くと、胃の粘膜にダメージが蓄積し、胃がんリスクが高まる
ピロリ菌に長く感染していると、胃の粘膜が絶えずダメージを受け続けます。
NHK きょうの健康 胃がん 最新情報 「ピロリ菌 除菌で予防」ピロリ菌が体内に侵入し、胃に長く住み着くと、胃の粘膜が壊され、炎症が起こります。
これが 「ピロリ感染胃炎」 です。ピロリ菌に感染すると、数週間~数か月後に、ピロリ感染胃炎がほぼ100%の確率で起こります。
ピロリ感染胃炎を放置していると、その一部で胃潰瘍や十二指腸潰瘍を発症します。また、一部で10~20年を経て胃の粘膜が萎縮し、胃液が十分に分泌されなくなる 「萎縮性胃炎」 に進行します。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、直接胃がんの原因にはなりませんが、萎縮性胃炎が進行すると胃がんを発症しやすくなります。まれに、内視鏡検査で萎縮性胃炎と診断されていない場合でも、ピロリ感染胃炎から胃がんを発症することもあります。
https://www.nhk.jp/p/kyonokenko/ts/83KL2X1J32/episode/te/WJ4Z2P5282/(参照:2025-09-09)
つまり、ピロリ菌感染を放置するほど胃がんリスクは高まります。
早めの検査と除菌治療が、将来の大きな病気を防ぐために有効です。「今は症状がないから大丈夫」とは言えない理由がここにあります。
世界的にもピロリ菌と胃がんの因果関係は認められている
ピロリ菌と胃がんの関係は、世界中の研究で裏付けられています。
世界保健機関(WHO)の関連機関は、ピロリ菌を「発がん因子」と公式に認定しています。
日本でも、胃がん患者の99%以上がピロリ菌に感染していたというデータがあります。
このことから「胃がん予防には、まずピロリ菌の除菌が重要」とされています。実際に除菌を行った人では、胃がんの発症率が有意に低下することが確認されています。
医療現場でも「除菌は最も効果的な一次予防」と位置づけられています。世界的に見ても、ピロリ菌対策は胃がん減少の鍵を握っているのです。
ピロリ菌の検査方法
血液・尿・便・呼気による非侵襲的な検査
ピロリ菌の有無を調べる方法として、まず挙げられるのが非侵襲的な検査です。
血液検査では、ピロリ菌に対する抗体を測定し、感染の有無を推測します。尿検査や便検査も同様に、抗体や抗原を調べて判定します。
さらに「呼気検査」では、専用の薬を飲んだあとに吐いた息を採取し、ピロリ菌の活動を確認します。
これらは身体への負担が少なく、短時間で結果が出るのが特徴です。特に呼気検査は精度が高く、除菌後の効果判定にも広く使われています。
内視鏡検査と組み合わせて行うケース
場合によっては胃カメラ(内視鏡検査)と併用されることもあります。
内視鏡で直接胃の粘膜を観察し、生検(組織の一部を採取)することで、ピロリ菌を顕微鏡で確認できます。この方法は、胃炎や潰瘍の状態を同時に評価できる点がメリットです。
特に、すでに胃の不調がある人や、がんの早期発見を兼ねたい人に適しています。
一方で、身体への負担はやや大きく、準備や時間がかかります。
非侵襲的検査と内視鏡検査を組み合わせることで、より確実な診断が可能になります。
健診や人間ドックで手軽に受けられる
ピロリ菌検査は、一般的な健康診断や人間ドックでも実施されています。
特に血液検査や尿検査は導入が簡単で、多くの健診で標準的に組み込まれています。
40歳以上を対象に、自治体が検査を助成しているケースもあります。
「症状がないけれど不安」という方でも、気軽に受けやすいのが特徴です。一度調べておくことで、自分のリスクを知り、必要に応じて除菌治療につなげられます。
早めのチェックが、将来の胃がん予防の第一歩になるといえるでしょう。
自治体によっては費用補助も
自治体によっては、ピロリ菌除菌治療費の補助を行っているところもあります。
例えば、京都府ではピロリ菌除菌治療費の一部を助成してくれます。
引用:京都府 ピロリ菌除菌治療費の一部を助成します!健康診断、人間ドック、市町村検診等でピロリ菌感染やその疑い(胃炎など)があると判明した方が行う保険適用の一次除菌治療に要する経費の一部を助成します。
https://www.pref.kyoto.jp/gan/pyro.html(参照:2025-09-09)
また、加入している保険組合によっては費用を補助する団体もあります。
検査や除菌を検討している方は、お住まいの自治体・加入している保険組合に一度問い合わせてみてくださいね。
ピロリ菌の除菌治療
保険診療で受けられる
ピロリ菌の除菌治療は、胃炎や胃潰瘍などの診断があれば健康保険の適用対象となります。
そのため、自己負担を抑えて治療を受けられるのが大きなメリットです。
最近では健診などで感染が見つかれば、医師の判断で治療を勧められるケースもあります。
抗菌薬と胃酸抑制薬を併用する治療法
治療の基本は、抗菌薬2種類と胃酸を抑える薬を1週間ほど服用する方法です。
胃酸を抑えることで薬の効果を高め、ピロリ菌を死滅させやすくします。
短期間で終えられるため、身体への負担も比較的少ないのが特徴です。
成功率は70〜90%、再除菌も可能
1回目の除菌での成功率はおおよそ70〜90%とされています。
もし失敗しても、薬を変えて再除菌を行うことができます。
再挑戦することで、さらに高い確率で除菌に成功するケースが多いです。
除菌後も定期的な検査が必要
除菌が成功したとしても、胃の粘膜のダメージが完全に回復するわけではありません。
そのため、定期的に内視鏡検査を受け、胃の状態をチェックすることが推奨されます。
特に胃がんのリスクが高い人は、長期的なフォローが大切です。
除菌のメリットと注意点
ピロリ菌を除菌する最大のメリットは、胃がんの発症リスクを大幅に下げられることです。
長期間の感染でダメージを受けた胃粘膜も、除菌後は回復しやすくなります。
さらに、慢性的な胃炎や胃潰瘍の再発予防にもつながります。再発を繰り返すことで生活の質が下がるのを防げる点は、大きな安心材料です。
ただし、除菌治療には抗菌薬を使用するため副作用が出ることもあります。
具体的には、下痢・腹痛・発疹・味覚の変化などが一時的に起こる可能性があります。
そのため、治療を受ける際には医師とよく相談し、自分の体調に合った方法を選ぶことが大切です。副作用が強い場合や薬が合わない場合も、医師の判断で対処してもらえます。
生活習慣の見直しも大切
塩分・喫煙・飲酒は胃がんリスクを高める
塩分を多く摂取すると胃の粘膜が傷つき、ピロリ菌の悪影響を受けやすくなります。
また、喫煙は胃粘膜の修復力を下げ、胃酸分泌を増加させて炎症を悪化させる要因です。アルコールも過剰に摂取すると胃の粘膜を直接刺激し、がん化のリスクが高まります。
これらの生活習慣は単独でも危険ですが、組み合わさるとリスクはさらに上昇します。
除菌治療を受けても、不適切な生活習慣を続ければ再発の可能性が残ります。
そのため、塩分控えめ・禁煙・節度ある飲酒を心がけることが大切です。
生活習慣の改善は、薬では補えない予防効果をもたらします。日常の小さな習慣の積み重ねが胃を守る第一歩です。
野菜・果物をしっかり摂取し、バランスの良い食生活を
野菜や果物に多く含まれるビタミンCや食物繊維は、胃の粘膜を保護する働きがあります。
抗酸化作用により、発がん性物質の影響を軽減できる点も注目されています。さらに、食物繊維は腸内環境を整え、消化機能の改善にも役立ちます。
肉や脂っこい料理が中心の食事は、胃への負担や生活習慣病のリスクを増やします。
「主食・主菜・副菜」を意識した食事バランスが、胃の健康を保つ基本です。彩り豊かな食卓を心がけることが、自然と栄養バランスを整えます。
外食が多い方も、野菜の多いメニューを選ぶように意識すると効果的です。日々の食習慣を少しずつ変えることが、大きな予防につながります。
規則正しい生活で免疫力を保つ
不規則な生活や睡眠不足は、免疫力を低下させ、病気にかかりやすくなります。
免疫力が落ちると、除菌後の再感染リスクや炎症の悪化にもつながりかねません。
十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理は胃の健康を支える大切な要素です。とくに運動は血流を良くし、自律神経のバランスを整える効果があります。
また、ストレスは胃酸の分泌を増やし、胃の粘膜を刺激するため注意が必要です。
規則正しい生活リズムを意識するだけでも、体調は大きく変わります。免疫力を維持することは、胃がん予防や消化器の健康維持に直結します。
生活習慣の見直しは、薬や検査と同じくらい重要なセルフケアです。
まとめ
ピロリ菌は胃の病気に深く関わる存在ですが、検査や除菌治療によってリスクを大きく減らすことができます。
除菌後も生活習慣を見直すことで、胃がんや再発の予防効果を高められます。日々の食事や生活リズムを整えることは、自分自身の体を守る最良の方法です。
「検査」「治療」「生活改善」をバランスよく組み合わせることが、健康長寿につながります。気になる症状がある方や健診で指摘を受けた方は、早めに医師へ相談しましょう。
胃の健康を守ることは、将来の安心と豊かな生活への投資です。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
NHK きょうの健康 胃がん 最新情報 「ピロリ菌 除菌で予防」
https://www.nhk.jp/p/kyonokenko/ts/83KL2X1J32/episode/te/WJ4Z2P5282/(参照:2025-09-09)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
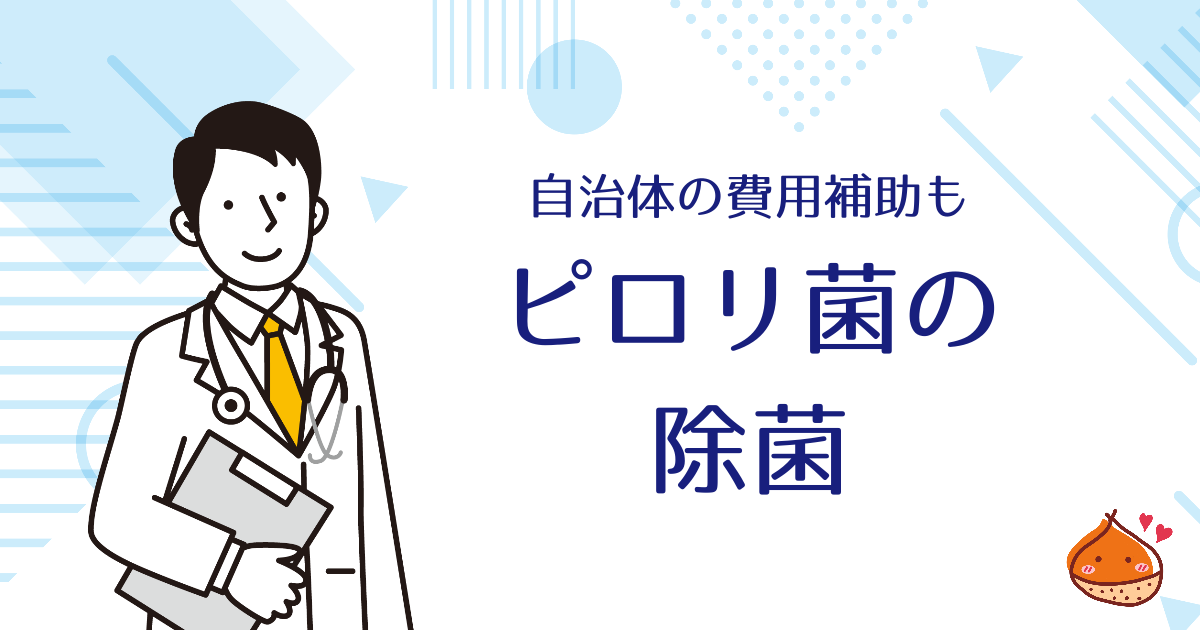
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。