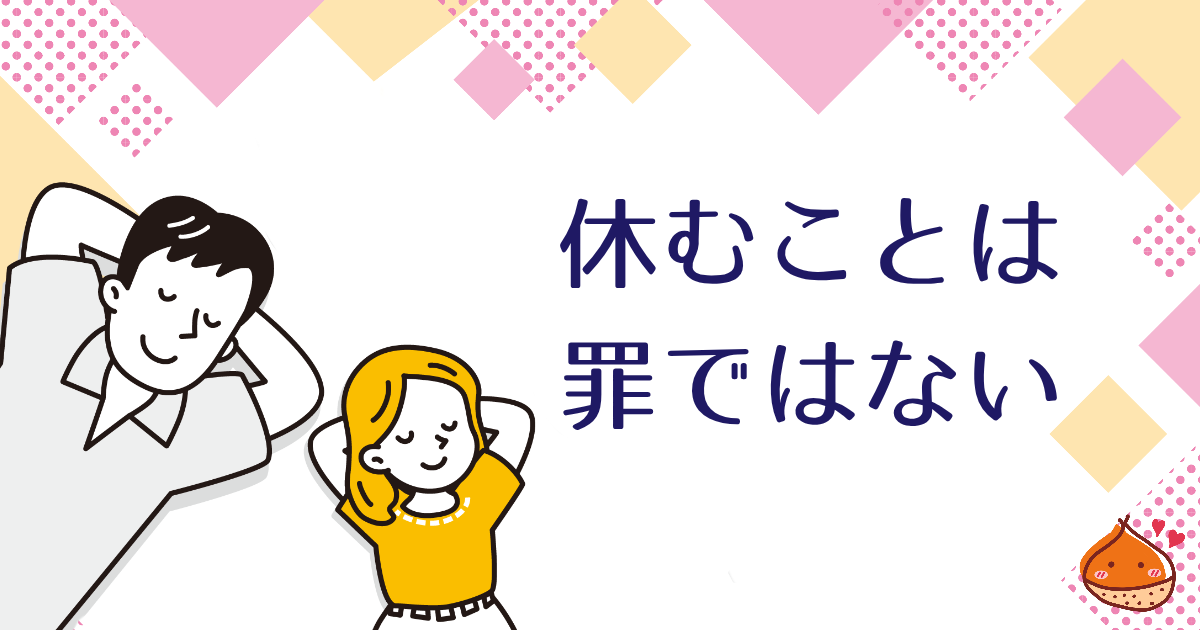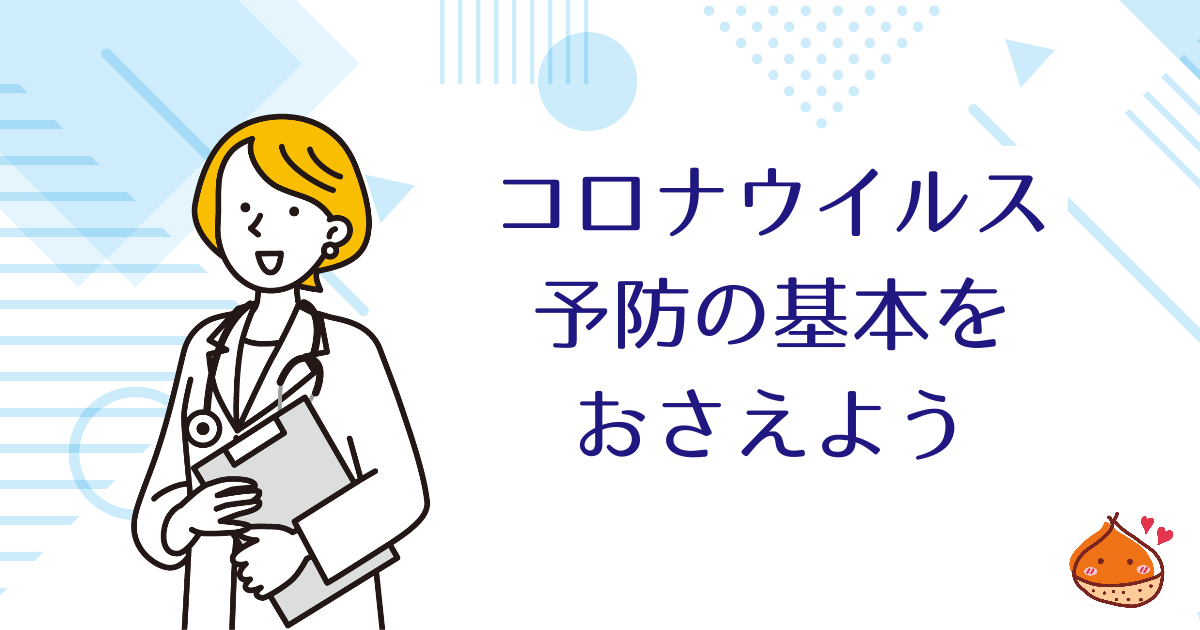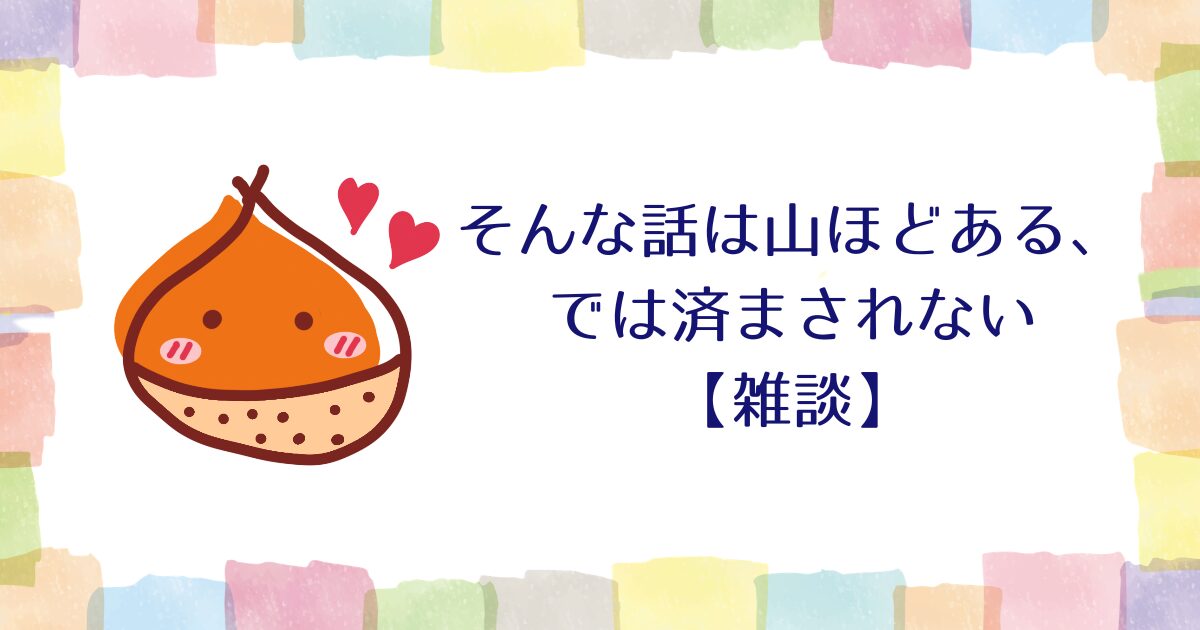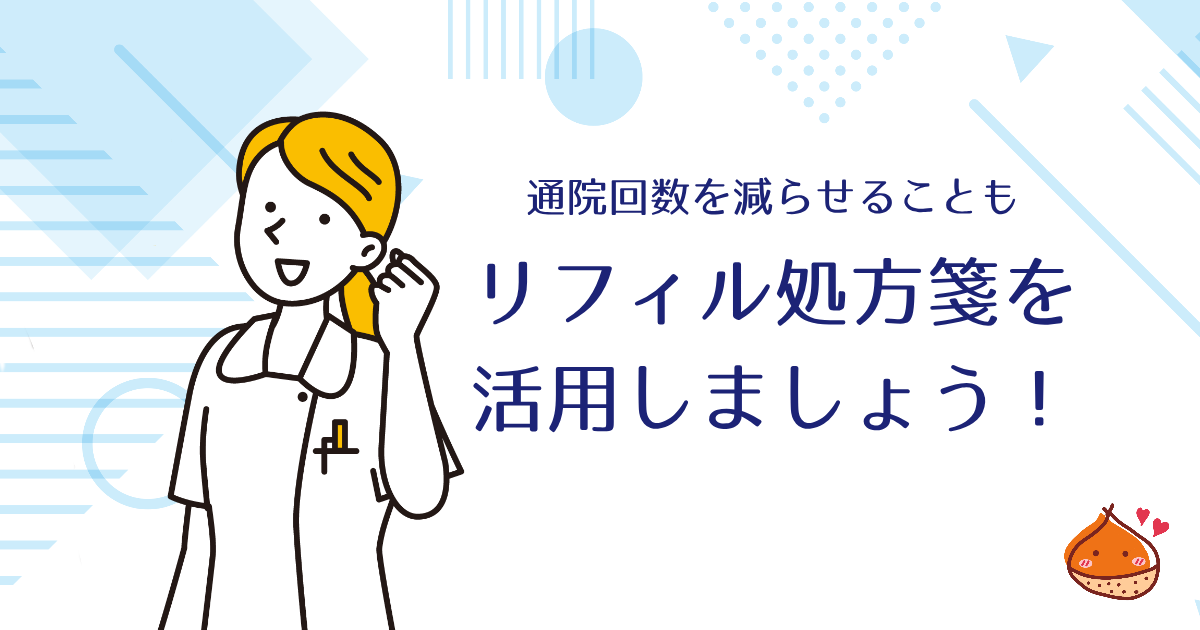
忙しい日々の中で、「病院に通う時間がなかなか取れない」と悩む方も多いのではないでしょうか?
そんな方に役立つ制度が「リフィル処方箋」です。令和4年度(2022年度)から導入されたこの仕組みは、症状が安定している患者さんが対象で、医師の判断により、1回の診察で最大3回まで薬をもらうことができます。
リフィル処方箋の基本知識
引用:政府広報オンライン 「リフィル処方箋」を知っていますか?1度の診察で最大3回まで薬の処方を受けられます!1通で、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋
「リフィル処方箋」は、症状が安定している患者で一定の要件を満たした場合に、医師が定めた期間内に最大3回まで繰り返し使用可能な処方箋で、令和4年度(2022年度)に導入されました。
通常の処方箋では、医師が決めた日数分の薬を1回だけ受け取れますが、リフィル処方箋では、診察を1回受けて1通の処方箋を発行してもらうだけで、一定の間隔で最大3回まで繰り返し薬を受け取ることができます。処方の期間は薬や症状などに応じて医師が個別に判断します。
※リフィル(refill)とは詰め替えの意味です。
https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html(参照:2025-07-21)
「リフィル(refill)」とは、英語で「詰め替え」の意味。
リフィル処方箋を使えば、毎回病院で診察を受けなくても、薬局で薬を受け取ることができます。
たとえば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、アレルギー性鼻炎などの慢性疾患で定期的に薬を服用している方にとっては、通院の負担が減り、時間の節約にもつながるでしょう。
リフィル処方箋のメリット
通院回数が減るので、時間を有効活用できる
リフィル処方箋の大きなメリットのひとつは、通院回数を減らせることです。
通常の処方箋では、薬がなくなるたびに病院に行く必要がありますが、リフィル処方箋なら最大3回まで薬局で薬を受け取れます。
そのため、病院に行く時間や待ち時間を大幅に短縮できます。
仕事や家事、育児などで忙しい方にとっては、自由に使える時間が増えるのは大きなメリットです。
また、病院が混み合う時期や体調が良くない時でも、無理に外出する必要がなくなります。
高齢者や持病を持つ方にとっても、通院の負担軽減につながります。
時間を有効活用しながら、薬の服用を継続できるのがリフィル処方箋の魅力です。
診察料が毎回かからないため、結果的に医療費を抑えられることも
リフィル処方箋を利用すると、医療費の負担が軽くなる場合があります。
通常の処方箋では、薬をもらうたびに診察を受け、その都度診察料がかかります。
しかしリフィル処方箋なら、初回の診察料だけで済み、以後は薬局で薬を受け取るだけなので、診察料が不要です。
これにより、結果的に医療費全体が抑えられるケースもあります。
例えば、生活習慣病で月1回通院していた方が、リフィル処方箋を利用すると、年に数回分の診察料が節約できます。
家計にとっても負担が減り、経済的なメリットが期待できます。
ただし、薬代や薬局での服薬指導料は別途必要になる点は覚えておきましょう。
服薬が途切れる心配が少なくなる
リフィル処方箋を使うと、薬を切らしてしまうリスクが減ります。
通常の処方箋では、通院の予定が合わなかったり、忙しくて受診できなかったりすると、薬がなくなってしまうことがあります。
しかし、リフィル処方箋なら、事前にまとめて繰り返し薬をもらうことができるため、薬が途切れる心配が少なくなります。
例えば、高血圧や糖尿病の薬は、飲み続けることが大切ですが、薬が切れてしまうと健康に悪影響を与えることも。
リフィル処方箋は、こうした「薬の中断」を防ぐための仕組みとして役立ちます。
薬局に行くだけで薬を受け取れるため、忙しい方にも便利な制度です。
注意点
リフィル処方箋を利用できる条件を満たす必要がある
リフィル処方箋は誰でも利用できるわけではありません。
「症状が安定している患者」に限られ、医師が「薬剤師の管理のもと、繰り返し処方しても問題ない」と判断した場合のみ発行されます。
また、すべての薬がリフィル処方箋の対象になるわけではありません。
湿布薬や向精神薬、新薬などは対象外です。
引用:政府広報オンライン 「リフィル処方箋」を知っていますか?1度の診察で最大3回まで薬の処方を受けられます!医師が「リフィル可能」とした患者が対象
リフィル処方箋の発行にはいくつかの条件があります。まず、対象となるのは「症状が安定している患者」のみで、「薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復使用が可能」と医師が判断した場合です。リフィル処方箋が処方される疾病としては、高血圧や糖尿病などの生活習慣病やアレルギー性鼻炎などの慢性疾患で、定期的に通院している患者が対象となることが多くなっています※。
ただし、処方できる薬は限定されており、新薬・湿布薬・向精神薬など一部の薬は処方ができません。医師の判断によってリフィル処方箋の処方となった場合は、処方箋に設けられた「リフィル可」の欄のチェックボックスにレ点と適用回数が記入されます。
※リフィル処方箋の発行は、患者の病状等を踏まえ、医師が判断するため、これらの疾病であれば必ず発行されるものではありません
https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html(参照:2025-07-21)
薬局では、薬剤師が服薬状況を確認し、問題がないと判断した場合に限り薬を渡します。体調に変化があれば、途中でも必ず医師に相談しましょう。
リフィル処方箋は大切に保管を
リフィル処方箋は、同じ処方箋を最大3回まで使用することができます。そのため、1回目の薬を受け取った後も、処方箋は大切に保管しなければなりません。
もし処方箋をなくしてしまうと、次回の調剤を受けることができなくなってしまいます。「紙の処方箋を何回も持ち歩くのは不安…」と感じる方もいるでしょう。
そんなときにおすすめなのが「電子処方箋」の活用です。電子処方箋なら、処方箋の原本が電子データとして管理されるため、紛失の心配がありません。
リフィル処方箋について、医師と相談してみましょう

リフィル処方箋が気になる方は、通院時に医師に「リフィル処方箋にできますか?」と相談してみましょう。
引用:政府広報オンライン 「リフィル処方箋」を知っていますか?1度の診察で最大3回まで薬の処方を受けられます!継続的に同じ薬を服用しているようなかたで、リフィル処方箋を利用したい場合は、まずは、かかりつけの医師に相談してみることをおすすめします。ただし、患者にリフィル処方箋が適しているかどうかは、あくまで医師が判断することなので、毎回医師の診察が必要となる場合もあります。
https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html(参照:2025-07-21)
自分では「症状が安定している」と感じていても、医師が見ると長期的な観点から慎重な判断が必要な場合もあります。自己判断せず、医師の判断を仰いでください。
人によって病状や生活習慣が異なるため、一律には決められません。また、リフィル処方箋には、保管方法や、次に薬を受け取れる期間(調剤可能期間)の決まりがあります。
このため、自己管理がきちんとできるかどうかも重要な条件になります。
診察回数が減る分、薬剤師と密にコミュニケーションを取り、薬の使い方や体調の変化についてよく相談することも必要です。
患者自身が「いつもと違う」と感じたときは、すぐに医療機関に相談する心構えも持ちましょう。
医師が「リフィル可」と判断した場合は、処方箋の「リフィル可」欄にチェックと回数が記載されます。なお、リフィル処方箋には「次回の受け取り期限」があります。期限内に薬局で薬を受け取るように注意しましょう。
まとめ
リフィル処方箋は、患者さんの負担を減らし、医療資源の効率的な活用にもつながる制度です。
慢性疾患で通院を続けている方は、ぜひかかりつけ医や薬剤師に相談してみてください。
自分の体調に合わせた医療の選択肢を知ることが、健康管理の第一歩です。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
横浜市 リフィル処方箋について
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/kenko/refill.html(参照:2025-07-21)
厚生労働省 長期処方・リフィル処方の活用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken14/index_00014.html(参照:2025-07-21)
政府広報オンライン 「リフィル処方箋」を知っていますか?1度の診察で最大3回まで薬の処方を受けられます!
https://www.gov-online.go.jp/article/202411/entry-6756.html(参照:2025-07-21)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
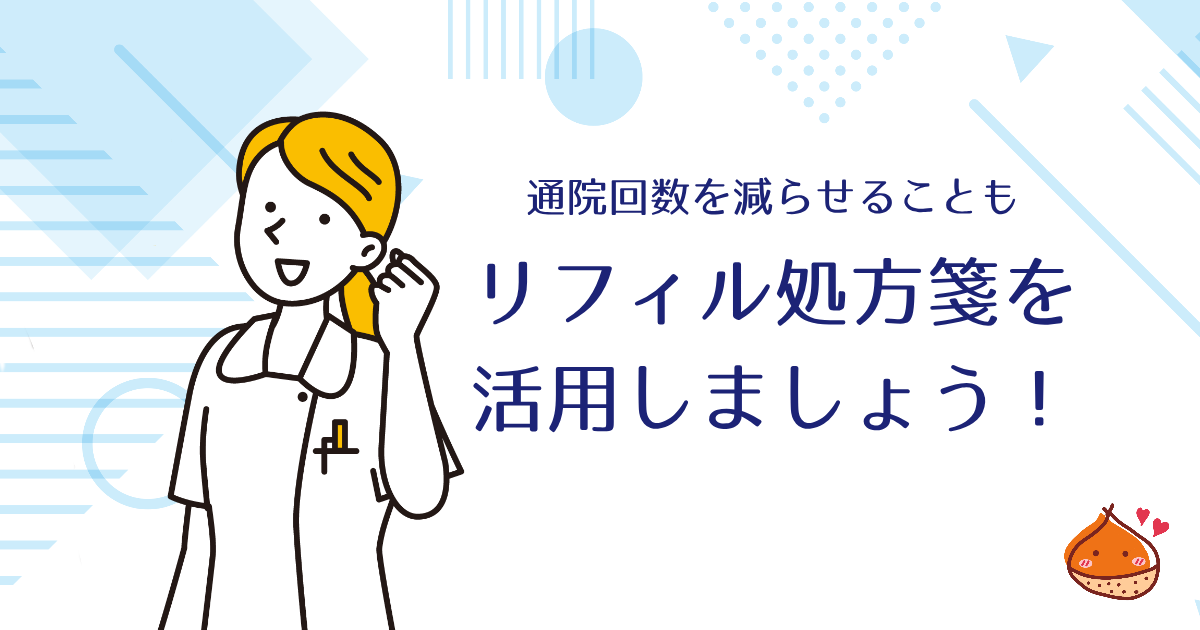
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。