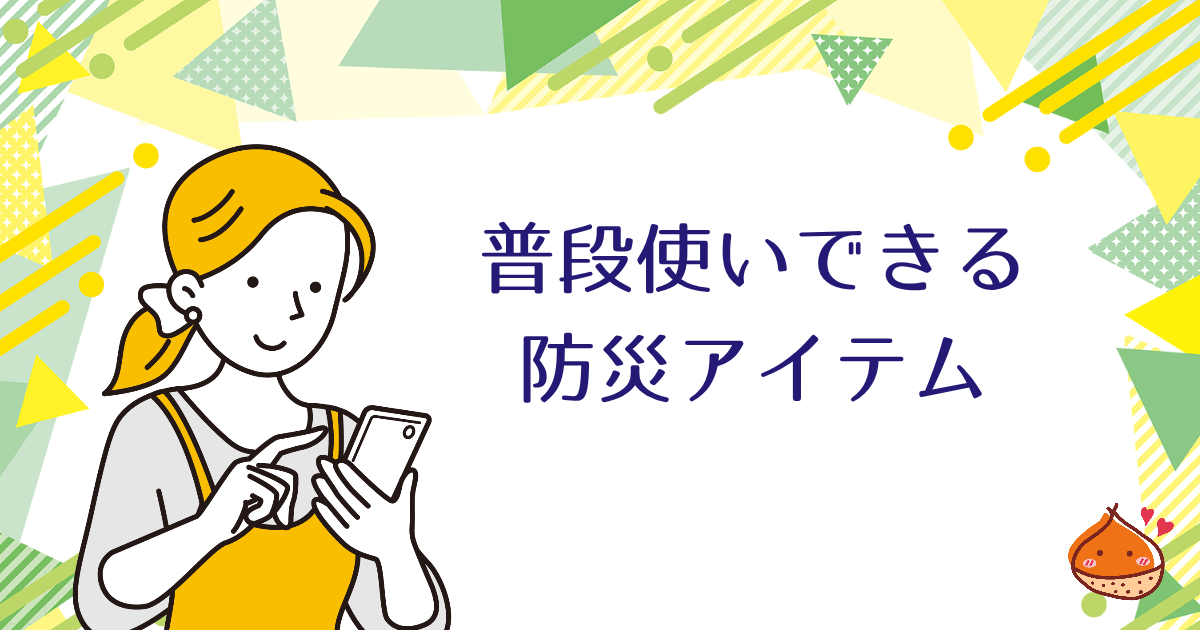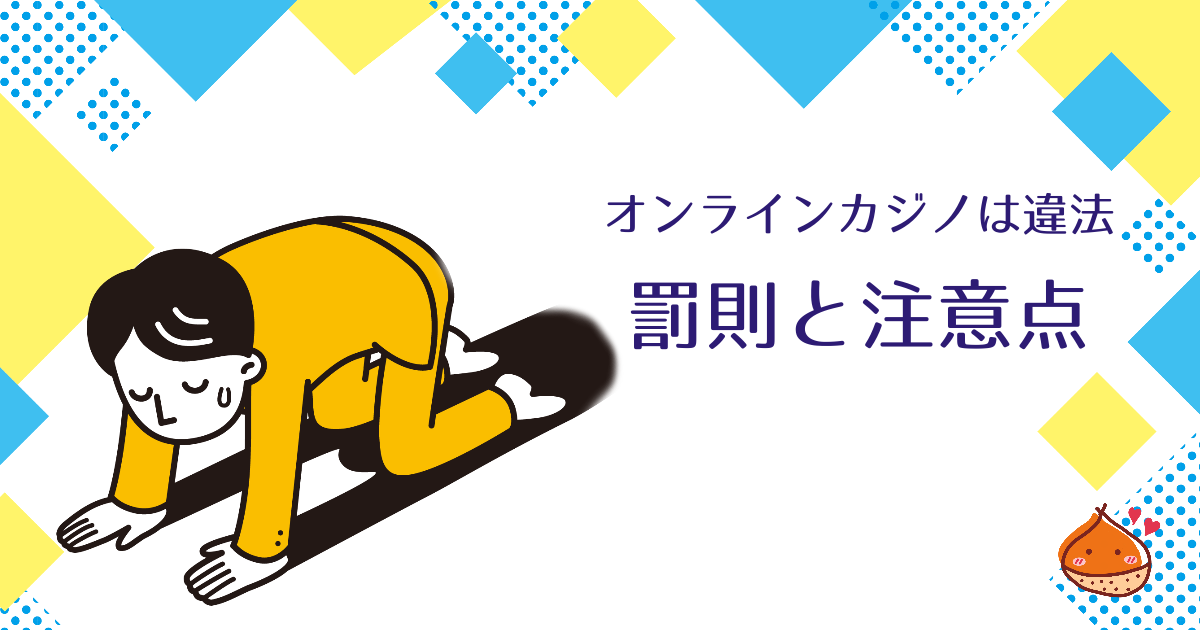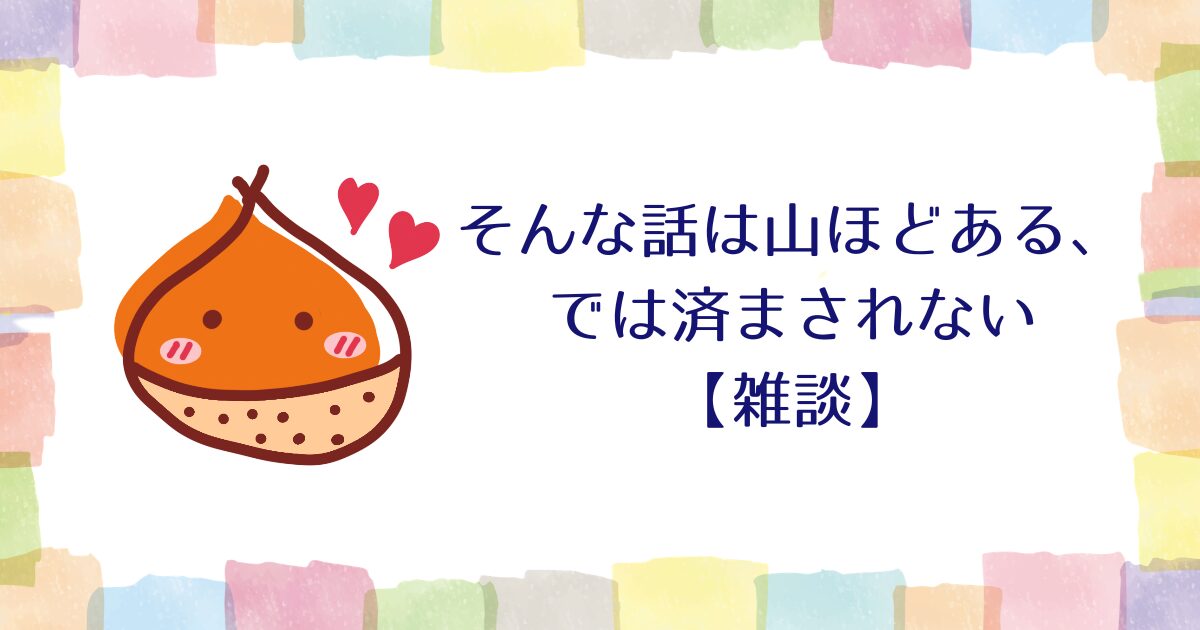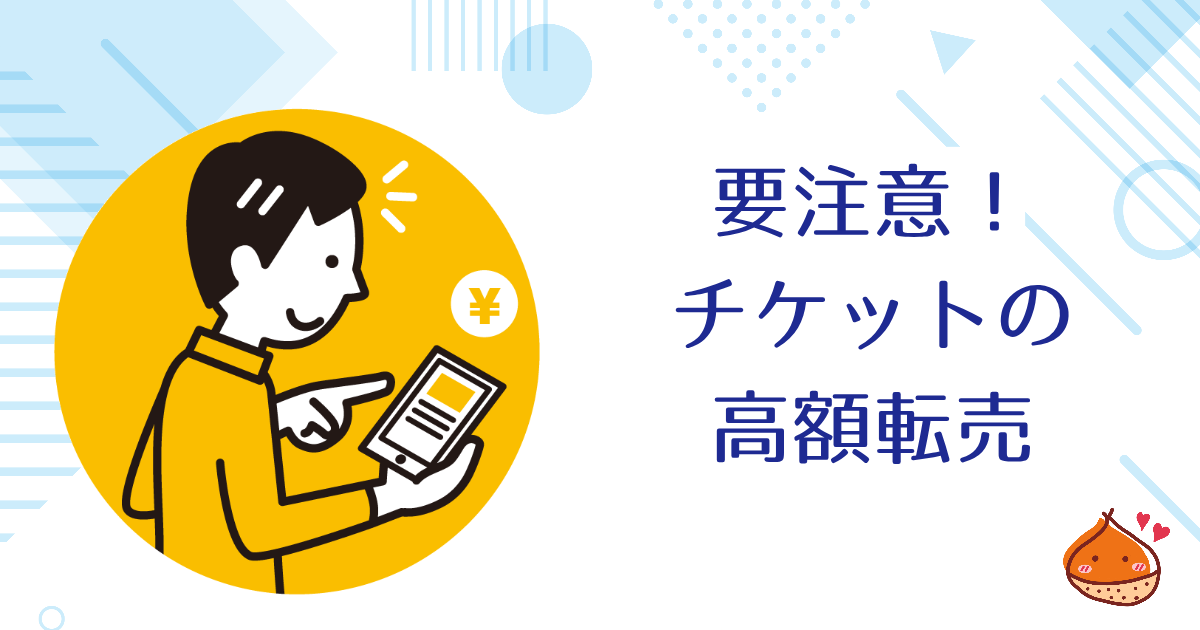
近年、人気イベントのチケットが高額で転売されるケースが増えています。
SNSやフリマアプリで「チケット譲ります」といった投稿を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
一見、個人同士のやり取りに見えても、それが違法行為に該当する可能性があることをご存知でしょうか?
2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」は、こうした転売行為を明確に違法とし、厳しく取り締まるものです。
チケット不正転売禁止法とは?
「チケット不正転売禁止法」は、正式には「興行チケットの不正転売の禁止に関する法律」です。
2019年6月14日から施行され、興行主の同意なしに、有償でチケットを譲渡することを禁止しています。
対象となるのは「特定興行入場券」と呼ばれるチケットで、次の3つの条件を満たすものです。
- 座席指定などの特定があること
- 興行主によって正規に販売されたこと
- チケットに購入者の氏名・連絡先などが記載されていること
つまり、映画・音楽・演劇・舞踊・スポーツなどのイベントのチケットが広く対象になります。
引用:政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。
禁止される行為は
- 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
- 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
「特定興行入場券」とは
不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。
- 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
- 興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。
- 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
なお、招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者又は入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは、「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html(参照:2025-07-10)
チケットの高額転売は誰も幸せにならない
チケットの高額転売は、消費者と主催者の両方に大きな悪影響を及ぼします。
まず、正規のルートで購入できなかったファンが、やむを得ず転売サイトで定価の何倍もの金額を支払うことになり、経済的な不利益を被ります。例えば、5,000円のチケットが5万円で出回るようなケースも少なくありません。
これはイベントを心から楽しみたい人たちの機会を奪い、「お金を出せる人しか参加できない」不公平な環境を生みます。
さらに、転売チケットによる入場トラブルや偽造問題が多発すれば、興行主の信頼も損なわれます。
「このイベントは安心して参加できない」と見なされれば、次回以降のチケット販売やブランドイメージにも悪影響が出るでしょう。
その結果、イベントの収益性が低下し、将来的な開催の継続にも支障をきたすことがあります。
つまり、高額転売は一部の転売業者が利益を得るだけで、多くの人に損失と不信感をもたらす行為なのです。
違反するとどうなる?
この法律に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
個人であっても、利益を得る目的での転売であれば処罰の対象になります。
「転売目的じゃなかった」「友人に譲っただけ」と思っていても、金銭を受け取った時点で有償譲渡にあたる可能性があります。
知らずに関わると、刑事責任を問われるケースもあるため、注意が必要です。
転売チケットでは入場できないことも
さらに、転売されたチケットではイベント会場に入れない場合もあります。
多くのイベントでは、本人確認が求められるようになってきており、
チケットに記載された名前と身分証が一致しないと入場を拒否されるケースも。
正規の価格より高く購入した上に、会場にも入れない…そんな悲しい事態を避けるためにも、
不正な転売チケットには手を出さないことが大切です。
転売チケットの主なトラブル例
入場を拒否される
転売で購入したチケットだと判明した場合、会場で入場を断られることがあります。特に本人確認が必要なイベントではほぼ確実に弾かれます。
偽造チケットをつかまされる
写真や画像を使ったチケット詐欺が横行しており、チケット番号やバーコードを真似た「偽造チケット」が送られてくるケースもあります。
高額転売による損失
本来5,000円のチケットが、転売で2万円以上で購入されてしまうことがあり、イベント中止や入場不可となった場合、返金もされず損失だけが残るという事態に。
チケットが届かない/ドタキャンされる
個人間取引で「当日手渡し」などを約束していたが、連絡がつかなくなり、当日すっぽかされるトラブルも報告されています。
法的リスクを負う可能性も
転売をしていた側が不正転売禁止法に違反していた場合、購入した側も状況によってはトラブルに巻き込まれる可能性があります。
安心・安全にチケットを購入するには
チケットを安心・安全に購入するためには、正規ルートを利用することが鉄則です。
たとえば、公式サイトや認定プレイガイド(e+、チケットぴあ、ローソンチケットなど)から購入すれば、偽造チケットや不正転売の心配がありません。
また、最近はアーティストやイベント主催者が運営する公式リセールサービスも増えており、やむを得ず行けなくなった場合でも、定価で譲渡できる仕組みがあります。
一方、SNSやオークションサイト、フリマアプリなどで出回るチケットは不正転売の温床になっていることも。高額なうえに、入場を拒否されるリスクもあります。金銭トラブルの元にもなりかねません。
「安く手に入れたい」「今すぐ欲しい」と思っても、焦って非正規ルートに頼るのは避けましょう。正規販売元の情報を事前に確認し、安心して楽しめる観覧体験を選ぶことが大切です。
おわりに
チケット不正転売は、法律に違反するだけでなく、文化・芸術・スポーツの健全な発展を妨げる行為です。
また、善意で購入した人がトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
自分自身の楽しみを守るためにも、チケットは正しい方法で購入・利用しましょう。
「知らなかった」では済まされない時代です。情報を正しく理解し、賢く行動しましょう。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html(参照:2025-07-10)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
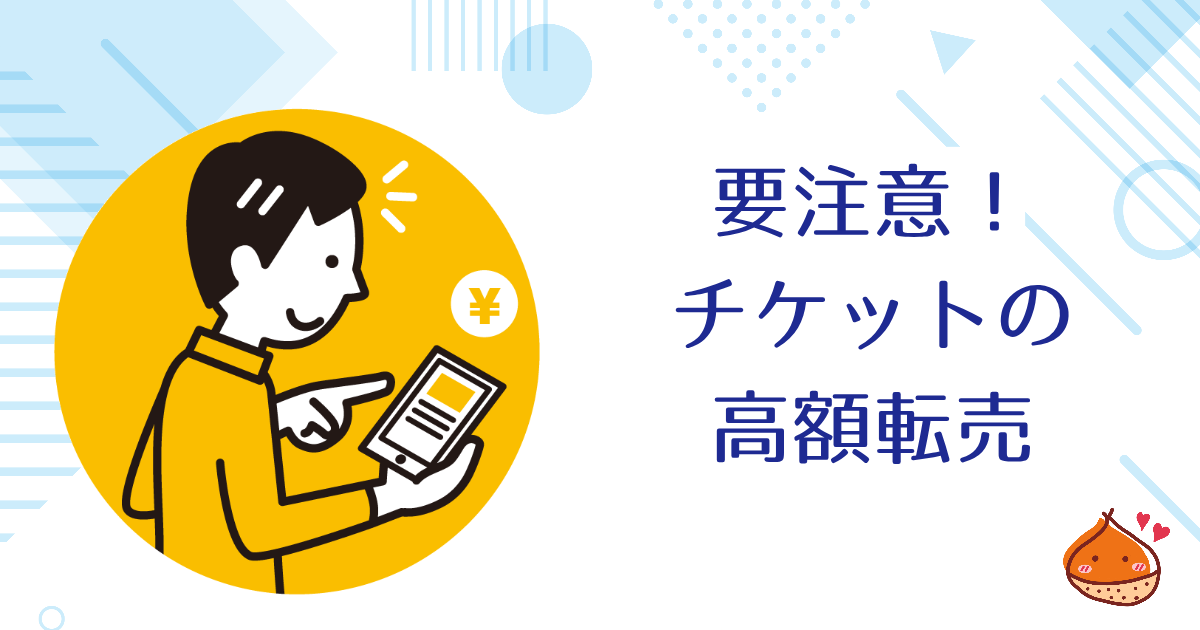
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。