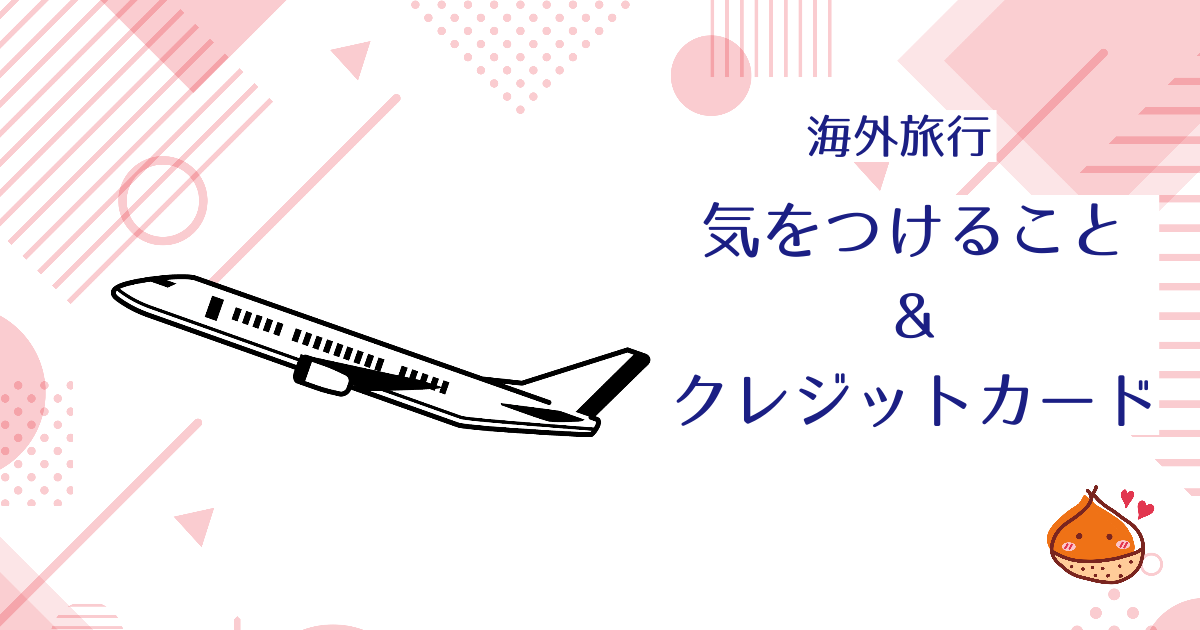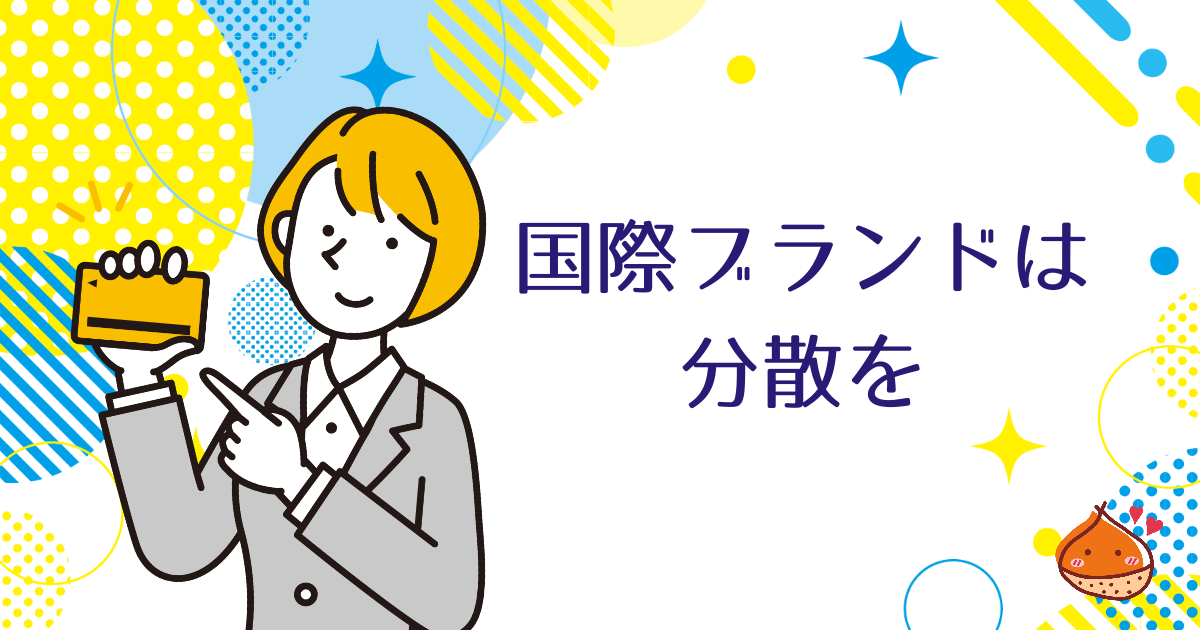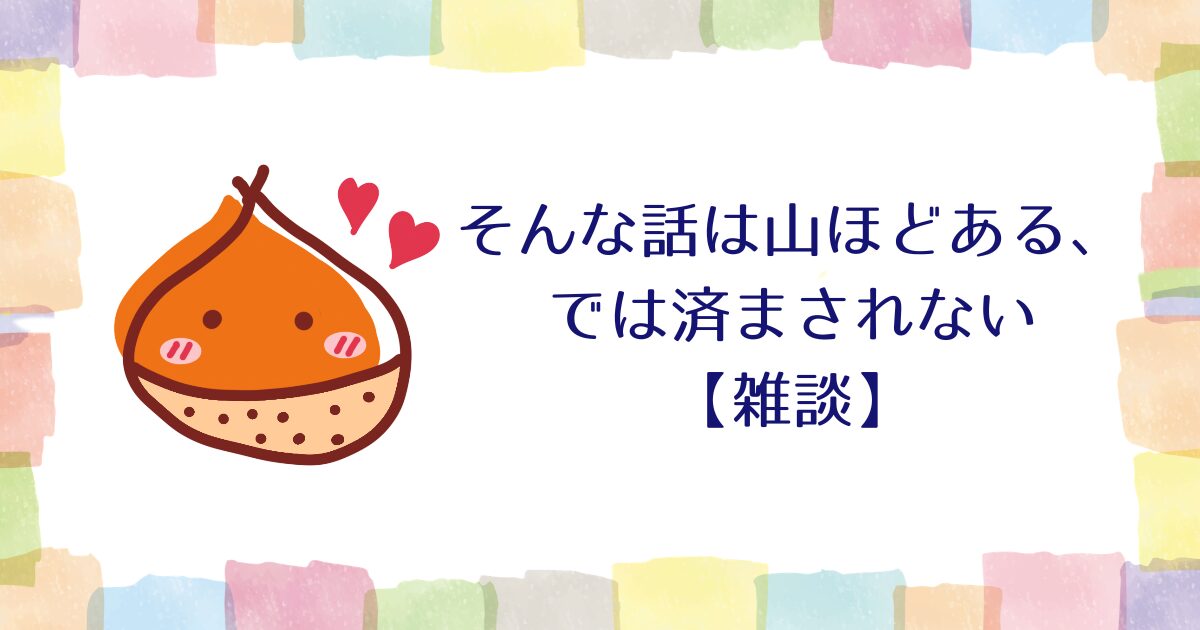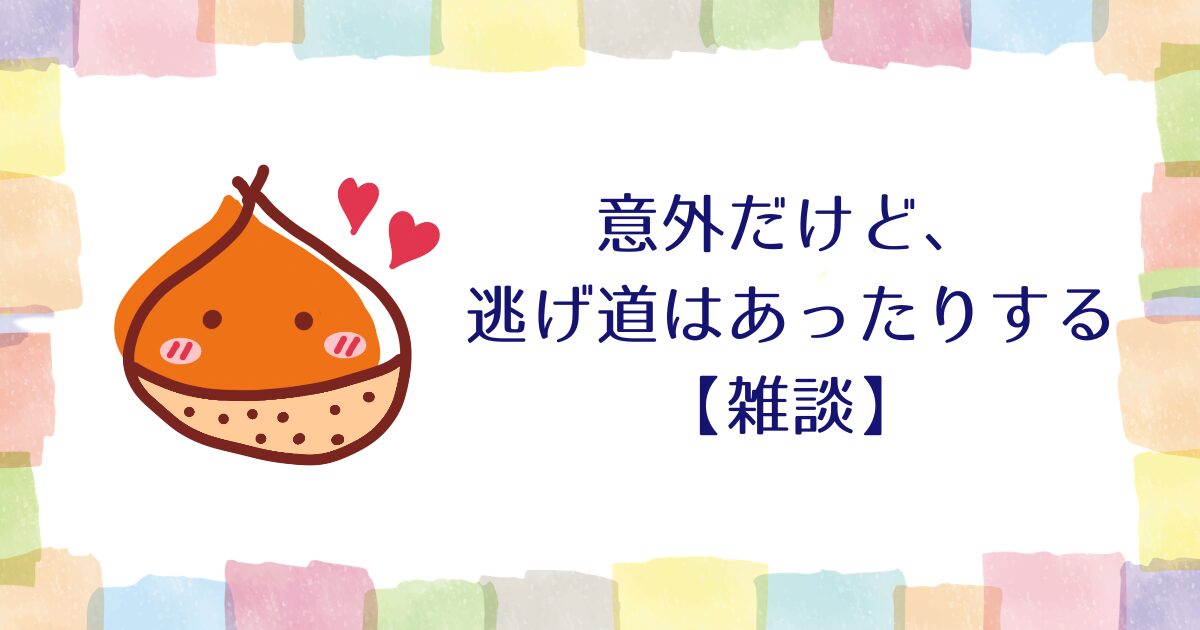「自分の人生をもっと充実させたい」「いつも他人に振り回されてしまう」そんな悩みを抱えていませんか?
でも、自分の人生の選択は自分にしかできません。
「自己決定」 が幸福度に大きく影響を与えることが研究結果でわかっています。
本記事では、なぜ自己決定が幸せにつながるのか、自己決定できない原因、他責思考の怖さ、そして自分軸を育てる方法を詳しく解説していきます。
1. なぜ自己決定が幸せにつながるのか?
神戸大学が行った研究では、国内2万人に対するアンケート調査の結果、所得、学歴よりも「自己決定」が幸福感に強い影響を与えていることを明らかにしました。
引用:神戸大学 所得や学歴より「自己決定」が幸福度を上げる 2万人を調査幸福感に与える影響力を比較したところ、健康、人間関係に次ぐ要因として、所得、学歴よりも「自己決定」が強い影響を与えることが分かりました。
これは、自己決定によって進路を決定した者は、自らの判断で努力することで目的を達成する可能性が高くなり、また、成果に対しても責任と誇りを持ちやすくなることから、達成感や自尊心により幸福感が高まることにつながっていると考えられます。
https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2018_08_30_01/(参照:2025-04-06)
自己決定が幸福につながる理由
また、自己決定が幸福につながる理由は以下のように考えられます。
- コントロール感が得られる
自分で選択した行動は、「自分で決めた」という実感が得られ、ストレスを軽減します。 - 内発的動機づけが高まる
例えば、誰かにやらされる仕事よりも、自分でやりたいと思った仕事のほうが楽しいですよね。責任と誇りを持ちやすくなるのもこれが理由の一つです。 - 後悔しにくくなる
「あのとき、あの人の言うとおりにしなければ…」と後悔することが少なくなります。
2. 自己決定できない原因とは?(環境・思考のクセ・教育など)
では、なぜ多くの人が自分で決めることが苦手なのでしょうか? その原因には、 環境・思考のクセ・教育 などが関係しています。
自己決定を阻む3つの要因
- 環境の影響
「親が決めてきた」「上司に指示される仕事ばかり」という環境だと、自分で決める経験が不足しがちです。 - 思考のクセ
「間違えたらどうしよう」「失敗したら責められる」といった 完璧主義 や 恐怖心 が自己決定を妨げます。 - 教育の影響
日本の教育は「正解を求める」傾向が強く、自由な選択を学ぶ機会が少ないことも要因のひとつです。
3. 他責思考の怖さ
自己決定できない人が陥りがちな思考のひとつが 「他責思考」 です。これは、物事がうまくいかない原因を 他人や環境のせいにする 考え方です。
「こんな状況になったのは、あの人のせいだ」
「うまくいかないのは、会社が悪い、社会が悪い」
一時的には心が軽くなったように感じるかもしれません。ですが、実は他責思考には、大きな落とし穴があります。
成長のチャンスを逃す
失敗や問題が起きたとき、「自分には関係ない」と思考を止めてしまうと、改善点に気づけません。
本当は少しの行動で状況を変えられたかもしれないのに、そこに目を向けられない。結果として、自分自身の成長のチャンスを逃してしまいます。
人間関係が悪化する
他責思考の人は、無意識に周囲を責める発言や態度を取りがちです。
「またあの人のせいだ」「なんでちゃんとしてくれないの?」
そうした言葉や空気感は、人間関係の亀裂を生みます。信頼を失い、孤立してしまうこともあるでしょう。
何も変わらない「現実」
これが一番恐ろしいですよね。「誰かのせい」である限り、自分が動く理由がなくなってしまいます。
でも、誰かが変わってくれる保証はありません。
つまり、何も変わらないのです。自分の未来を他人任せにしている限り、状況も、環境も、現実もそのまま。変えられるのは「自分」だけなのです。
4. 自分軸を育てるためのステップ(具体的な行動)
私たちは日々、さまざまな「選択」をしています。
朝起きる時間、着る服、食べるごはん、出かけるかどうか……。けれども意外と多くの人が、無意識のうちに「流されるまま」に決めていることに気づいていません。
自分の意思で「決定する」ことには、大きな意味があります。
それは自分の人生を「自分の足で歩いている」という感覚を持てるようになることです。
そして、その習慣は小さなトレーニングの積み重ねで育てていけます。
まずは小さなことから決める練習を
いきなり大きな決断を迫られると、人は不安になり、他人に意見を求めたくなります。
ですから、最初は「今日の昼ごはんは何を食べるか」など、ささいなことから自分で決めてみましょう。
ポイントは、「誰かに聞かない」「過去と違う選択をしてみる」こと。
いつものパターンを崩して、自分で「考えて選ぶ」ことがトレーニングになります。
自分の選択に責任を持つ
決めることができたら、その選択に対して「自分が決めた」と意識を持ちましょう。
たとえその結果が満足いくものでなかったとしても、「次にどうすればよくなるか」を考える癖がつくことで、選択の精度も上がっていきます。
自分の決断に責任を持つことは、自信の積み重ねにもつながります。
決定を人任せにしない自分になる
他人の意見や空気を読むことは大切ですが、すべてを周囲に委ねていると、自分の人生のハンドルを他人に渡してしまうことになります。
迷ったときほど、「私はどうしたいのか?」と、自分の心の声に耳を傾けてみてください。
日々の積み重ねが、あなたを「自分で道を選べる人」へと成長させてくれるでしょう。
5. 他人の意見を参考にしつつ、自分で決める方法(バランスの取り方)
「自己決定=独断」ではありません。大切なのは、 他人の意見を取り入れながら、自分で決める ことです。
バランスの取り方
- 他人の意見は情報として受け取る (決めるのは自分)
- 「なぜそう思うのか?」を考える (自分の判断基準を作る)
本を読むなどインプットを増やすことで、自分の判断基準の軸の解像度が上がりますよ - 最後は自分の価値観に従う (納得できる決断をする)
スティーブ・ジョブズも言っていましたが「自分の心は知っている」です。最後は自分の価値観や心に従うのが幸せへの第一歩です。
6. 「自己決定=孤独」ではない!周囲との関係を保つコツ
「自分で決める」と聞くと、「孤独になりそう…」と感じるかもしれません。しかし、 自己決定は人間関係を良好にする ことにもつながります。
周囲との関係を保つ4つのポイント
- 「私はこう思う」を伝える
他人と意見が違っても、「あなたの意見も尊重するよ」と伝えれば関係は壊れません。 - 相手の選択も尊重する
自分が決めたように、相手にも自由な選択の権利があることを忘れないでくださいね。 - 共感を大切にする
自分の考えを押しつけるのではなく、相手の気持ちにも耳を傾けましょう。あなたの生き方にヒントをもたらしてくれるかもしれませんよ。 - 最後は自分で決定するので、他人を責める必要がなくなる
他人を攻撃する必要がなくなるので、信頼が生まれます。また、自分で決定するということが幸福度を高めます。
おわりに
他人の意見を聞くのは決して悪いことではありません。しかし、盲信してしまうとそれは他人の決定のもとで生きていくということ。
他人の決定はあなたを幸せにしてくれません。あなたの幸せをあなた以上に考える人はいないからです。
人生の選択は、自分でするしかありません。あかぐりのサイトも、あなたの背中を押すことはできますが、あなたの代わりに何かを決定することはできないのです・・・。
ですが、お役に立つ情報を提供することはできますし、今後も続けていきます。
自己決定ができると、 自分の人生に責任を持ち、幸福感が高まる ことが科学的にも証明されています。他人の意見を取り入れつつも、最後は自分で決めることで、 より充実した人生 を送ることができます。
今日から 「自分で決める練習」 を始めてみませんか?
<記事を作成するにあたって参考にしたサイト>
神戸大学 所得や学歴より「自己決定」が幸福度を上げる 2万人を調査
https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2018_08_30_01/(参照:2025-04-06)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。