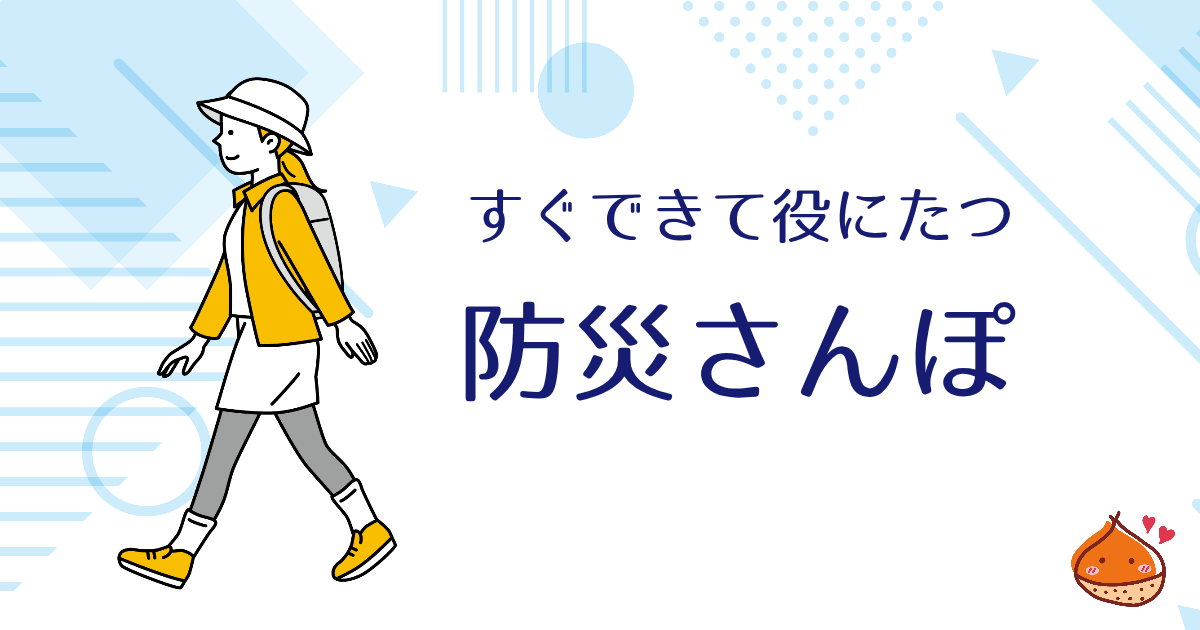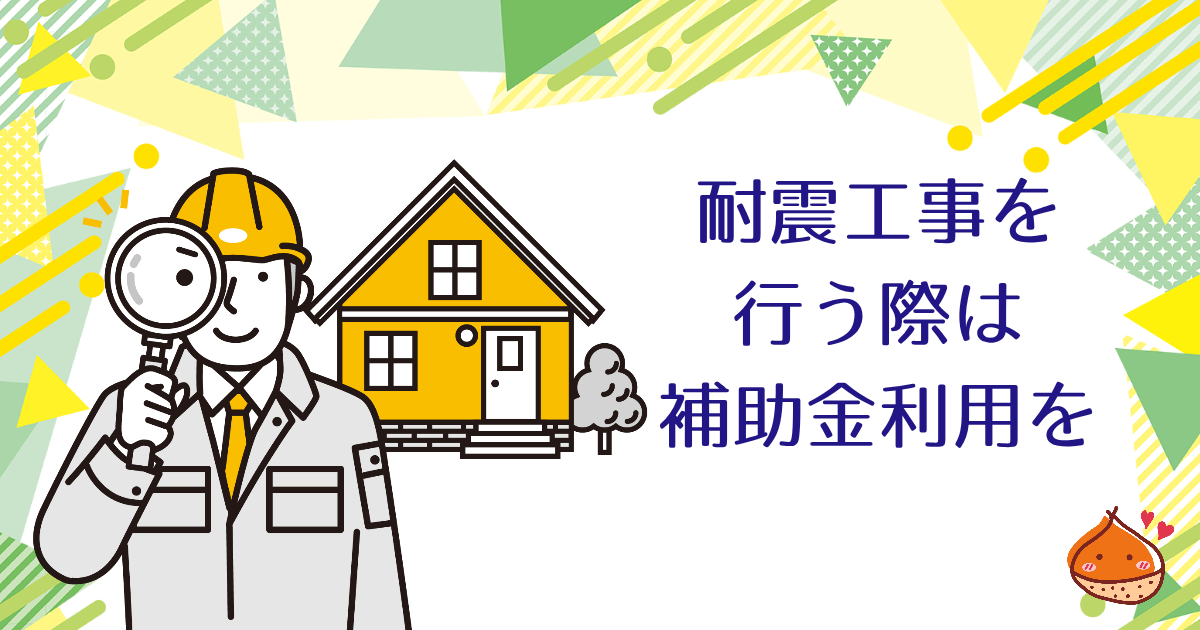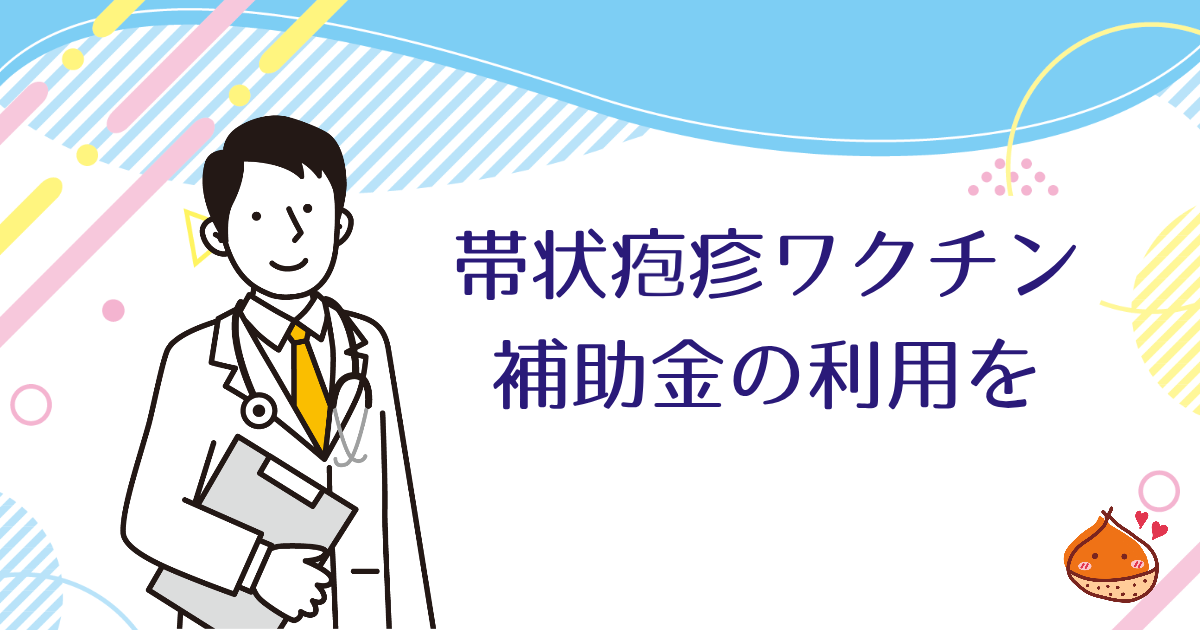台風や突風で飛んだ瓦が隣家や通行人に当たり重大事故につながる――近年、こうした被害が相次いでいます。
伝統的な瓦屋根は美しい反面、留め付けが不十分なまま経年すると強風で飛散しやすくなります。自治体による耐風対策の補助制度を賢く利用して、早めに屋根の安全性を高めましょう。
瓦屋根が強風に弱い理由
瓦屋根は、日本の伝統的な住宅に広く使われてきた美しい屋根材ですが、構造上の特徴から強風に弱い面があります。
まず、古くから用いられてきた土葺き工法では、瓦の下に土を敷き詰め、その重みで瓦を押さえる方法が一般的でした。
この場合、瓦自体が釘やビスで固定されておらず、固定がほぼ重力任せになっていることがあります。
台風や突風などの強風時には、この固定力の弱さが原因で瓦が持ち上げられやすくなります。
さらに、屋根は長年の風雨や日射にさらされ、経年劣化が進みます。
瓦自体が摩耗したり、下地材(野地板・桟木)が腐食や乾燥割れを起こすと、瓦の固定力は一層低下します。釘や金具が錆びたり緩んだ場合も、瓦は風圧で外れやすくなります。
固定の弱い瓦が一枚外れると、その隙間から風が入り込み、周囲の瓦も次々と飛ばされる連鎖が起こりやすくなります。
また、瓦は1枚あたりの重量があり、飛散した場合には人や建物への被害が大きいのも問題です。
現行の建築基準法では、瓦を釘やビスで確実に留める施工が義務化されていますが、古い住宅はその基準を満たしていない場合が多くあります。
そのため、特に築年数が古い瓦屋根は、耐風診断や補強工事を行うことが強く推奨されます。固定方法の改善(全数釘打ち、金具固定)や下地の補修によって、強風への耐性は大幅に向上します。
放置すると飛散事故や雨漏りの原因となるため、早めの点検と改修が安全確保の鍵となります。
日本は、いつ災害が起きてもおかしくない国土環境です。ですがしっかり準備しておけば、致命傷は避けられるはず。労力はかかりますが、時間が経ってから「やっておいてよかった」と思うはずです。
自治体の補助金 主な事例
実際に多くの市町村が、瓦屋根の耐風診断や耐風改修工事に対して補助金を出しています。代表的な事例は次のとおりです。
岡崎市:瓦屋根の診断費を2/3(上限21,000円)、改修は診断の結果に応じて工事費の一部(工事費または屋根面積換算のいずれか低い額の23%)を補助する制度があります。対象や上限は条件あり。
引用:岡崎市 瓦屋根の脱落被害を防ぐための補助制度について補助金の額
・瓦屋根診断
瓦屋根の診断に要する費用×2/3(上限21,000円)
・瓦屋根改修
瓦屋根の改修に要する費用×23/100(上限552,000円)
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1165/p035198.html?utm_source=chatgpt.com(参照:2025-08-10)
千葉市:耐風診断費の3分の2を補助(上限21,000円)、改修工事費は工事費または屋根面積×24,000円のいずれか低い額の23%が例として示されています。
引用:千葉県 住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度補助額
1.耐風診断
耐風診断に要する費用の3分の2の額。ただし、2万1千円が限度。
2.耐風改修
工事費または屋根面積×24,000円のいずれか低い額の23%。ただし、55万2千円が限度。
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kawarayane_taihu.html?utm_source=chatgpt.com(参照:2025-08-10)
診断と改修をセットで補助する制度を設け、資格を持つ専門家による診断を条件とする自治体が多くあります(対象年式や改修履歴など、条件が細かく設定されているので要確認)。
また、国の取り組み(住宅・建築物安全ストック形成事業)を受け、地方自治体で補助を実施するケースも増えています。補助率や上限金額は自治体によって大きく異なるため、必ずお住まいの自治体窓口で最新情報を確認してください。
補助の対象となる工事・診断の中身(共通例)
自治体の補助が想定する代表的な内容は下記です(自治体により対象は差があります)。
- 耐風診断:瓦の緊結方法や下地の状態を専門家が評価。診断士や瓦ぶき技能士による現地調査。
- 瓦の緊結(固定)工事:瓦1枚ずつ釘やビスで固定する、あるいは耐風金具を設置する工事。
- 屋根の葺き替え:軽量瓦や金属屋根など耐風性の高い材料への葺き替え(補助の対象になる自治体あり)。
- 下地補強:野地板や垂木など下地の補強によって全体の耐風性能を向上させる工事。
補助を受けるには「診断を受けて基準に適合しないと判断された場合に改修工事を行う」といった流れが一般的です。
補助を受けるための手順(一般的な流れ)
- 自治体の制度を確認:市役所の建築・住宅課などで条件(対象築年数・屋根材・申請期限)をチェック。
- 事前相談(必要に応じて):申請書の書き方や必要書類を確認。予算枠で受付が終了する自治体もあります。
- 耐風診断の依頼:資格者による診断を受ける(補助対象となる診断士や業者指定がある自治体も)。
- 診断結果に基づいて見積りと工事計画を作成。
- 事前申請(助成の申請)→ 審査 → 工事着工 → 完了報告 → 補助金交付(自治体により工程や書類が細かく指定されます)。
注意:補助金は年度予算の範囲で交付されます。早めの申請と、自治体ルールに沿った手続きが重要です。
工事業者を選ぶときのポイント
- 補助を受けるため「資格を有する業者」の指定がある自治体があります。自治体の案内にあるリストや、全日本瓦工事業連盟などの公的団体で確認しましょう。
- 見積りは複数社から取り比較。材料や固定方法(釘・ビス・金具)・下地補強の内容を確認してください。
- 施工後の保証(雨漏りや工事瑕疵)やアフターケアも確認しておくと安心です。
補助制度を利用するメリットと留意点
メリット:自己負担を抑えて耐風性能を高められるだけでなく、万が一瓦が飛散して第三者に被害を与えるリスクや、その後の長期的な修繕コストを減らせます。
留意点:自治体によって対象住宅や補助率、上限額、申請締切が異なります。また、補助は年度予算で枠が埋まると終了します。申請前に必ず公式ページで最新情報を確認してください。
まず何をすべきか
- 住まいの屋根が瓦かどうか、築年数と改修履歴を確認。
- お住まいの市区町村の「瓦屋根 耐風 補助」ページを検索して要件を確認。
- 診断を受けられるか、どの業者が対象かを自治体に問い合わせる。
- 見積りを取り、補助申請のスケジュールを立てる(年度内の予算に注意)。
まとめ
瓦屋根の耐風対策は「自宅を守る」だけでなく、飛散が近隣に与える二次被害を防ぐ重要な施策です。
自治体の補助を活用すれば負担を軽減しつつ、確かな施工で安心を得られます。まずはお住まいの自治体の制度を確認し、早めの行動をおすすめします。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
岡崎市 瓦屋根の脱落被害を防ぐための補助制度について
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1165/p035198.html?utm_source=chatgpt.com(参照:2025-08-10)
千葉県 住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kawarayane_taihu.html?utm_source=chatgpt.com(参照:2025-08-10)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。