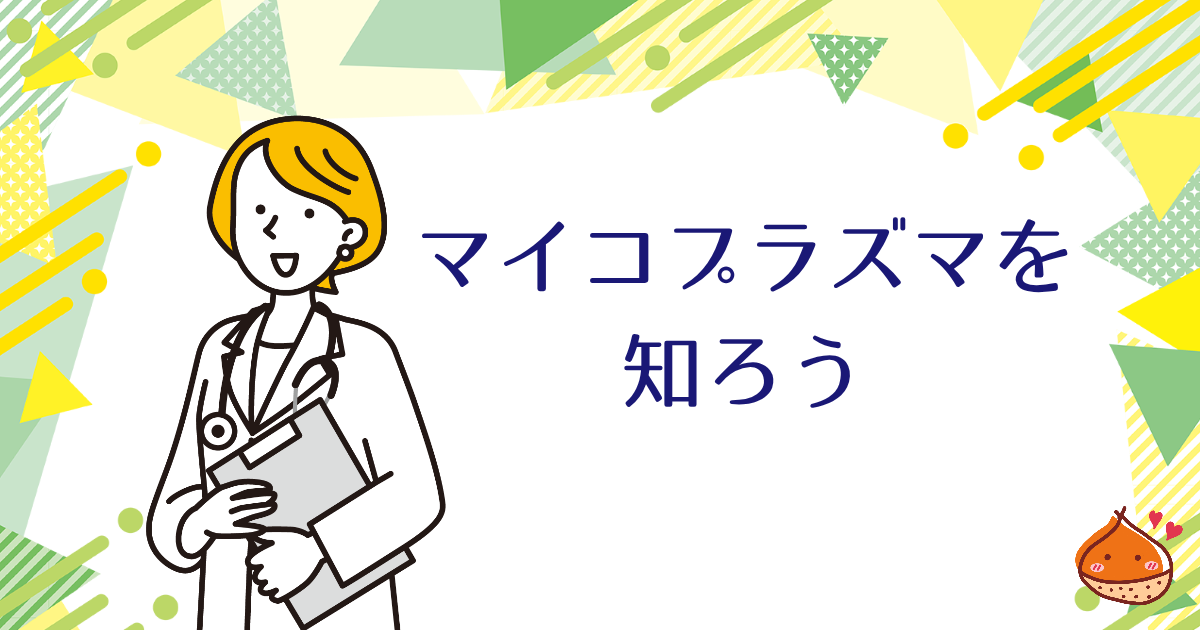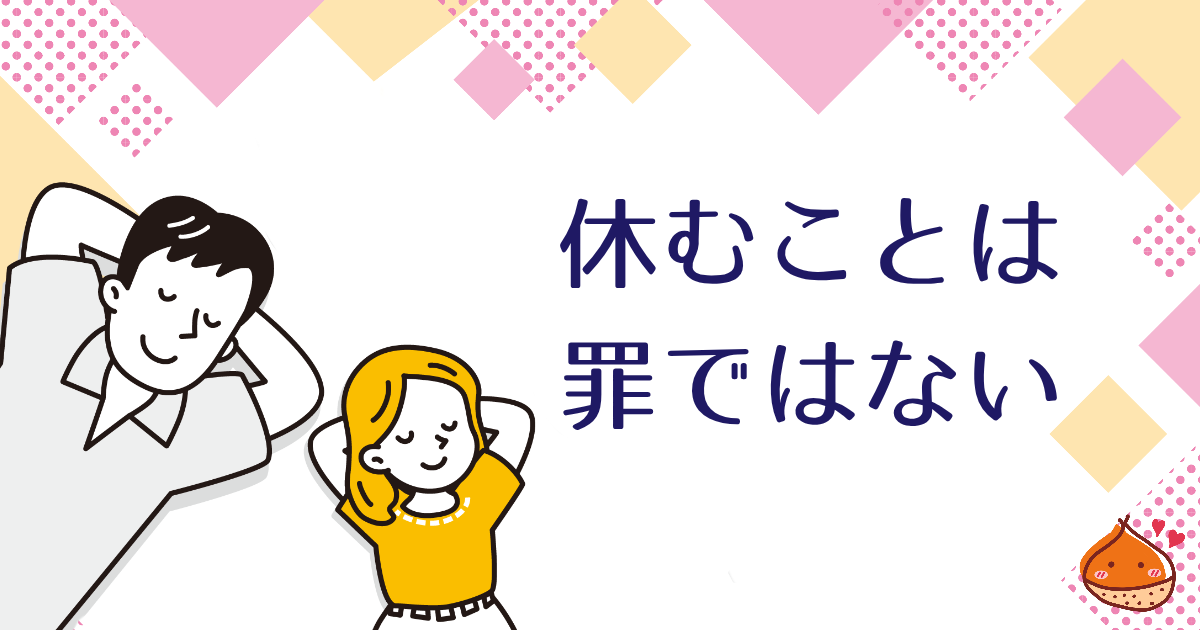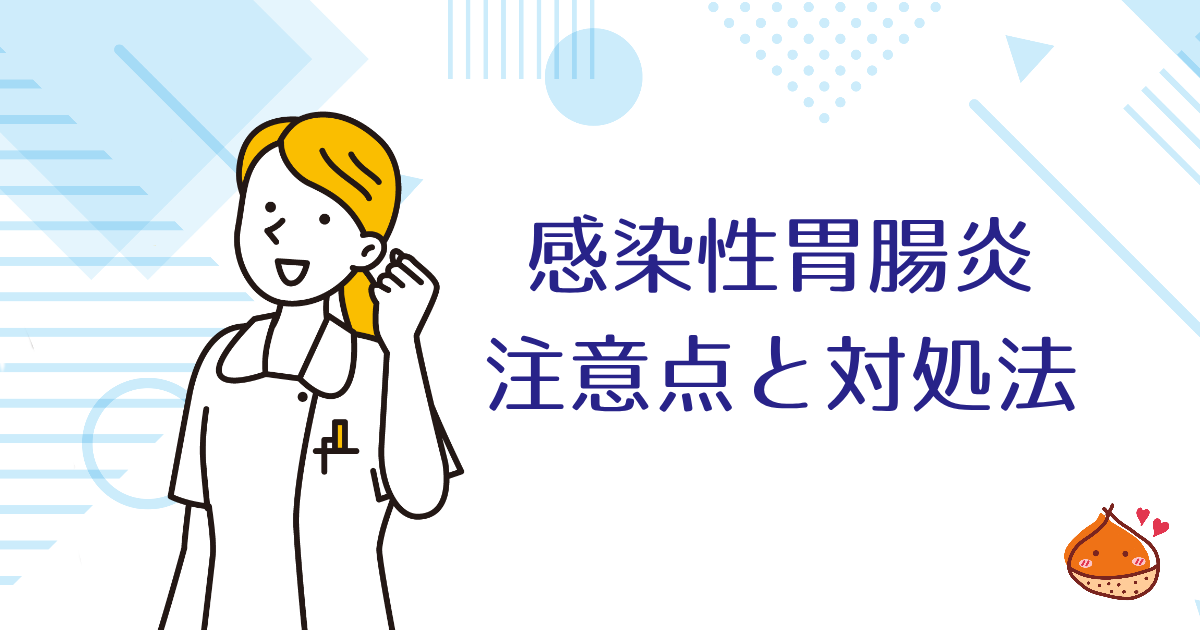
寒くなってくると、毎年のように話題になる「感染性胃腸炎」。
突然の吐き気や下痢に襲われ、「食べたものが悪かったのかな?」と思っていたら、実はウイルスによるものだった――そんな経験はありませんか?
感染性胃腸炎は、ノロウイルスやロタウイルスなどが原因で、家庭や職場、学校などで一気に広がることがあります。特に冬の時期は流行のピーク。
自分が感染するだけでなく、知らないうちに家族や職場の人にうつしてしまうケースも少なくありません。
この記事では、「感染性胃腸炎ってどんな病気?」「どうやってうつるの?」「もし感染したらどうすればいい?」という疑問に答えながら、
うつらない・うつさないための正しい知識と対処法をご紹介します。
感染性胃腸炎とは?

感染性胃腸炎とは?
感染性胃腸炎とは、ウイルスや細菌などの病原体が胃や腸に感染して起こる炎症のことです。
主な症状は、吐き気・嘔吐・下痢・発熱・腹痛などで、体内の水分や電解質が失われやすいため、脱水に注意が必要です。
原因となる病原体は季節によって異なり、冬はウイルス性、夏は細菌性のものが多くみられます。
特に集団生活の場(学校・保育園・介護施設など)では感染が広がりやすいため、「うつらない・うつさない」対策が大切です。
原因となるウイルス(ノロ・ロタ・アデノなど)
感染性胃腸炎の原因ウイルスには、主にノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスがあります。
最も多いのがノロウイルスで、わずかな量のウイルスでも感染しやすく、感染力が非常に強いのが特徴です。
ロタウイルスは主に乳幼児に多く、白っぽい下痢便や嘔吐を繰り返す傾向があります。
アデノウイルスは季節を問わず発生し、発熱や咽頭炎を伴うこともあるのが特徴です。
これらのウイルスは体外でも長く生存しやすく、ドアノブやタオル、食器などを介して感染が広がることがあります。
感染経路(手指・食べ物・飛沫)
感染性胃腸炎は、主に接触感染・経口感染・飛沫感染の3つの経路で広がります。
最も多いのは手指を介した接触感染で、ウイルスが付着した手で口や食べ物に触れることで感染します。
また、ウイルスが付着した食材や調理器具からの食べ物経由の感染も多く、加熱不足や調理後の汚染が原因になります。
さらに、嘔吐物や便の処理中に**ウイルスを吸い込む「飛沫感染」**が起こることもあります。
感染力が非常に強いため、手洗い・消毒・トイレ後の衛生管理が何よりの予防になります。
「夏の感染性胃腸炎」と「冬の感染性胃腸炎」
「感染性胃腸炎」は年間を通して発生しますが、季節ごとに原因と特徴が異なります。
夏は主に細菌性(カンピロバクター・サルモネラ・腸炎ビブリオなど)が原因で、食中毒型が多くみられます。
一方、冬はウイルス性(ノロ・ロタなど)が中心で、人から人へうつる集団感染型が特徴です。
夏は「食材の取り扱い」、冬は「手洗い・消毒」がポイントとなります。
つまり、季節に応じた予防意識の切り替えが、感染性胃腸炎を防ぐ最大の鍵なのです。
主な症状と発症の流れ

吐き気・嘔吐・下痢・発熱など
感染性胃腸炎の主な症状は、吐き気・嘔吐・下痢・発熱・腹痛などです。
多くの場合、最初に「胃のむかつき」や「軽い吐き気」が現れ、その後に嘔吐や水のような下痢が続きます。
発熱は37〜38度台が多いですが、子どもでは高熱になることもあります。
嘔吐が落ち着いても下痢がしばらく続くケースが多く、体力を消耗しやすいのが特徴です。
感染しても軽症で済む人もいますが、高齢者や乳幼児では重症化しやすいため注意が必要です。
発症のタイミングや症状の出方には個人差があり、家庭内で次々と発症することも少なくありません。
潜伏期間と回復までの目安
感染性胃腸炎には「潜伏期間」があり、感染してから1〜3日程度で症状が現れるのが一般的です。
ノロウイルスでは12〜48時間後、ロタウイルスでは約1〜3日後に発症するケースが多く見られます。
症状は通常、2〜3日でピークを過ぎ、4〜5日ほどで回復に向かうのが典型的な経過です。
ただし、下痢だけが長引いたり、体力が戻るまで1週間ほどかかることもあります。
回復してもウイルスはしばらく体内に残り、便から1〜2週間ほど排出されるため油断は禁物です。
完全に治ったと思っても、手洗いなどの衛生管理は継続することが大切です。
脱水症状に注意すべき理由
感染性胃腸炎で最も怖い合併症が脱水症状です。
嘔吐と下痢が続くことで体内の水分と塩分が失われ、めまい・倦怠感・尿の減少・口の渇きが現れます。
特に乳幼児や高齢者は脱水になりやすく、重症化すると意識障害やけいれんを起こすこともあります。
「水分を取らなければ」と焦って一度に多く飲むと、嘔吐を誘発することがあるため注意が必要です。
対策としては、少量をこまめに、経口補水液(OS-1など)で水分と電解質を補うのが効果的です。
回復期でも油断せず、尿の色や回数、体のだるさをチェックすることが大切です。
感染を広げないための具体的な対処法
正しい手洗い

感染性胃腸炎の最大の感染経路は「手」です。
トイレ後、食事前、調理前、看病後は必ず石けんで30秒以上しっかり洗いましょう。
流水で軽く流すだけではウイルスは落ちません。指の間や爪の間、手首まで丁寧に洗うことが大切です。
ノロウイルスなどはアルコール消毒では不十分な場合があるため、石けん+流水が基本です。
外出先でも、ウェットティッシュではなくハンドソープが使える場所を選ぶのが理想です。
家庭内ではペーパータオルの使用を推奨し、共有タオルで感染を広げない工夫も大切です。
トイレ後の消毒を行う

感染者が使ったトイレは、目に見えない飛沫やウイルスが広がっています。
使用後は、便座・レバー・ドアノブなどを塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で拭き取りましょう。
薄め方の目安は、水1リットルに対して家庭用漂白剤キャップ約1杯(0.02%濃度程度)です。
掃除の際は使い捨て手袋とマスクを着用し、使った布はすぐに廃棄します。
トイレの蓋は、流す前に必ず閉めることでウイルスの飛散を防止できます。
小さな子どもがいる家庭では、大人が最後に必ず消毒確認を行うことを習慣化しましょう。
嘔吐物処理のポイント
嘔吐物には大量のウイルスが含まれており、最も感染リスクが高い場面です。
処理の際は必ず手袋・マスク・できればエプロンを着用します。
新聞紙などで覆ってから、塩素系漂白剤を含ませた布で外側から中心に向かって拭き取るのが基本です。
拭き取った後は再度同じ消毒液で床を拭き、使用した道具はすぐに廃棄します。
布製品に付着した場合は洗濯機で洗う前に熱湯消毒(85℃で1分以上)が有効です。
処理後は必ず石けんと流水で手を洗い、うがいを行うことを忘れずに。
慌てず、感染を広げないことを最優先に落ち着いて対処しましょう。
水分補給と食事管理
感染性胃腸炎では、無理に食べるより水分補給を優先することが大切です。
脱水を防ぐために、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつこまめに摂取しましょう。
吐き気が落ち着いたら、おかゆ・うどん・スープなど消化にやさしい食事を少しずつ再開します。
脂っこいもの、乳製品、生もの、冷たい飲み物は胃腸に負担をかけるため避けるのが無難です。
症状が落ち着いた後も、2〜3日は刺激物を控えると再発防止につながります。
食器は共用せず、使ったものはすぐ洗い、しっかり乾燥させることも感染予防になります。
体調が戻るまでは無理せず、回復を優先することが一番の感染対策です。
症状が重いとき・長引くときは医療機関へ

脱水症状や血便などの危険サイン
感染性胃腸炎の多くは数日で自然に回復しますが、一部の症状には注意が必要です。
唇の乾き、尿の減少、ふらつき、皮膚の乾燥などは脱水症状のサインです。
また、血が混じった便・高熱(38℃以上)・強い腹痛がある場合は、細菌性胃腸炎などの可能性もあります。
嘔吐が続いて水分を取れない場合も、自力での回復が難しい状態と考えましょう。
我慢せず、早めに内科または小児科を受診することが大切です。
医師の指示に従い、整腸剤や点滴など適切な治療で体力を回復させることが重要です。
「もう少し様子を見よう」と思って手遅れになるケースも少なくありません。
乳幼児・高齢者・持病がある人は特に注意
乳幼児や高齢者、糖尿病・腎臓病などの持病がある人は脱水リスクが高くなります。
体内の水分量が少ないため、短時間で重症化しやすいのが特徴です。
また、免疫力が低下しているため、感染が長引いたり二次感染を起こすこともあります。
特に乳幼児では、泣いても涙が出ない・おしっこが少ない・ぐったりしているなどの様子があればすぐ受診を。
高齢者では、軽度の発熱でも意識がぼんやりする・食欲が落ちるといった変化を見逃さないことが大切です。
家庭内で看病する際は、体調の変化をメモして医師に伝えると診断がスムーズになります。
「年のせい」「疲れのせい」と思わず、早めの対応を心がけましょう。
早めの受診が重症化を防ぐ

感染性胃腸炎は放っておくと、脱水や腎障害、誤嚥性肺炎などの合併症を起こすおそれがあります。
特に嘔吐を繰り返す場合は、体力の消耗が激しくなる前に医療機関へ行くことが大切です。
受診時は、症状の始まり・回数・便や嘔吐物の状態をメモして伝えると診断が早まります。
ウイルス性か細菌性かを見極めるために、便検査を行う場合もあります。
また、医師の指示で点滴治療を受ければ、短時間で体調が安定することもあります。
無理に市販薬で抑えようとせず、原因を正確に把握することが回復の近道です。
「長引く胃腸炎」は、迷わず専門家の力を借りましょう。
まとめ:感染予防のために手洗いからはじめよう
感染性胃腸炎は、冬だけでなく夏にも発生する身近な感染症です。
主な原因はノロウイルスやロタウイルスで、手指や食べ物を介して簡単に感染が広がることが特徴です。
症状が軽くても、吐き気・下痢・発熱などが続く場合は体をしっかり休ませることが回復の第一歩。
また、嘔吐物や排泄物の処理は手袋・マスクを着用し、塩素系消毒液で丁寧に除菌することが大切です。
家庭内感染を防ぐためには、手洗い・トイレ・食事まわりの衛生管理を徹底しましょう。
乳幼児や高齢者など、体力の弱い人がいる家庭では特に注意が必要です。
重い症状(脱水・血便・高熱・息苦しさなど)があるときは、早めに医療機関を受診することが重症化を防ぐ鍵になります。
「うつらない・うつさない」は、正しい知識と日々の小さな行動から。
冬も夏も油断せず、家族全員で健康を守る習慣を身につけましょう。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
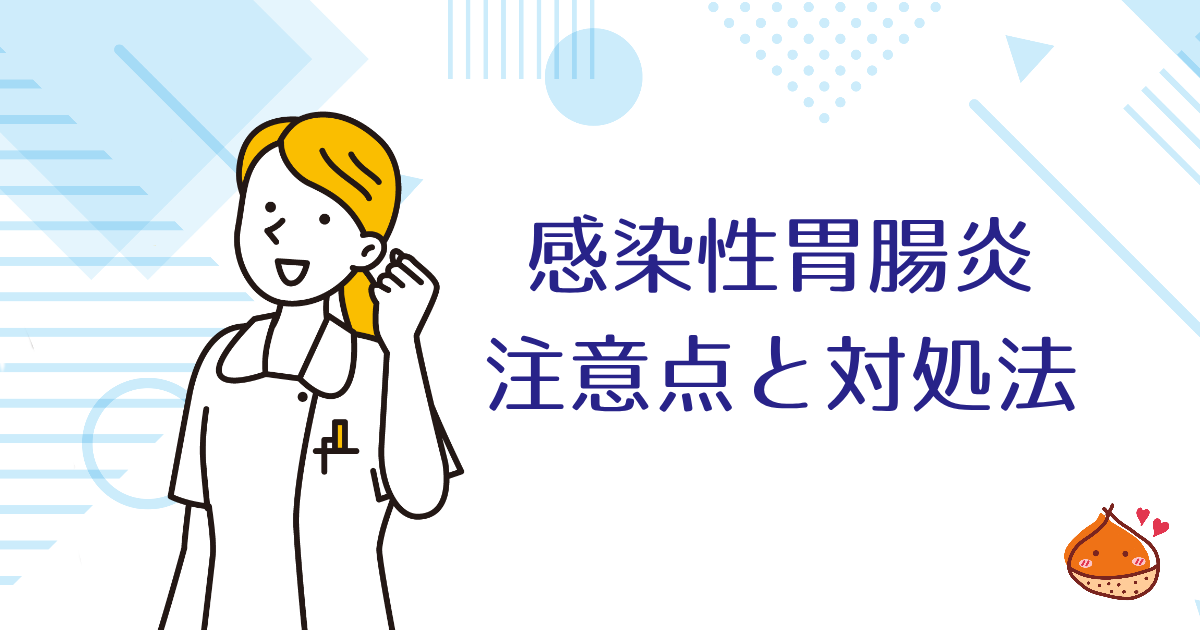
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。