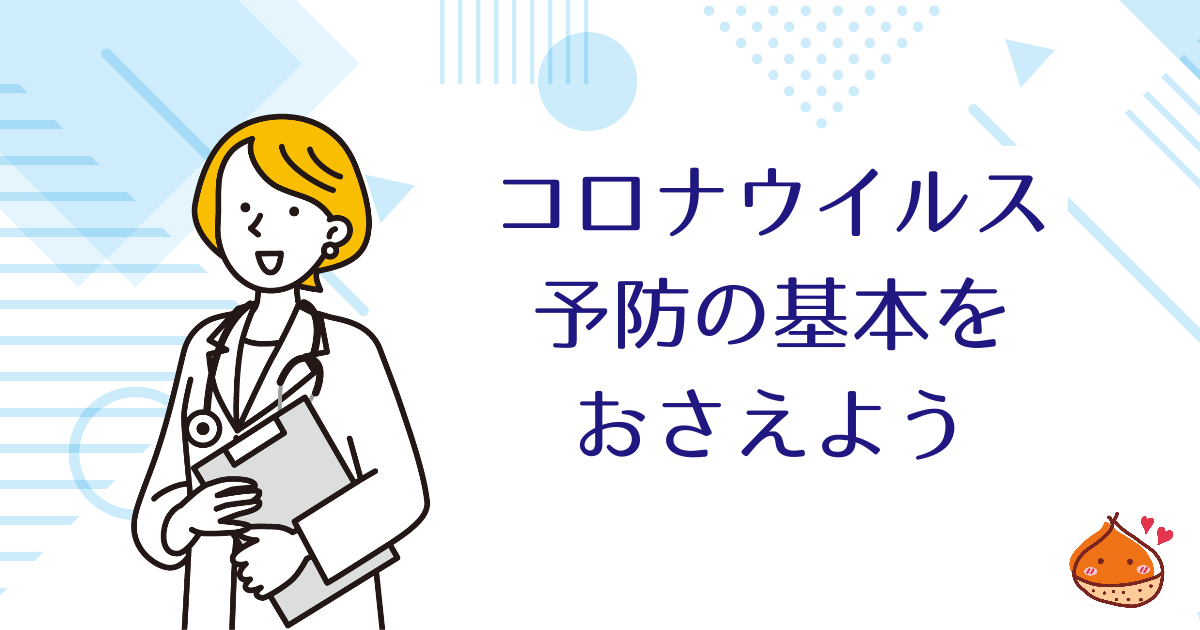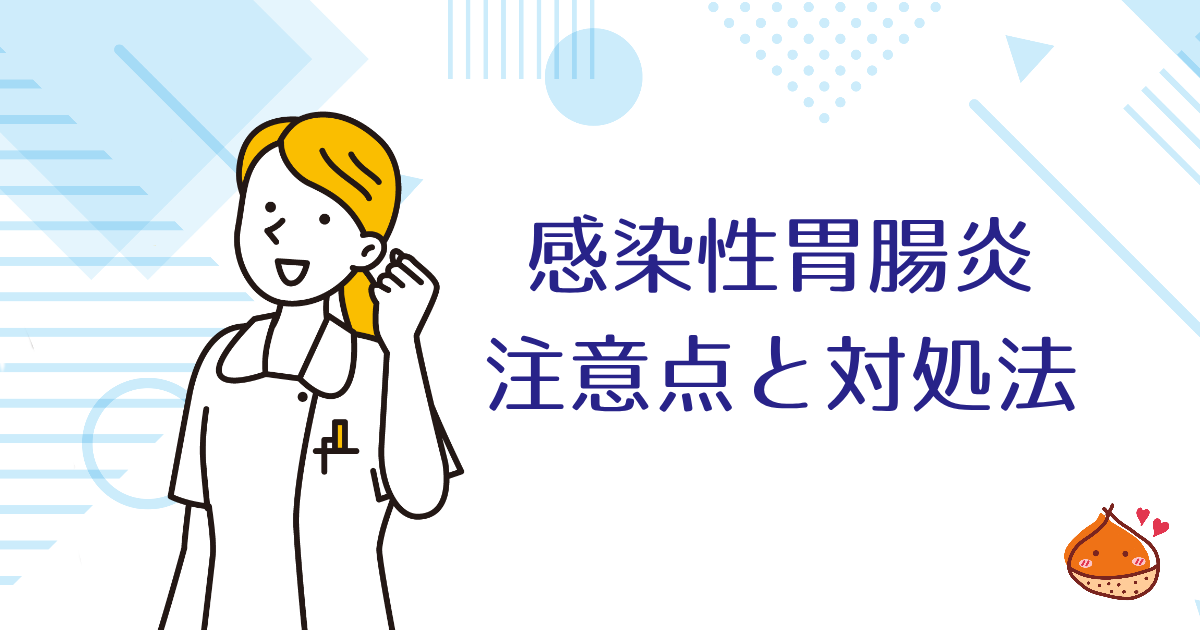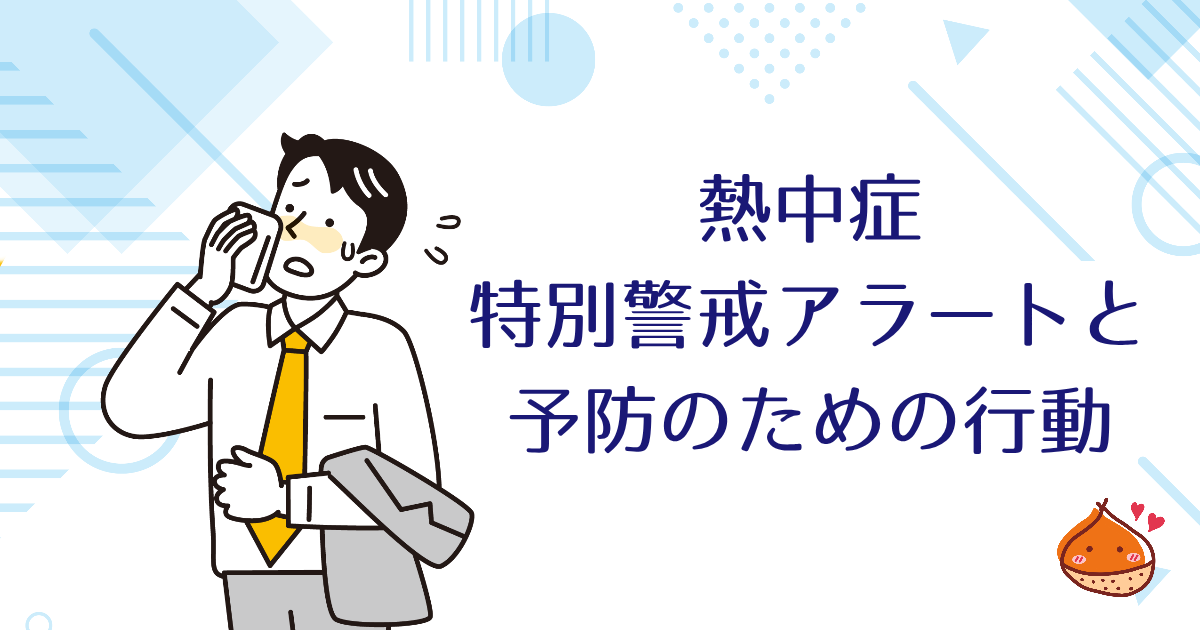一般的に食中毒は夏に増えるイメージがありますが、実は年間を通じて発生しています。
冬でもノロウイルスや寄生虫など、油断できない原因が潜んでいます。
しかも家庭の調理や保存のちょっとした油断が、大きなリスクにつながることも。
せっかくの食事を安心して楽しむためには、季節ごとの特徴と食材別の注意点を知ることが大切です。
今回は、食中毒を防ぐためのポイントをわかりやすくご紹介します。
季節ごとの主な原因別リスク
春(3〜5月)
春は気温・湿度が上がり始め、食中毒菌の活動が徐々に活発になります。
- アニサキス(寄生虫):サバ、サンマ、イカなど生食で感染の危険。
- 芽が出たジャガイモ(ソラニン):家庭菜園や保存中の芋で発生。
- 行楽やお花見で作るお弁当は、室温で長時間放置しないことが重要。
夏(6〜8月)
高温多湿で細菌が爆発的に増える時期。発症までの時間も短い傾向があります。
- サルモネラ菌:生卵や十分に加熱していない肉類が原因。
- 黄色ブドウ球菌:手指や傷口から食品に入り、毒素を作る。
- 腸炎ビブリオ:海水温が高くなると魚介類に増える。調理前の真水洗浄が有効。
秋(9〜11月)
気温は下がるが、まだ食中毒菌は活発で、自然毒にも注意が必要です。
- きのこ・山菜の毒:食用と似た有毒種を誤食すると重篤化の恐れ。
- フグ毒(テトロドトキシン):免許のない人が処理すると危険。
- アニサキス:秋サンマやイカなど旬の魚介でも油断は禁物。
冬(12〜2月)
細菌の活動は弱まるが、ウイルス性食中毒が急増。少量でも感染します。
- ノロウイルス:カキなど二枚貝や、人から人への接触で感染。
- ロタウイルス:乳幼児に多く、嘔吐や下痢を引き起こす。
- 調理器具やまな板の消毒は85℃以上の熱湯、または次亜塩素酸ナトリウムが有効。
食材別に注意したいポイント
肉類
中心温度が75℃以上になるまで加熱することで、サルモネラ菌やカンピロバクターを死滅させられます。
鶏肉やひき肉は特に菌が広がりやすいため、半生やレア調理は避けたほうがよいでしょう。
魚介類
生食用でも新鮮さを確認し、中心まで加熱するのが安全です。
特に牡蠣などの二枚貝は85〜90℃で90秒以上の加熱が望ましいとされています。
刺身用の魚でも、冷凍処理でアニサキスを死滅させることが可能です(−20℃で24時間以上)。
野菜類
泥や菌が付着している場合があるため流水でよく洗いましょう。
カット野菜やサラダは購入後すぐに冷蔵し、なるべく早く食べきることが大切です。
卵
賞味期限内に使用し、生食は新鮮なものを選び、割ったらすぐ調理しましょう。
ヒビの入った卵は菌が侵入しやすいので使用を避けたほうが無難です。
きのこなどの自然毒
見た目や匂いで判断せず、確かな知識がない場合は採取・調理するのはやめましょう。
食用とよく似た有毒種も多く、少量でも命に関わる危険があります。
フグなどの毒
フグにはテトロドトキシンという猛毒が含まれ、加熱しても毒は分解されません。
素人が調理するのは非常に危険で、毎年死亡事故が報告されています。
調理は必ず自治体の認可を受けた有資格者が行う必要があります。
「少しなら大丈夫」という自己判断は命に関わります。
不明な種類や不安がある場合は、絶対に食べないことが最も安全です。
寄生虫(アニサキス)
加熱または冷凍で死滅します。表面を目視確認することもできるので、見つけたら身から取りましょう。
すべての食材は「低温保存+早めに調理・消費」が基本です。
調理器具や手指の清潔管理も、食材の安全を守る大切なポイントです。
自宅での基本的な予防策
つけない
菌やウイルスを食品に持ち込まないことが第一歩です。
調理や食事の前、肉や魚を扱った後は必ず石けんで手洗いを行いましょう。
調理器具やまな板は、食材ごとに使い分けるか、使用後に洗剤+熱湯消毒を。
特にノロウイルスは非常に感染力が強く、少量でも発症するため念入りな衛生管理が必要です。
増やさない
菌は温かい環境で急速に増殖します。冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は−15℃以下を保つことが望ましいです。
作った料理や切った食材を常温で長時間放置しないようにしましょう。
買ってきた食品は寄り道せずにすぐ冷蔵・冷凍へ。食品を持ち帰る際は、保冷剤や氷などを使用しましょう。
その際は、保冷バッグも併用することをお忘れなく。保冷力もアップしますし、何より通常のエコバッグに保冷剤を入れると、濡れてしまいます。
やっつける
加熱でほとんどの菌やウイルスは死滅します。肉や魚は中心温度75℃以上で1分以上加熱するのが目安。
二枚貝(牡蠣など)は85〜90℃で90秒以上がより安全です。
調理済み食品の再加熱も、全体が十分に熱くなるまで行いましょう。
ノロウイルス対策として、調理器具は85℃以上で1分以上の加熱消毒、または塩素系漂白剤を活用します。
この三原則を習慣にすれば、家庭での食中毒リスクは大幅に減らせます。
万が一食中毒になったら
食中毒は突然発症し、嘔吐や下痢、発熱などの症状が出ます。
まずは安静にし、脱水を防ぐためにこまめに水分を補給します。
経口補水液やスポーツドリンクなどで、水分と電解質を同時に補うと回復を助けます。
嘔吐や下痢があっても、無理に止めず、体内の毒素を排出させることが大切です。
ただし、次のような場合はすぐに医療機関へ相談してください。
・脱水がひどく、水分がほとんどとれないとき。
・赤ちゃん、高齢者、妊婦が発症した場合(重症化しやすいため)。
・ボツリヌス菌などによる神経症状(視力低下、まぶたが下がる、呼吸困難など)が見られるとき。
血便が出たり、激しい腹痛や高熱が続く場合も受診をしましょう。
自己判断で市販薬を使う前に、必ず症状を医師に伝えてください。
原因食品の残りがあれば、診断や原因特定のために保管して持参すると役立ちます。
家族内での二次感染を防ぐため、トイレや調理器具は消毒を徹底します。
特にノロウイルスは感染力が強いため、汚物処理は使い捨て手袋・マスクを使用しましょう。
早めの受診と適切な対応が、重症化を防ぐカギとなります。
まとめ
食中毒は夏だけの問題ではなく、1年を通じて注意が必要なリスクです。
季節によって主な原因は変わりますが、つけない・増やさない・やっつけるを徹底すれば、その最大限の被害を防ぐことができます。
日々の調理と保存のちょっとした工夫が、大切な健康を守ります。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。