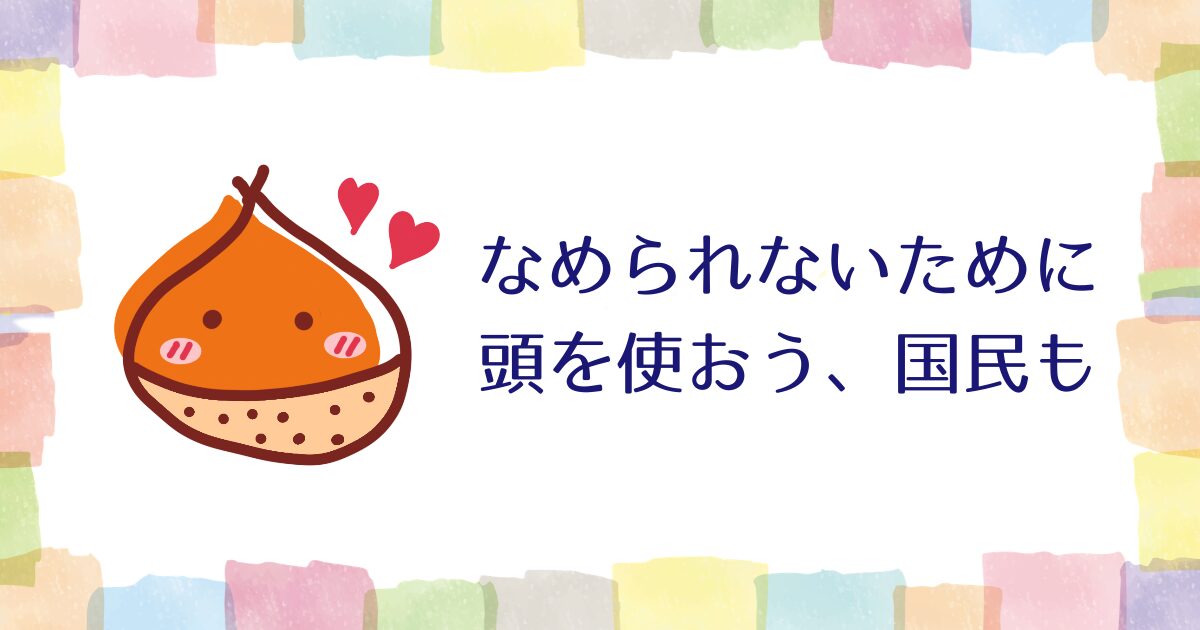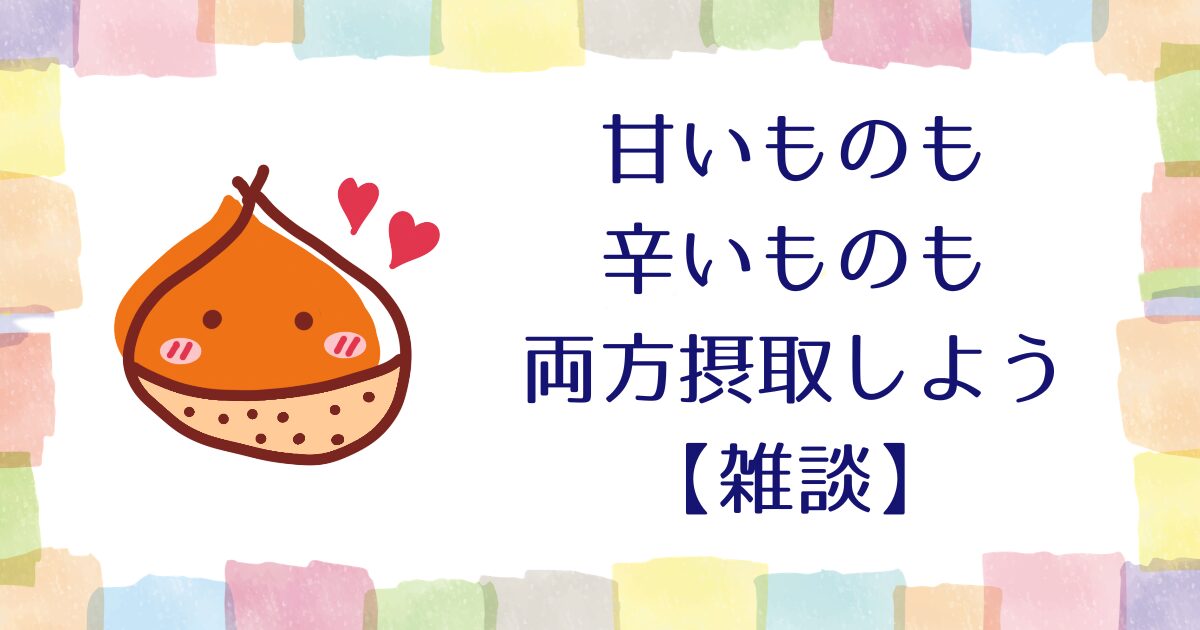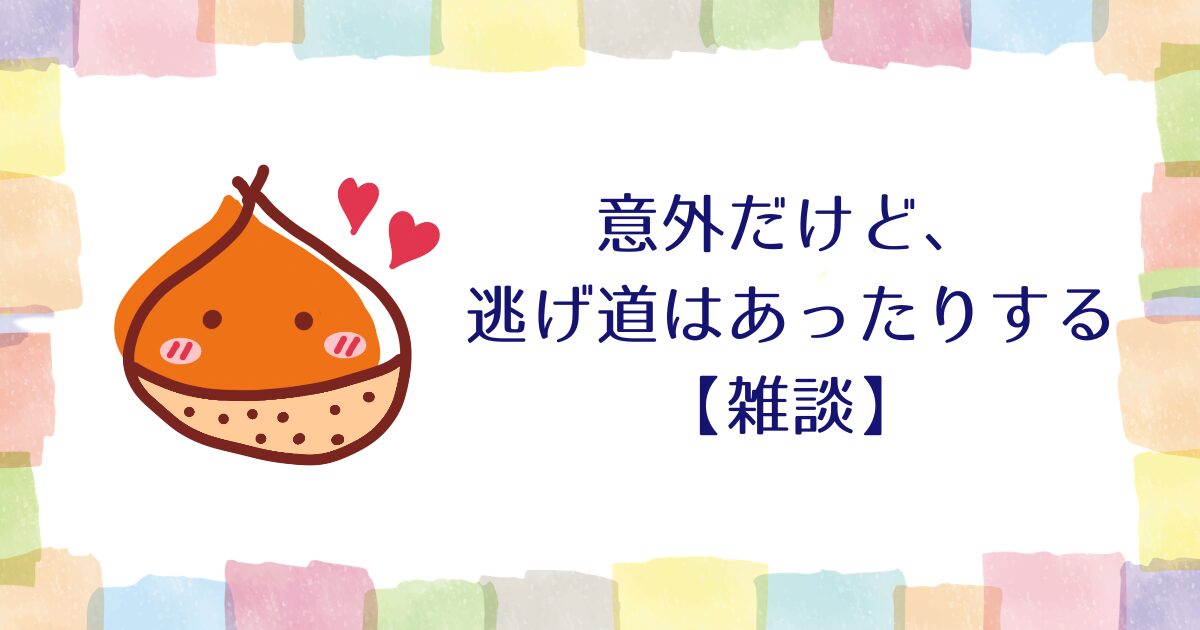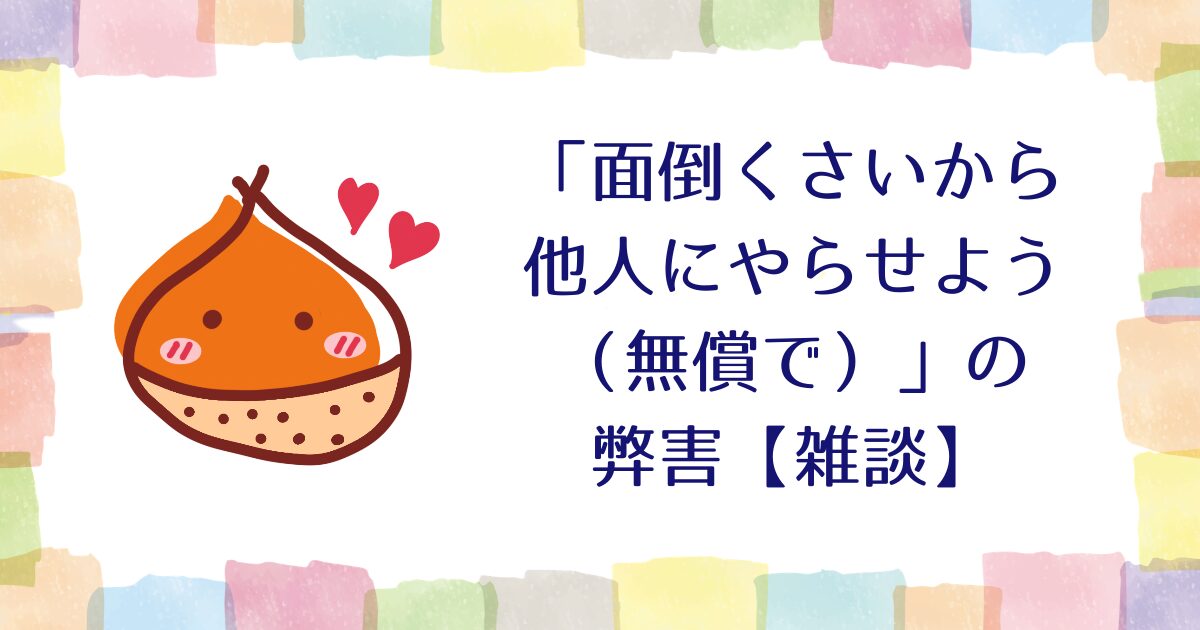
「俺の時間がもったいない」
ある時、入社3ヶ月目の新人さんと一緒に仕事をしていた時のこと。
書類をまとめて郵送しなければならなくなった時、新人さんは「この郵送の業務を他の人間に任せられないか」と相談されました。
理由を聞くと「だって、面倒くさいじゃないですか」とのこと。
またある時、後輩と今後の仕事について話をしていた時のこと。
後輩曰く「自分に有益な仕事はやりたいが、何も得られるものがなければやりたくない」とのこと。
またまたある時、上司と話をしようとした時に言われた「俺の時間がもったいない」「俺の時間を返せよ」というセリフ。
経営、そして仕事を行う上で、効率化・他の人に任せるというのはとても大切なことです。
自分がやるよりも、他の人にお願いしたほうが良い時が必ずあります。
自分にしかできないことをやるのはまあ正しい、しかし、その他のことは他人に「お願いする」ではなく「自分が単にやりたくないから、他人にやらせる、他人を使う」になってくると、ちょっと違ってきます。
「自分でやるのは面倒くさい」「自分にしかできないことをやるのだ、自分の時間を使うのが惜しい」「自分の時間がもったいない」となってくるのです。
効率厨乙、というところでしょうか(古すぎ?)。
「面倒くさいから他人にやらせよう(無償で)」の弊害
この「自分の時間を使うのが惜しい」が行き過ぎると「自分は付加価値の高い仕事ができる人間だから、瑣末なことは他人を使おう」になってきます。
そうなると「それは私がやらなければならない仕事ですか」と言うようになります。管理職だろうが新人だろうが、言う人は言います。
注目したいのは「自分は付加価値の高い仕事ができる」という部分。
これが事実ならいいのですが、事実でないのであれば単にサボってるだけじゃん、になります。あなたの代わりにその仕事をやる私は価値がない人間とでも?と言いたくもなるでしょう。
しかし、絶対の正解が存在しないこの世界で、事実かどうかを確かめるのは非常に難しい。付加価値の高さはどうやって評価すればよいのか、評価項目はどうやって決めるのか、誰が評価するのか??
この「俺は私は、付加価値の高い仕事ができるぜ!」が事実かどうかはさておき、他人に任せることで失うものについて述べたいと思います。
それは、自ら行動する習慣です。
行動しないことは、ある意味効率がいいです。自分の時間を使わない、現状維持ができている、つまり悪い方向には進んでいない(ように見える、ゆっくり死んでいっているのかもしれない)。
厚切りジェイソンさんがいつぞや上司に言われた「成果をあげたら、そのあと何もするな。その成果の印象だけで残って生きていける」ではないですが、特に日本では、何もしないは罪に問われにくいのです。
言ったもん負け文化、「チャレンジして失敗したらどうするんだ」「失敗するくらいなら何もやらない方がいい」は、なんとかすべき課題であると考えます。
100点中95点を取ったら、「あと5点で100点だったのに!」と怒る人間と「95点取れてすごい!」と得られたものをストレートに見れる人間、どちらがいいのかは言わずもがなですが、日本に根強く残っている「既定路線や完璧以外は全て悪」は負の側面が強すぎます。
面倒くさいけど行動することで明日が楽になるはずという考え方は、効率厨とは真逆の考え方なのかもしれませんが、私にとってこれは譲れない考え方です。
実際は、やってみないとわからないことが多い
効率を求めすぎると、完璧以外受け入れられなくなります。
「これもダメ」「あれもダメ」「もっといい企画を持ってこい」
ですが、残念ながら、やってみないとわからないことが多いのが現実です。そして、成功には再現性が無いこともあります。
成功した理由は後付けが多く、真実は誰にもわかりません。「成功には再現性が無いこともある」が、見過ごされがちです。
再現性が無いことに目を向けて、だけれどもどうしたら成功率を上げられるのか、期待値を上げられるのか、その打ち手をどれだけ多く打てるのか。
効率を求める心を少し抑えて「やってみないとわからないよね」とスモールスタートを行える人間こそが、未来の果実を得られるのでしょう。
効率をどうしても求めてしまう私も含めて、意識し続けたいと思います。
九州から東北にかけて局地的に激しい雨に見舞われ、心身ともに疲れている方も多いのではないでしょうか。
どうか、命を最優先に安全を確保して過ごしていただき、穏やかな日常が戻ってくるよう祈っております。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
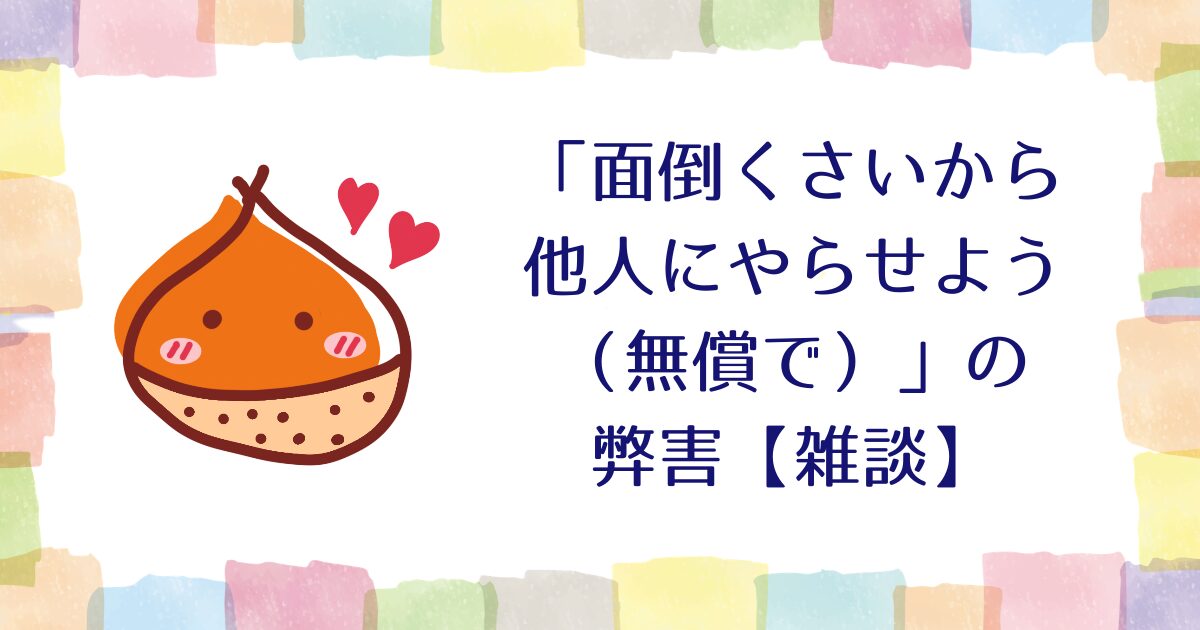
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。