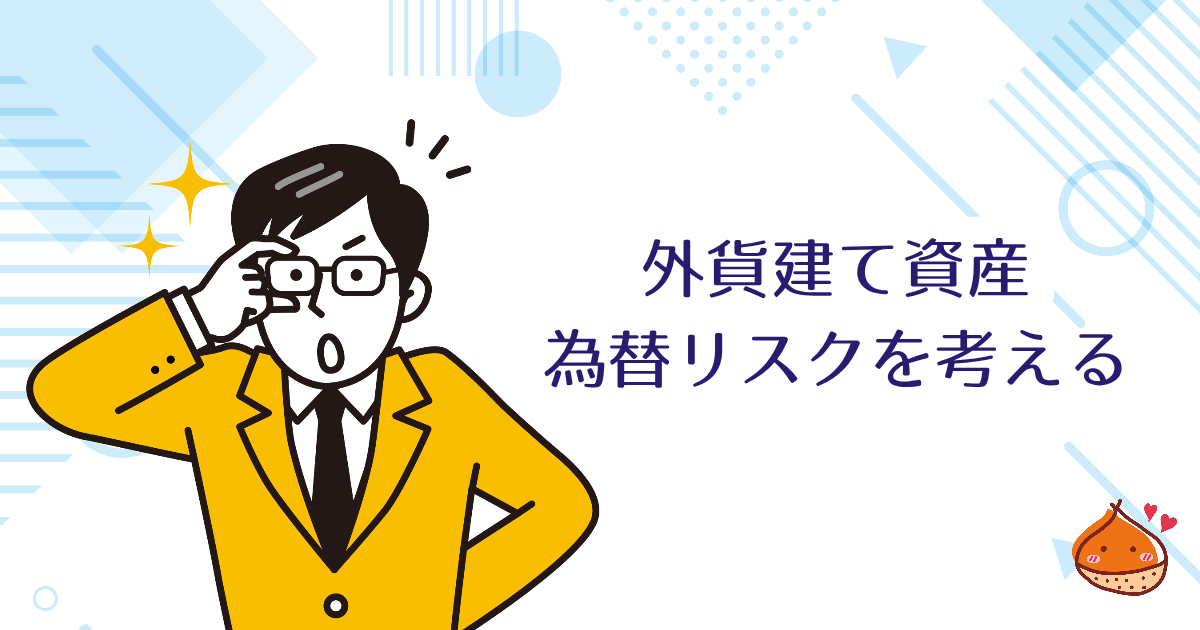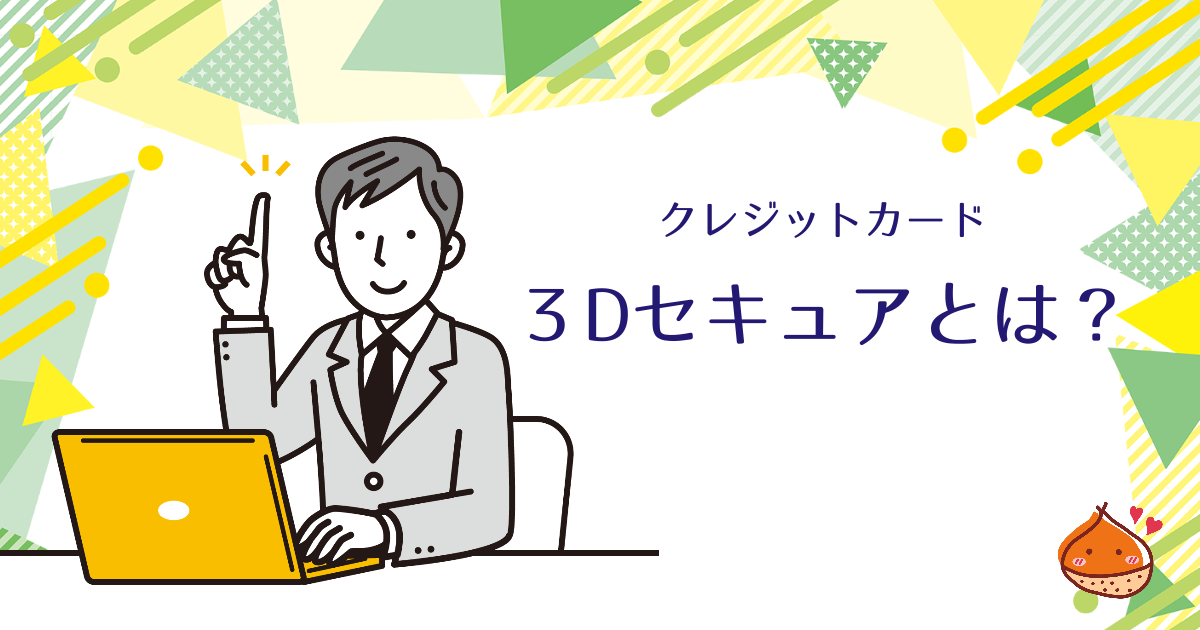日本は「災害大国」であることを知ろう
日本は世界でも有数の「災害大国」といわれており、地震・台風・豪雨・津波・火山噴火・豪雪と、さまざまな自然災害が発生しています。
例えば、2011年の東日本大震災は記憶に新しく、津波や原発事故など深刻な被害をもたらしました。また、近年では九州豪雨(2020年)や西日本豪雨(2018年)など、大雨による河川の氾濫や土砂災害が多発しています。さらに、台風による強風や高潮も毎年のように発生し、住宅やインフラに被害を及ぼしています。
日本列島は4つのプレートが交差する地震の多発地域に位置しており、年間の地震回数は世界有数。加えて、全国に活火山が多数あり、噴火リスクも無視できません。
このように、日本に住む限り、災害と無縁ではいられないのです。まずは「災害が起こることは前提」であるという意識を持ち、備えることが重要です。
災害リスクは「ゼロ」にできないが、「減らす」ことはできる
災害リスクを完全になくすことはできませんが、工夫次第でその被害を大きく減らすことは可能です。
たとえば、引っ越しや住まいの購入を検討している人は、ハザードマップを活用しましょう。川の近くや土砂災害警戒区域を避けるだけで、水害や土砂崩れのリスクを大幅に減らせます。家の立地を見直す、避難経路を確保しておく、災害情報を集めるなど、日常の中に「備え」を取り入れることが大切です。
また、2階以上に非常用バッグを置く、家具を固定しておく、避難経路を家族で確認しておくといった日常の備えも、有事の生存率を上げる要因になります。
太陽光発電+蓄電池の導入や地震に強い建築構造の家を選ぶといった対策も中長期的には有効です。
「どうせ逃げられない」ではなく、「被害を小さくするには何ができるか」と考えることが、命や資産を守る第一歩です。
「住む場所」で災害の影響は大きく変わる
災害のリスクは「住む場所」によって大きく左右されます。たとえば、川の近くに住めば大雨による洪水や土砂災害のリスクが高まり、海の近くに住めば津波や高潮の被害を受けやすくなります。
また、山の斜面や急傾斜地では、地震や豪雨の際に土砂崩れの危険があります。実際、過去の豪雨災害では、ハザードマップで「危険」とされていた区域に集中して被害が出ています。
一方、平坦地でも埋立地などでは液状化現象が起きやすく、地震に弱い地盤であることが多いです。逆に、内陸部や標高の高い地域では津波の被害は避けられるなど、災害の種類と影響が変わってきます。
住む前には自治体のハザードマップを確認し、災害リスクを事前に把握することが、自分と家族の命や資産を守る第一歩になります。
保険と備蓄も「資産防衛」の大事な手段
災害が起きたとき、大切な資産を守るためには「保険」と「備蓄」の両方が欠かせません。たとえば地震保険や火災保険に加入していれば、住宅や家財の被害に対して金銭的な補償を受けられ、生活の立て直しに役立ちます。実際に地震や台風の被災後、保険金で修繕費をまかなえたケースも少なくありません。
一方で、災害発生直後は物資が手に入りづらくなります。そのため、飲料水や非常食、乾電池やモバイルバッテリー、簡易トイレなどの備蓄は「生活を守る資産」として非常に重要です。備蓄がないと、避難所での生活負担や買い出しの危険性が増します。
保険で「金銭的な復旧」を、備蓄で「日常の継続」をカバーすることが、資産防衛の実践的な第一歩といえるでしょう。
投資による資産は有形資産に比べて守備力が高くなる
災害時には、家や車などの有形資産は直接的な被害を受けやすく、破損や全損のリスクがあります。実際に地震や台風で住宅が倒壊したり、浸水で車が使えなくなったという事例も少なくありません。
一方、株式や投資信託といった「投資による資産」は物理的な被害を受けることがなく、災害による直接的な損壊リスクがありません。つまり、物理的な守備力という点で投資は有形資産よりも強いのです。
もちろん、災害の影響で日本経済が落ち込み、国内株が値下がりするなど、投資先によっては間接的な損失が生じることもあります。しかし、「外国株」「全世界株式」などに分散投資をしておけば、被害を抑えることが可能です。
こうした分散投資は、つみたてNISAを活用することで手軽に始められます。資産の一部を投資に振り分けておくことは、「万が一」の備えとしても有効な手段といえるでしょう。
保険より先に、まずは備蓄品の見直しがおすすめ
災害への備えというと「保険」に目が行きがちですが、実際の生活を守るには、まず「備蓄品の見直し」が優先です。地震や台風、豪雨などが発生すると、電気・ガス・水道が止まり、数日間ライフラインが復旧しないこともあります。その間、飲料水や食料がないと命に関わる事態にもなりかねません。
たとえば最低でも3日分、できれば1週間分の保存水・レトルト食品・カセットコンロ・乾電池・携帯トイレなどを備えておくことが重要です。小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、オムツや常備薬、持病の薬の確保も忘れずに。
災害時、まず困るのは「電気」と「水」が使えなくなることです。だからこそ、備蓄の第一歩として「モバイルバッテリー」と「飲料水」の準備が最重要です。
停電でスマホが使えなくなると、安否確認や情報収集ができなくなり、不安が一気に高まります。モバイルバッテリーがあれば、いざというときに命綱となるスマホを守れます。容量は10,000mAh以上あるものがおすすめです。
そして水。人は水がなければ3日と生きられません。1人1日あたり約3リットルが目安です。最低でも家族分×3日分を備えておきましょう。
保険は「災害後」に力を発揮しますが、備蓄は「災害直後の命と生活」を守ります。まずはご自宅の備蓄品を今すぐ確認することから始めてみましょう。
災害が起きる前にこそ「できる備え」がある
家具の固定、家屋の耐震診断、避難ルートの確認、行政の防災アプリの活用など、日常に取り入れられる対策は数多くあります。
特に戸建て住宅では、古い建物ほど耐震補強が重要です。さらに、災害後には詐欺や便乗商法が横行するケースもあるため、冷静な判断力と正しい情報の取得も欠かせません。
非常用の持ち出しバッグを準備しておけば、いざという時すぐに避難できます。バッグには水や食料、モバイルバッテリー、常備薬、衛生用品などを入れておきましょう。
また、家族との連絡手段や集合場所を事前に話し合っておくことで、混乱時でも落ち着いて行動できます。家具の転倒防止器具の取り付けや、ガス・電気の遮断方法を確認しておくことも、二次災害の防止に有効です。
備えは、命を守る「最も手軽で確実な防災対策」です。
まとめ:命と資産を守るために「備え」は今すぐに
災害はいつ起こるかわかりません。しかし、備えることは今すぐにできます。
居住地の選定、保険の加入、備蓄の準備、家族との話し合いなど、小さな行動の積み重ねが、大きな被害を防ぎます。「まさかの時」を「備えていてよかった」に変えるために、今日からできることを始めましょう。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。