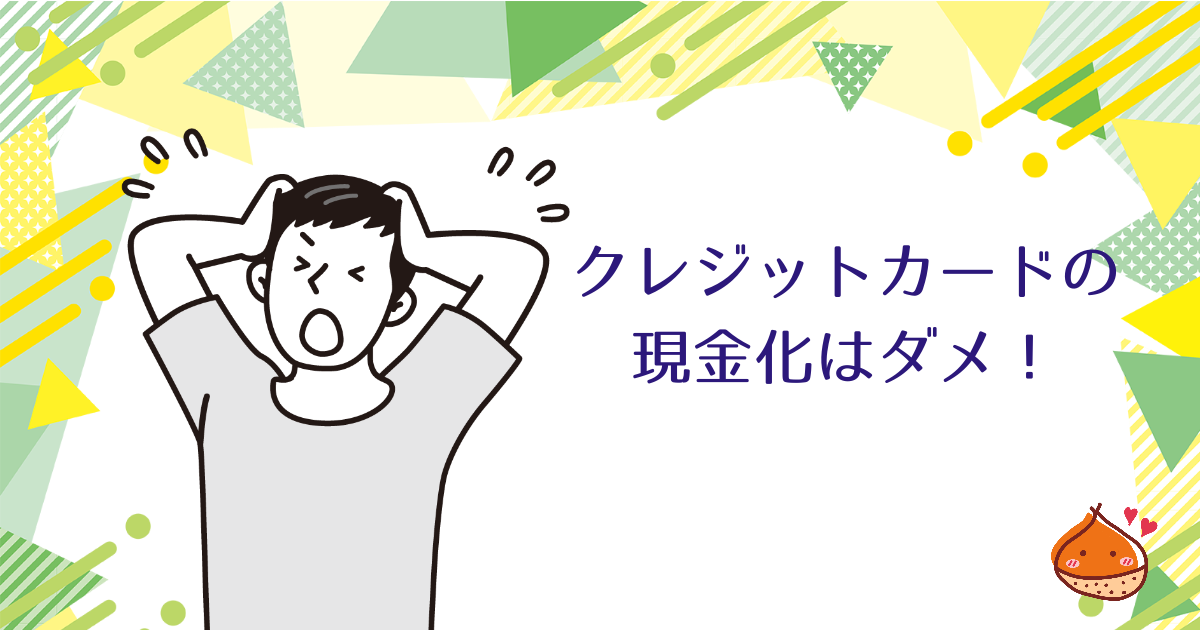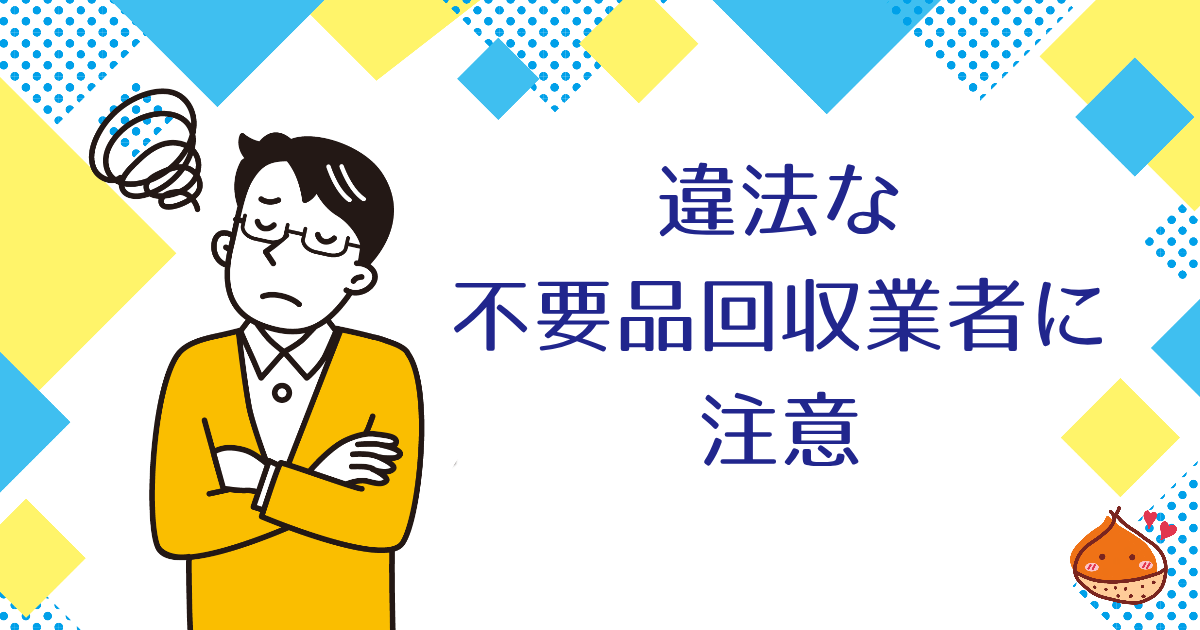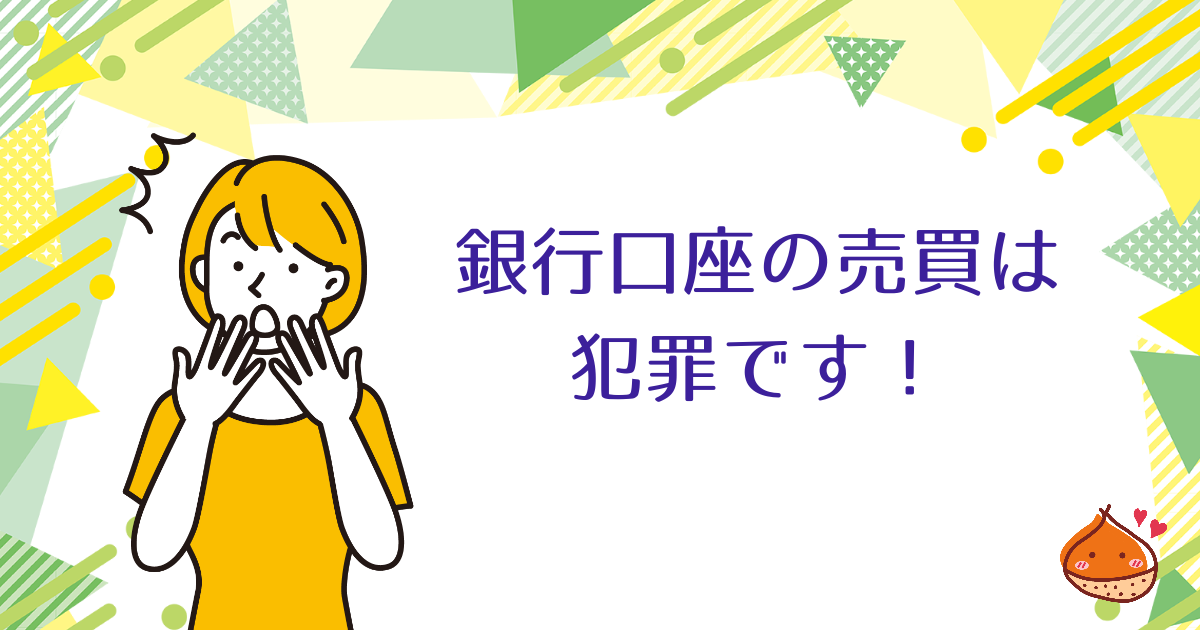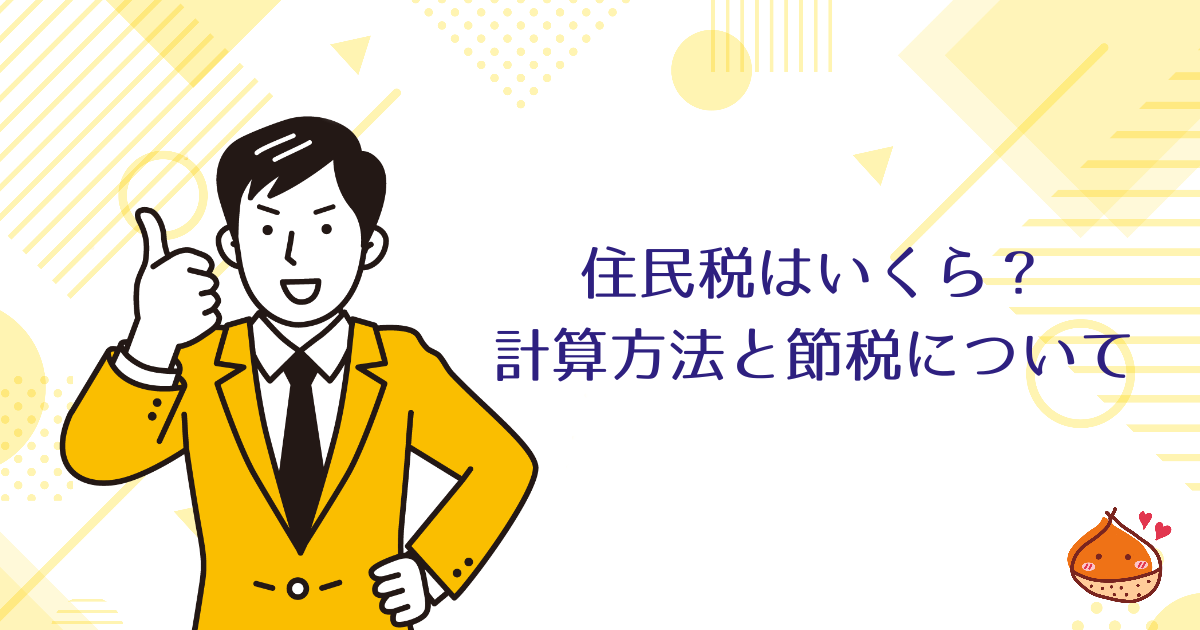
社会人1年目には給料から引かれていなかった住民税。2年目から引かれることはご存知ですか?
所得税と違って前年の収入をもとに決まり、「なんでこんなに高いの?」と驚くことも…。
でも大丈夫です。
この記事では、年収から住民税を計算する方法や、節税のポイントを分かりやすく解説します。
自分の住民税をざっくり計算する方法
税金を少しでも抑えるための節税テクニック
社会人2年目からの住民税の注意点
これらを知っておけば、無駄に税金を払うことなく、賢くお金を管理できるようになります!
それでは、詳しく見ていきましょう!
1. 住民税とは?基本を知ろう
住民税の概要
住民税とは、都道府県や市町村などの地方自治体に納める税金のことです。国に納める所得税とは異なり、地方の行政サービス(道路整備や福祉、教育など)に使われます。
住民税には以下の2つの種類があります。
- 都道府県民税:都道府県に納める税金
- 市町村民税(東京23区では特別区民税):住んでいる市町村に納める税金
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得を基に計算され、翌年の6月から支払いが開始されます。前年に所得がない場合は、住民税は発生しません。
住民税の納付方法
住民税は働き方によって徴収方法が異なります。
- 給与天引き(特別徴収):会社員や公務員の場合、毎月の給料から自動的に引かれます。
- 自分で納付(普通徴収):フリーランスや個人事業主の場合、自治体から送られてくる納付書を使って支払います。
2. 住民税の計算方法
住民税は 「所得割」 と 「均等割」 の2つで構成されています。
住民税の内訳
- 所得割:前年の所得に応じて決まる(通常、課税所得の10%程度)
- 均等割:所得に関係なく一定額を支払う(都道府県民税 1,000円、市町村民税 3,000円が標準)
住民税は、「課税所得」 に応じて決まるため、所得控除を利用することで住民税を減らすことが可能です。
住民税はお住まいの市区町村によって税率が異なりますが、どの市区町村も課税所得の大体10%前後の値です。
この10%の税率は、課税所得と言って1年の全ての収入から経費や所得控除(会社員の場合は給与所得控除)を引いたものにかかります。
例)年収500万円の会社員の場合
年収500万円ー(給与所得控除+控除)=課税所得200万円前後
例外の人がいるかもしれませんが、大多数はこのくらいの額に収まる人が多いかと思います。そこに税率をかけます。
課税所得200万円×10%ー税額控除額(人によって異なる)=住民税約20万円前後
「税額控除額」とは扶養控除や寄付金控除、住宅借入金特別控除などがそれにあたります。これらの金額が大きくなるほど住民税が小さくなります。後述する「ふるさと納税」がこの税額控除の対象になります。
よって、年収500万円の人は住民税が約20万円前後となります。
所得が多いほど所得割の負担額が多くなります。自治体の財政状況によって税率の増減もあるので、あなたの住んでいる自治体の公式サイトから最新情報を確認することをお勧めします。
3. 住民税を節税する方法
住民税の納付金額を小さくするには、控除を上手に活用する必要があります。
ここからは、納付額を小さくする控除についてご紹介。今より一歩進んだ節税ができますよ。
① ふるさと納税を活用する
- 住民税の控除が受けられる
- 実質2,000円の負担で地域の特産品がもらえる
- 期限内に確定申告を行ったり、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するなど、控除を受けるために必要な手続きがあるので忘れずに
控除の上限額は年収や家族構成によって異なるため、上限額を事前に確認しておきましょう。ふるさと納税を行なっている通販サイトにシミュレーターがあるのでそちらをご活用ください。
② iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する
自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
- 掛け金が所得控除の対象となり、課税所得が減る
- 節税しながら老後資金を積み立てられる
③ 医療費控除・生命保険料控除を活用する
- 医療費が年間10万円を超えた場合(または年間所得が200万円までの人は所得合計額の5%)、確定申告で住民税が軽減される
- 生命保険料を支払っていると、最大7万円の控除が適用される
④ 配偶者控除・扶養控除を見直す
- 配偶者や扶養家族がいる場合、控除を活用することで住民税を減らせる
4. 住民税を滞納したらどうなる?
延滞金が発生する
住民税を期限までに支払わないと、延滞金 が発生します。延滞が長引くほど金額が増えるため、早めに支払いましょう。
差し押さえの可能性がある
未納が続くと、銀行口座や給与の差し押さえを受ける可能性があります。法律上は「督促状を送付してから10日を超えた時点」で納付がなされないと、滞納者の財産を差し押さえることができます。
分割納付の相談が可能
会社員であれば給料から天引きされるので未払いになることは少ないと思いますが、自分で収める普通徴収を選択している場合、どうしても納付が難しくなる時があるかもしれません。
一括での支払いが厳しい場合は、自治体に相談することで 分割払い が可能な場合があります。
お住まいの自治体に相談してくださいね。
5. 社会人2年目から支払いが始まる
住民税は社会人1年目には徴収されず、2年目から支払いが始まる仕組みになっています。これはどういうことなのか、詳しく解説します。
なぜ社会人1年目は住民税がかからないの?
住民税は、「前年の所得」に対して課される税金です。つまり、前年に収入がなかった場合(学生だった場合など)、住民税の課税対象にならないのです。
住民税の課税スケジュール
住民税の計算は、以下のような流れになっています。
1月~12月 → この期間の所得に対して、翌年の住民税が決まる
翌年1月1日 → 住んでいる市区町村が住民税を計算
6月~翌年5月 → 住民税の支払いが始まる
例えば、2025年4月に新卒で入社した場合、2025年の1月~12月の間の所得が計算され、2026年6月から住民税の支払いが発生するという流れです。
社会人2年目に要注意!住民税の支払いが始まるタイミング
2年目になると、初めて住民税の支払いが始まります。給料から天引きされる「特別徴収」か、自分で納付書で支払う「普通徴収」のどちらかになります。
特別徴収(会社員のほとんどがこちら)
会社が住民税を給料から天引きして納める方式。6月から天引き開始になるので、給料が急に減ったように感じる人も多いです。
普通徴収(自営業やフリーランス向け)
市区町村から送られてくる納付書を使って、自分で納付する方式。支払いは年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分かれています。
2年目からの住民税に備えるためにやるべきこと
6月からの手取り減少を想定しておく → 住民税分の貯金をしておくと安心です
給与明細をチェックする → 住民税が引かれ始めたか確認しましょう。わからない場合は会社の総務の人に問い合わせてください。
副業収入がある人は確定申告を忘れずに! → 副業や株式の保有などによる所得や配当がある場合は、それに対しても住民税がかかるので納付が必要です。
6. 住民税をクレジットカードで納付するメリット
個人事情主の方は、住民税をご自分で収める必要があります。
会社員の方でも副業や株の配当金がある場合、普通徴収をしている方もいるかもしれません。
「支払うだけで何も得にならない」と思っていませんか?
実は、クレジットカードで住民税を納付することで、ちょっとしたお得が生まれる のです。
今回は、クレジットカードで住民税を支払うメリットについて解説します!
住民税をクレジットカードで納付する方法
住民税は、各自治体のオンライン納付システム(例:都道府県・市区町村の公式サイト)などを利用することで、クレジットカードで納付できます。
※利用できるクレジットカードや手続き方法は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
クレジットカード納付のメリット
① ポイントが貯まる
クレジットカードで納付すると、利用額に応じた ポイント が貯まります。例えば、還元率1%のカードで10万円の住民税を納付すれば 1,000円分のポイント を獲得できます。
② 高額納付でカードの特典を活用できる
クレジットカードには「年間利用額に応じて特典がもらえる」制度があります。例えば、年間100万円利用でボーナスポイントが付与されるカードなら、住民税の支払い分もカウントされるため、特典獲得に近づきます。
③ 分割払いやリボ払いが可能(※おすすめはしない)
クレジットカードで納付すれば、支払方法を分割払いやリボ払い にすることもできます。ただし、これらは 金利手数料が発生する ため、余裕がある場合は 一括払い が基本です。
④ 現金を用意する手間や時間が省ける
住民税を金融機関やコンビニで支払う場合、現金を用意する手間と移動時間がかかります。一方、クレジットカードならオンラインで簡単に納付できるため、忙しい人にとって便利です。
時間や場所を選ばずに支払うことができるのは大きなメリットです。
クレジットカード納付の注意点
① 手数料がかかる
クレジットカード納付には 決済の際に利用料金などの手数料 が発生します。各自治体の公式サイトより手数料を確認してください。
手数料よりもポイント還元が上回るかどうかを計算するのが重要です!
例えば、還元率1.5%のクレジットカードなら、10万円の納付で1,500円分のポイントが貯まります。手数料分を差し引いてお得になるかどうか、確認することが大切です。
② 自治体によって対応が異なる
すべての自治体がクレジットカード納付に対応しているわけではありません。また、対応していても、利用できるカードの種類が限定されている場合があるので、事前に公式サイトで確認しましょう。
③ 利用限度額に注意
高額な住民税を納付する場合、クレジットカードの 利用限度額 を超える可能性があります。支払い前に、自分のカードの上限額をチェックしておきましょう。
7. あなたの暮らしをよくする住民税
「住民税」と聞くと、「給料から引かれるお金」「支払うのが大変」といったマイナスな印象を持つ人もいるかもしれません。
しかし、住民税は私たちの生活を支える大切な役割を果たしています。あなたが普段何気なく利用している公共サービスやインフラも、住民税によって支えられているのです。
住民税は何に使われている?
住民税は、主に 地方自治体(市区町村や都道府県)の運営費 に充てられます。具体的には、次のような公共サービスや施設の維持に使われています。
① 教育や子育て支援
子どもたちの教育環境を整え、未来を担う人材を育てるために使われています。
② 医療・福祉サービス
病院での治療や、高齢者・障がい者の生活支援に役立っています。
③ 道路や公共交通の整備
安全で快適な移動環境を守るために使われています。
④ 消防・警察・防災対策
火事や災害が発生したときの命綱を支えるために使われています。
⑤ 住環境の整備・公園や図書館の運営
快適に暮らせるまちづくりのために使われています。
住民税を納めることで、私たちの暮らしが支えられる
住民税は「自分のためだけに払うお金」ではありません。地域全体の生活を豊かにし、将来の安心を守るための大切な財源です。
例えば、道路が整備されていなければ通勤が不便になり、消防・警察が機能しなければ災害時に助けを求めることができません。住民税を納めることで、こうした公共サービスが維持され、私たちが安心して暮らせる社会が成り立っているのです。
住民税の使い道を知ると、納税の意識が変わる!
「ただ取られるお金」ではなく、「自分たちの生活をより良くするための投資」と考えると、住民税の見え方が変わってきます。自治体によっては、税金の使い道を公表しているところもあるので、自分が住んでいる地域の情報をチェックしてみるのもおすすめです。
住民税は、あなたの暮らしを守るために使われています。大切な税金がどのように活用されているのかを知り、より良い地域づくりに関心を持つきっかけにしてみてはいかがでしょうか?
税金をもっと知りたい人へのおすすめ書籍
税金についてもっと広く知りたい人へ。
Youtubeでお金の知識を発信しているリベラルアーツ大学の両学長「本当の自由を手に入れる お金の大学」はとてもわかりやすくて初心者におすすめです。
この本を読むだけで、周りより一歩も二歩も先を行く金融リテラシーを身につけることができますよ!
8. まとめ
住民税は前年の所得に応じて決まる
控除を活用すれば住民税を減らせる
ふるさと納税やiDeCoで節税が可能
納付が厳しい場合は早めに自治体へ相談するのが大切
今回の記事は住民税について少し深く書きました。なんて生真面目な硬い記事・・・人によっては面白くないかもしれません。
ですが、こういった知識で周囲と差が生まれます。
ここまで読んだあなたは、「どうしたら節税ができるか、クレジットカードでお得になるか」が理解できているはず。素晴らしい!
住民税の基本がわかると、お金も貯まりやすくなります。
税金は正しく理解し、計画的に支払うことで負担を減らせます。節税対策を活用しながら、賢く管理していきましょう!
皆さんのお役に立てるように、あかぐりも勉強し続けます。一緒に勉強をしていきましょう。
<記事を作成するにあたって参考にしたサイト>
総務省 個人住民税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
(参照:2025-04-01)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
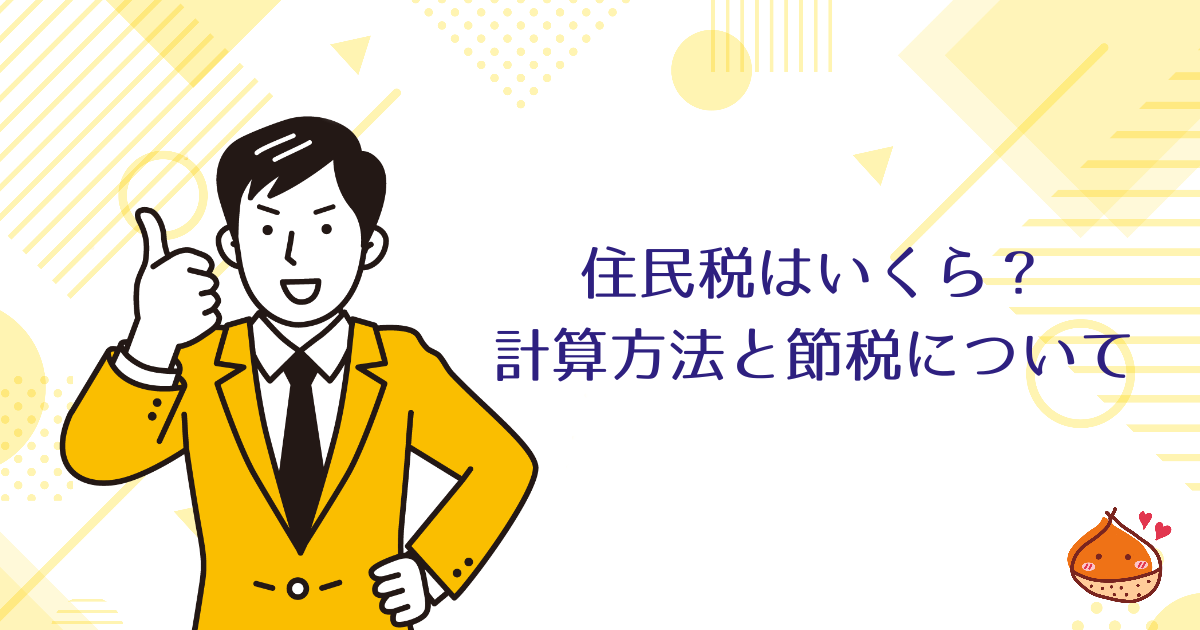
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。