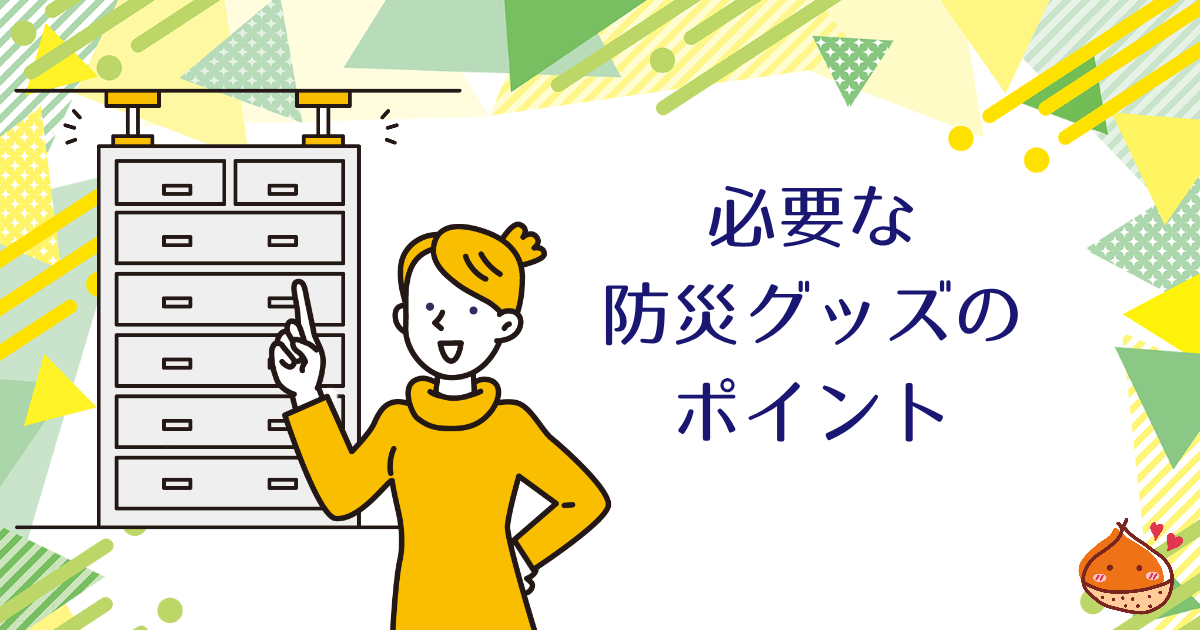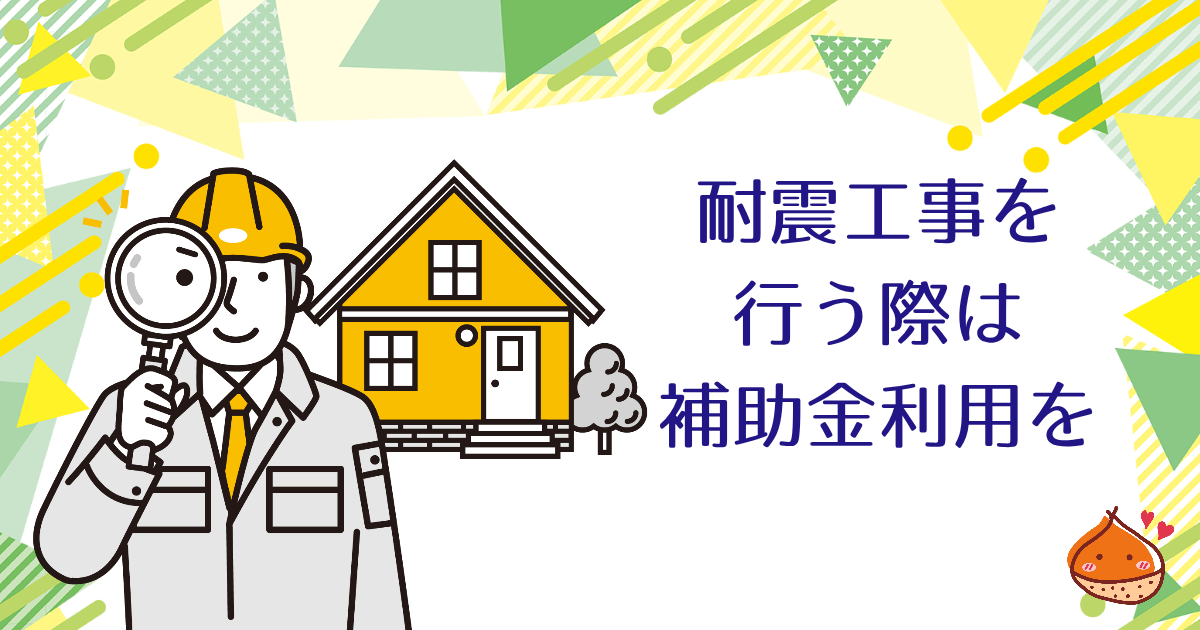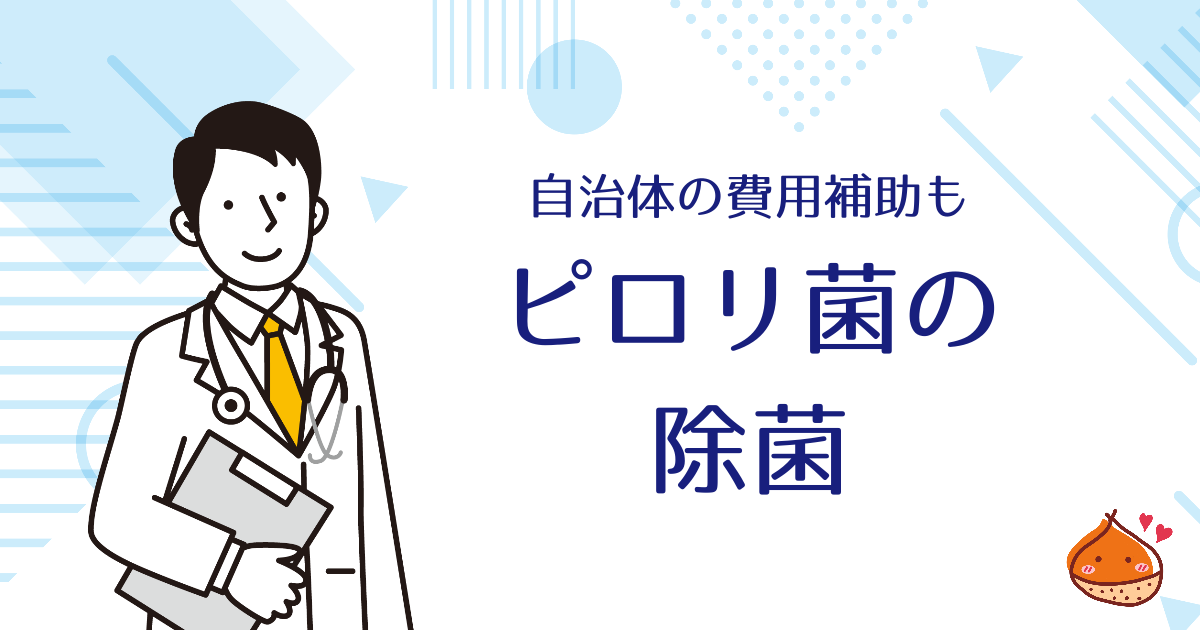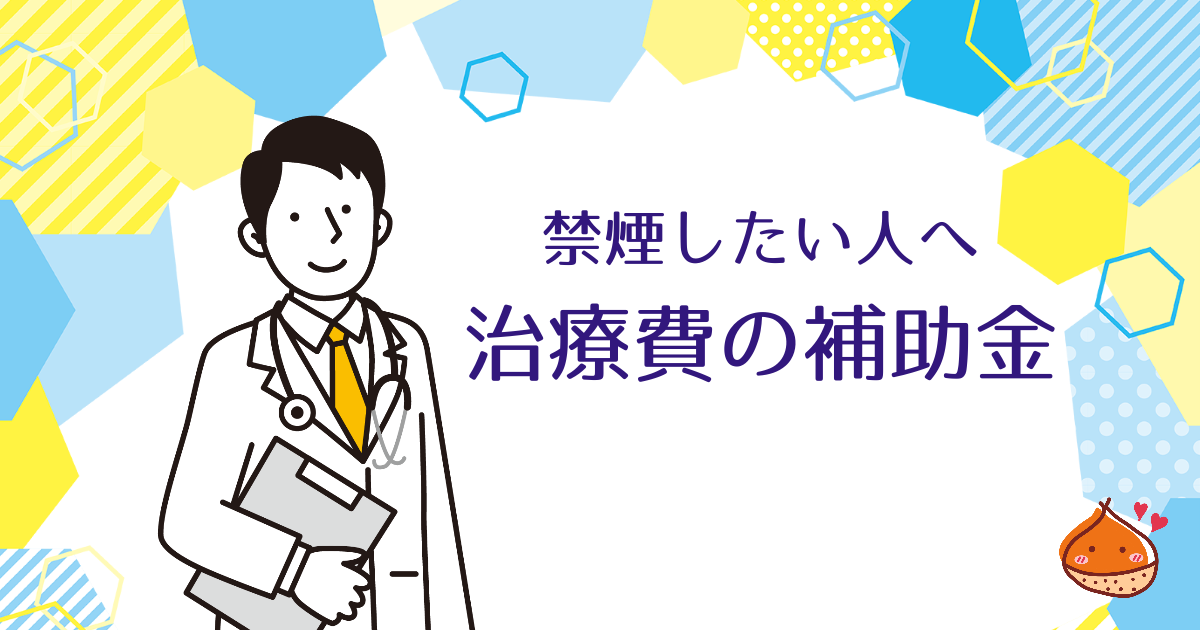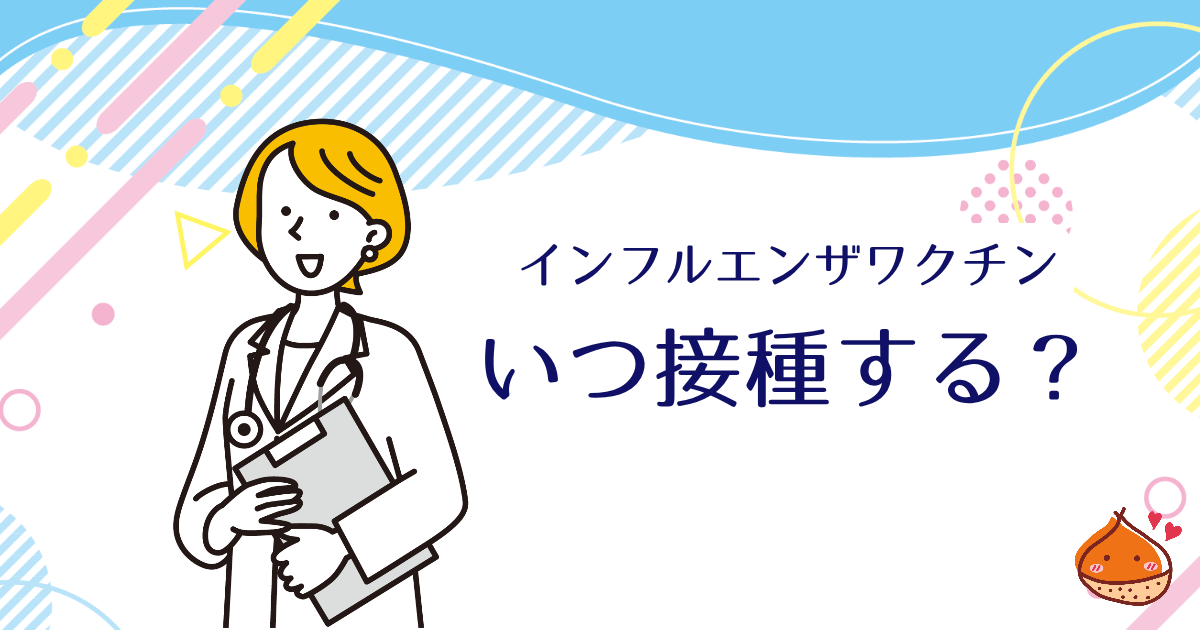
毎年秋から冬にかけて流行するインフルエンザ。
重症化を防ぐために予防接種が推奨されていますが、「結局いつ打てばいいの?」「費用について補助制度はあるの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
インフルエンザワクチンは効果が出るまでに少し時間がかかり、持続期間にも限りがあります。
本記事では、予防接種の効果と接種の目安時期、さらに健康保険組合や自治体の補助制度を活用する方法についてわかりやすくご紹介します。
インフルエンザ予防接種の効果と持続期間

ワクチンの効果が現れるまで約2週間かかる
インフルエンザの予防接種を受けても、その効果はすぐに発揮されるわけではありません。
体の中で抗体が作られるのに時間が必要で、一般的に接種から2週間ほどで免疫力が整い始めます。
つまり、接種したその日から安心できるわけではなく、流行が本格化する前に余裕をもって打つことが大切です。特に学校や職場で感染が広がる前に準備しておくと安心です。
効果の持続期間は約5か月程度
インフルエンザワクチンの効果は永続的ではなく、およそ5か月程度といわれています。そのため、シーズンの初めに打っても、春先まで効果が続くとは限りません。
日本ではインフルエンザの流行は12月から3月ごろにピークを迎えることが多いため、持続期間を意識したスケジュールが必要です。
特に受験生や高齢者など、感染リスクの高い人は注意して計画を立てましょう。
流行シーズンに備えて「接種時期を逆算する」ことが大切
ワクチン効果の発現と持続期間を考慮すると、「いつ接種するか」がとても重要になります。
例えば、12月から流行が始まると想定するなら、効果が現れるまでの2週間と持続期間5か月を逆算して、10月〜11月ごろの接種が理想的です。
早すぎるとシーズン終盤には効果が薄れ、遅すぎると流行初期に間に合わなくなる可能性があります。自分や家族の生活環境に合わせて、最適なタイミングを選びましょう。
打つべきおすすめの時期

一般的には10月〜11月がベスト
インフルエンザの流行は例年12月から3月にかけてピークを迎えます。
そのため、効果が出るまでの約2週間と持続期間5か月を考慮すると、10月〜11月に接種しておくのが最も理想的とされています。
この時期に打っておけば、年末年始や受験シーズンなど感染リスクが高まる時期をカバーできます。家族や職場の予定を考えて、この時期を目安に接種計画を立てましょう。
早すぎると流行期の後半に効果が薄れる可能性あり
9月などシーズンのかなり早い時期に接種すると、流行が長引いた場合に翌年の2月〜3月には免疫効果が薄れてしまう可能性があります。
特に受験や卒業イベントなど大切な予定が春先にある人は、接種が早すぎると安心できません。
もちろん、早めに準備するメリットもありますが、持続期間を考えるとベストな時期を逃さないことが大切です。
遅すぎると免疫がつく前に感染のリスクが高まる
逆に、12月以降に接種すると、効果が出るまでの約2週間の間に流行が本格化し、感染リスクが高まってしまうおそれがあります。
せっかく接種しても、流行のピークに間に合わなければ予防効果を十分に得られません。年末に体調を崩さないためにも、遅くとも11月中には接種を済ませておくことが安心です。
特に小さな子どもや高齢者は早めの対策が重要です。
子ども・高齢者・基礎疾患のある方は要注意
子どもは2回接種が必要な場合あり → 早めのスケジュール調整を
小児科で接種する子どもの場合、年齢や過去の接種歴によって2回接種が必要になることがあります。
1回目と2回目の間隔は約2〜4週間空ける必要があるため、流行期に間に合わせるには早めのスケジュール調整が欠かせません。
特に保育園や小学校に通う子どもは集団生活で感染リスクが高く、家庭内に広がるきっかけにもなりがちです。保護者が早めに計画を立て、家族全体で予防意識を高めていくことが重要です。
高齢者・持病がある人は重症化リスクが高いため接種の検討を

高齢者や糖尿病・心疾患・呼吸器疾患など基礎疾患を持つ人は、インフルエンザにかかると重症化のリスクが高いとされています。
肺炎や入院につながるケースもあるため、予防接種は非常に有効な備えです。また、体力や免疫力が低下していると感染後の回復に時間がかかることもあります。
地域によっては高齢者向けの補助制度があるので、自治体の情報も確認すると安心です。
医師と相談してベストなタイミングを決めることが重要
基礎疾患がある方や薬を常用している方は、かかりつけ医と相談して接種の可否や時期を判断することが大切です。
体調や治療中の病気の状況によっては、接種を控えるべき場合や、逆に早めに接種すべきケースもあります。医師に相談することで、副反応や相互作用に関する不安も解消できます。
自己判断せず、専門家のアドバイスを受けながら、無理のない予防を進めましょう。
コロナワクチンも接種したい場合は、事前に医師に相談

インフルエンザワクチンとコロナワクチンを同じ時期に接種したいと考える人も多いでしょう。
原則的には、種類によって同時接種や間隔を空ける必要がある場合があるため、医師に確認して調整するのが安心です。接種間隔を誤ると効果が十分に得られなかったり、副反応が強く出る懸念もあります。
体調やスケジュールを考慮しながら、安全に両方のワクチンを受けられるよう、早めに医師と相談しておきましょう。
保険組合や自治体の補助制度を活用しよう
多くの健康保険組合が接種費用を一部補助している
インフルエンザの予防接種は全額自己負担と思われがちですが、実際には多くの健康保険組合で補助制度が設けられています。
たとえば、数千円の接種費用のうち半額程度が補助されるケースもあり、家計の負担を大きく減らせます。
補助の内容や申請方法は健保組合ごとに異なるため、会社からの案内や健保の公式サイトを確認するのが確実です。
接種方法も「指定医療機関のみ利用可」や「領収書を提出すれば後日還付」など、条件が細かく決まっている場合があります。
申請期限を過ぎると補助が受けられないこともあるため、早めに情報をチェックして準備しておきましょう。面倒に思えても、きちんと確認すれば数千円単位でお得になる可能性があります。
家族も対象になる場合があり、利用の検討を
補助制度は本人だけでなく扶養家族も対象になる場合があります。
小さなお子さんや高齢の両親が接種する際に補助を活用できれば、家族全体での負担が大きく軽減されます。制度を使わずに全額負担していると、結果的にかなりの出費につながってしまうかもしれません。
家族の人数が多いほどメリットも大きいので、必ず対象範囲を確認しておきましょう。知らなかったでは済まされない、実は身近で役立つ支援です。
お住まいの自治体によっては補助金も
自治体によっては、インフルエンザワクチン接種に補助金を出しているところもあります。
江東区では、お子さんのインフルエンザ予防接種に対して助成金を出しています(1回2,000円〜4,000円)。
また、千代田区では、65歳以上の高齢者は無料で接種が可能です。これはすごい!
補助額は各自治体で異なります。お住まいの自治体の公式サイトから確認してくださいね。
接種前後に気をつけたいこと

接種当日は体調を整える(熱や風邪症状があると接種不可)
インフルエンザ予防接種は、体調が万全な状態で受けることが大切です。
発熱や風邪の症状があると、接種を断られることもあります。これは、体調が悪い状態で接種すると副反応が強く出たり、正しく免疫がつかない可能性があるからです。
前日は十分な睡眠を取り、当日は朝から体調を確認しましょう。
小さなお子さんや高齢者は特に体調変化に注意が必要です。無理に予定通り接種せず、医師と相談して日程を調整しましょう。
接種後は激しい運動や飲酒を控える
接種した当日から翌日にかけては、体に負担をかけないようにすることが大切です。
激しい運動や長時間の入浴、過度の飲酒は避けましょう。これは、血行が良くなりすぎることで注射部位が腫れやすくなったり、体調不良が出やすくなるからです。
軽い散歩や日常生活程度なら問題ありませんが、スポーツやアルコールは控えめにするのが安心です。接種後は無理をせず、安静に過ごすことを心がけましょう。
副反応(腫れ・発熱など)は一時的なことが多い
予防接種を受けると、多くの人に軽度の副反応が現れます。
接種部位の腫れや赤み、軽い発熱、倦怠感などが代表的です。これらは体が免疫を作っているサインであり、通常は2〜3日以内に自然と落ち着きます。
特に子どもや高齢者は反応が出やすい傾向にありますが、必要以上に心配しなくても大丈夫です。水分をしっかりとり、休養を優先すれば改善していくことがほとんどです。
副反応が酷い場合は医療機関受診の検討を
まれに高熱や強い頭痛、呼吸が苦しいなどの重い副反応が出る場合があります。
これは通常の範囲を超えている可能性があるため、自己判断せずに医療機関へ相談しましょう。特にアナフィラキシーのような急激な症状が出た場合は、救急対応が必要です。
接種後30分程度は医療機関で待機するよう案内されるのも、重篤な副反応に備えるためです。異常を感じたらすぐに受診することが、安心につながります。
ところで、あなたは体温計、持っていますか?
引っ越しの際に、どっかいっちゃった、それ以来持ってないや・・・
電池が切れちゃって、買い替えてないや・・・などなど。
余談ですが、以前病院を受診した際、「熱がでました」と言って受診した親子をお見かけしました。
問診を受けているお母様が医師から「赤ちゃんの体温は?」と聞かれて「測ってません!」と答えていました。医師も困っていました。
事情は人それぞれあるでしょうが、ご自身の体調を知る上で体温を知ることはとっても重要です。一家に一台は、体温計を持っておきましょうね。
まとめ
インフルエンザワクチンは、接種から効果が現れるまでに約2週間、持続期間はおおむね5か月程度とされています。
そのため、流行シーズンに合わせて逆算し、一般的には10月〜11月に接種するのが望ましいでしょう。特に子どもや高齢者、基礎疾患を持つ方は重症化リスクが高いため、医師と相談しながら早めにスケジュールを立てることが大切です。
また、接種費用は健康保険組合や自治体の補助を活用することで、家計の負担を軽減できます。
適切なタイミングと正しい知識でワクチンを受けることで、安心して冬を過ごす備えが整います。
<記事を作成するにあたり参考にしたサイト>
厚生労働省 インフルエンザワクチン(季節性)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/influenza/index.html(参照:2025-10-2)
NHK きょうの健康 ニュース 「どうなる?今年のインフルエンザ」
https://www.web.nhk/tv/an/kyonokenko/pl/series-tep-83KL2X1J32/ep/N88JJRJP4W(参照:2025-10-2)
東京都 保険医療局 インフルエンザの定期予防接種について
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/info/influ/influenzayobossesyu(参照:2025-10-2)
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
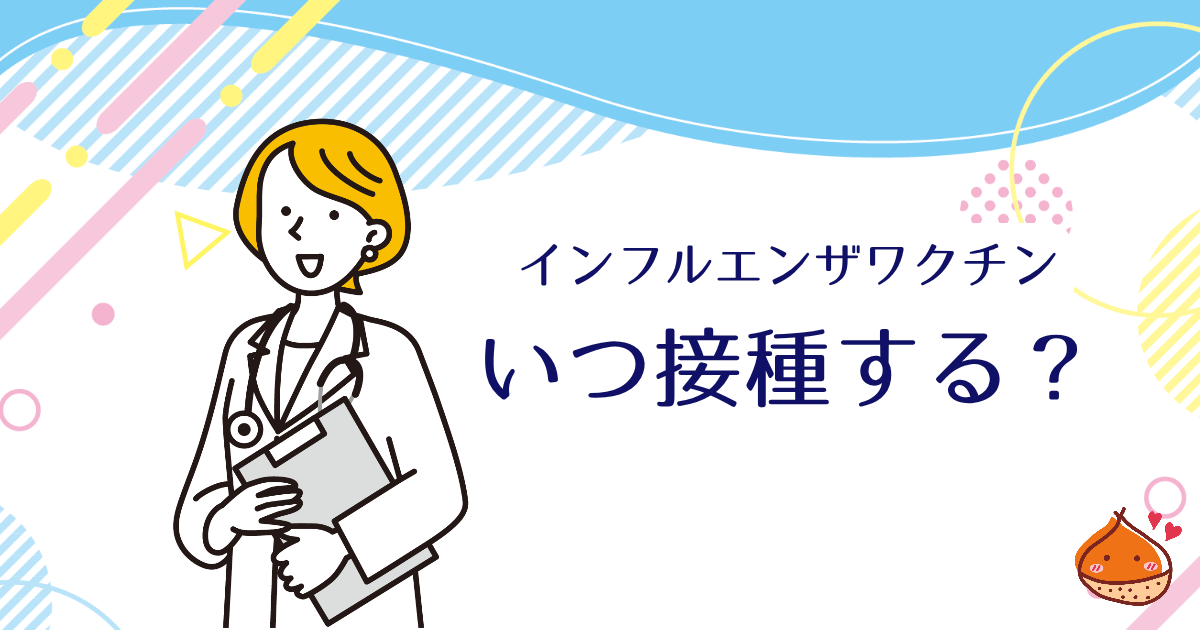
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。