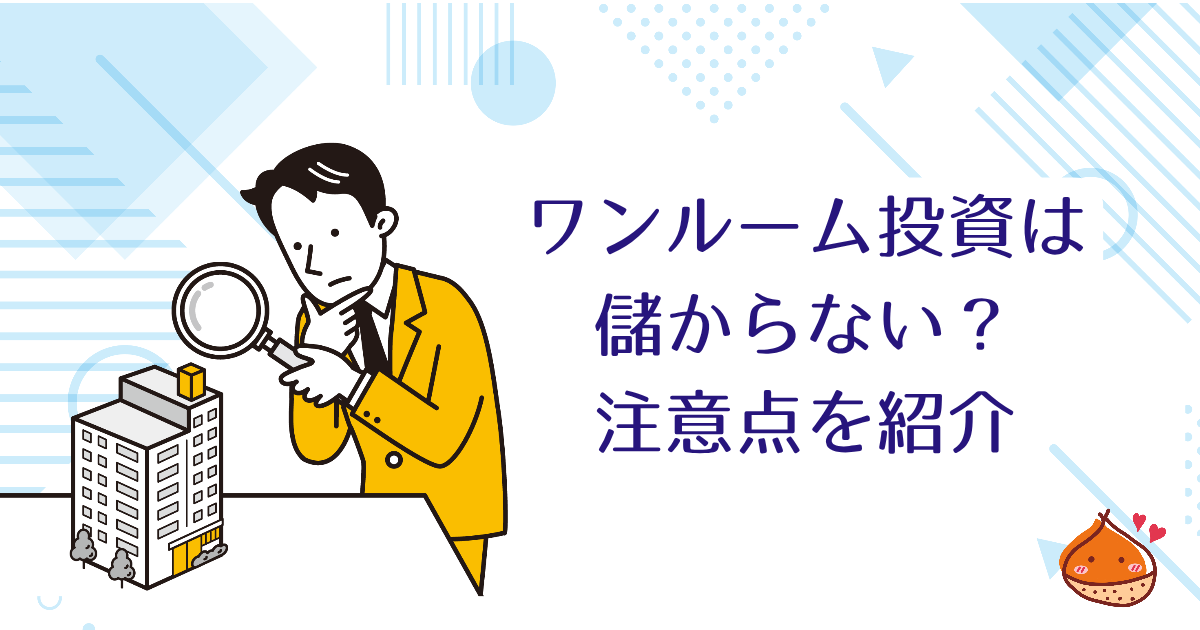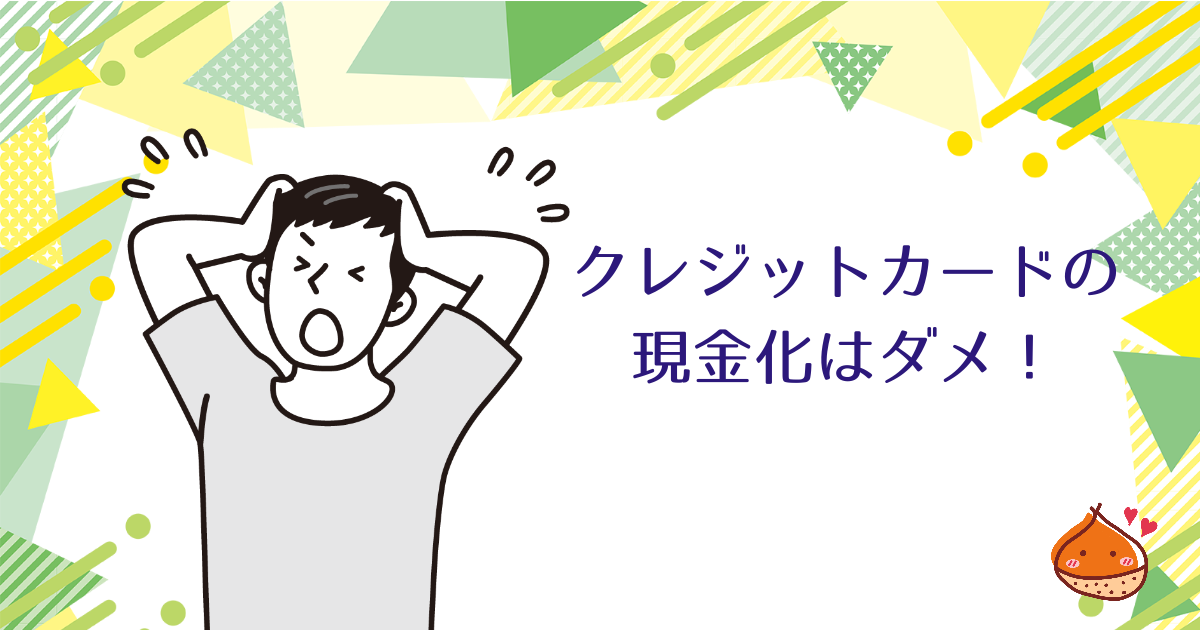物価がじわじわ上がる「インフレ」。最近の日本でも「値上げラッシュ」が続いており、家計への影響を実感している方も多いかもしれません。
インフレにはさらに深刻な形があります。それが「ハイパーインフレ」です。
最初に伝えておきますが、日本でハイパーインフレが起こる確率は低いです。
本記事では、ハイパーインフレの意味や過去の事例、日本で起こる可能性、そして私たちができる備えについて紹介します。
ハイパーインフレとは? ― お金の価値が「暴落」する現象
通常のインフレは年2~3%程度の物価上昇を指しますが、ハイパーインフレは「月50%以上」の物価上昇が続く異常な状態を指します。お金の価値がものすごい速さで下がり、昨日買えたものが今日は倍以上の値段になっている――そんな事態です。
パン1個が数千円、タクシー代が日給以上になるような世界では、現金はもはや信用を失い、国民の生活は混乱します。
ハイパーインフレが実際に起きた国とその影響
歴史を振り返ると、いくつかの国がハイパーインフレを経験しています。
ドイツ(ワイマール共和国・1920年代)
第一次世界大戦の賠償金負担と紙幣の乱発で、パン1個が数十億マルクになる事態に。国民は現金をかかえても食料が買えず、物々交換が主流になりました。
ジンバブエ(2000年代)
農業政策の失敗と政治の混乱が引き金となり、物価が「日ごと」に跳ね上がり、100兆ジンバブエドル紙幣が発行されました。
ベネズエラ(2010年代)
原油価格の下落や経済政策の失敗により、トイレットペーパーや食料がスーパーから消えるなど、深刻な生活危機が発生。
戦後の日本
日本でもハイパーインフレは起きています。
軍事費用を国債で補っていたため通貨の価値は下落。戦争によりインフラが破壊され生産能力が低下し物不足が発生しました。物価統制も廃止され、市場での物価価格が急激に上昇しました。
ハイパーインフレの主な原因
- 紙幣の大量発行 財政赤字を補うため、政府が無制限にお金を刷ると貨幣の価値が急落します。
- 国の信用の低下 経済政策の不透明さ、政治の不安定さなどで、国内外から「この国の通貨は信頼できない」と見なされます。
- 外的要因 戦争、制裁、原材料価格の急騰なども引き金になります。
日本でもハイパーインフレは起こる?
現時点で日本がハイパーインフレに陥る可能性は「低い」とされています。
たしかに、世界の歴史を見れば、ジンバブエやベネズエラのように、物価が短期間で何百倍にもなる「ハイパーインフレ」が発生した例はあります。しかし、結論から言えば 日本でハイパーインフレが起こる可能性は極めて低いと考えられています。
1. 強力な中央銀行(日本銀行)と通貨の信頼性
日銀は、インフレを抑制・調整する力を持つ中央銀行として機能しており、金融政策も世界から高く評価されています。また、日本円は「信用のある通貨」として、世界的にも安全資産と見なされています。
2. 日本円は国債の95%以上を国内で消化している
ハイパーインフレが起こる国では、国債が外国人に売られ、国家の信用が外部から失われていました。一方日本では、国債のほとんどが国内の金融機関などに保有されており、資金調達面でも安定しています。
3. 政治・治安・インフラの安定
ハイパーインフレを経験した国は、政治の混乱や汚職、戦争や制裁などの「非常事態」が背景にありました。日本は、民主主義体制が機能し、治安も良く、インフラや情報も安定しています。これは経済の信用力に直結する重要な要素です。
つまり、ハイパーインフレが起こる時とは日本政府の信頼が著しく低下する、戦争などで物が過剰に不足する時、と考えられるでしょう。
よって日本でハイパーインフレが起きる可能性は、経済の基盤や金融政策、通貨への信頼性から見ても「非常に低い」と言えます。
では「安心して何もしなくていい」のか?
とはいえ、「ハイパーインフレの確率は低い=無関心でいい」という意味ではありません。万が一に備え、通貨の分散や日用品のストック、自分自身のスキル強化といった備えは、どんな時代にも有効です。
また、世界経済の変化や地政学的リスクに敏感であることは、生活防衛の第一歩です。
だからこそ、目の前の「現実的な対策」――家計管理、収入源の確保、資産運用など――に目を向け、地に足をつけた行動をすることが、最も賢明な選択と言えるでしょう。
私たちができるハイパーインフレ対策
ハイパーインフレは国レベルの危機ですが、個人にも備えは可能です。
1. 通貨・資産の分散
円だけでなく、外貨建ての預金や資産(米ドル、ユーロなど)や、金や不動産などの「実物資産」を保有するのも手です。
2. 自分のスキルを磨く
どんな時代でも価値のある「人材」になれば、経済がどう変化しても生き残る力になります。学びや副業のスキルに投資することも「最強の備え」です。
ちなみに、ハイパーインフレの際に自給自足できる人(農業をしている人など)は最強になります。お金の価値がなくなった時は、物々交換になるでしょうね。
まとめ:通常の資産形成で対応可能、過剰な心配はしないように
ハイパーインフレは「異常事態」ではありますが、過去に現実として起こってきたものです。今の私たちにも無関係とは言えませんが、確率は低いです。
この時に、インフレを煽るビジネスには注意してくださいね。通常の資産形成でインフレ対策は可能ですし、そもそもハイパーインフレの確率は低いので特別なサービスは必要ありません。
過剰に心配したりせずに、外貨建ての資産を持つなど、できることを少しずつ行うだけで十分かと思います。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/

記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。