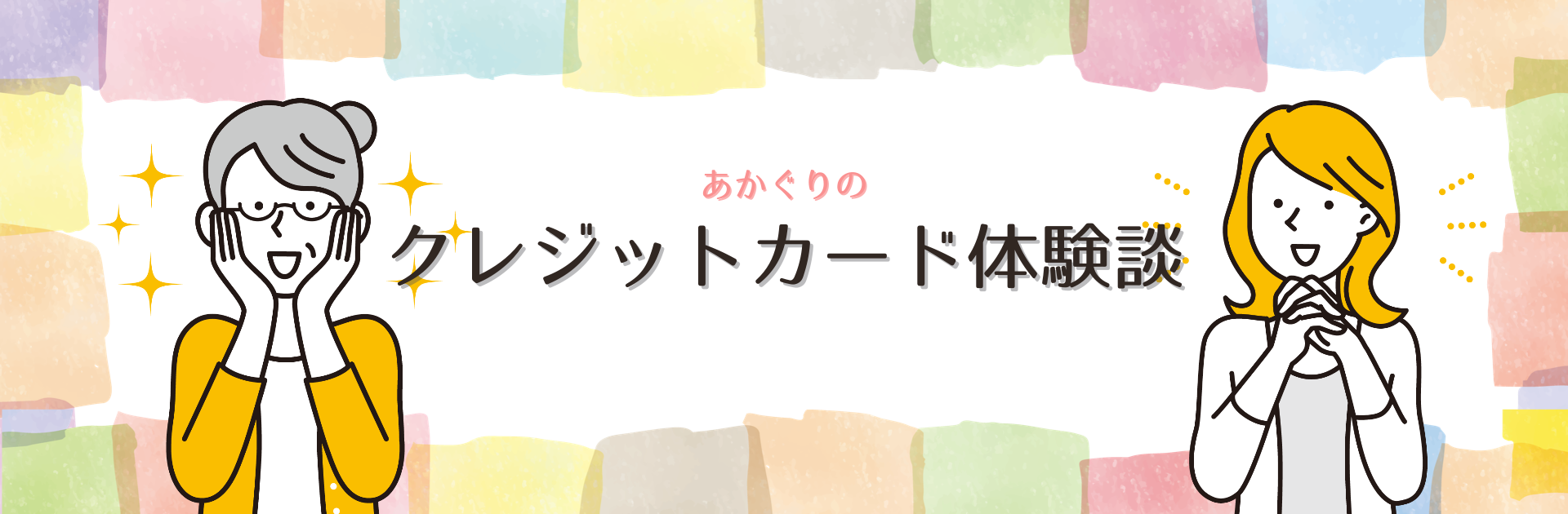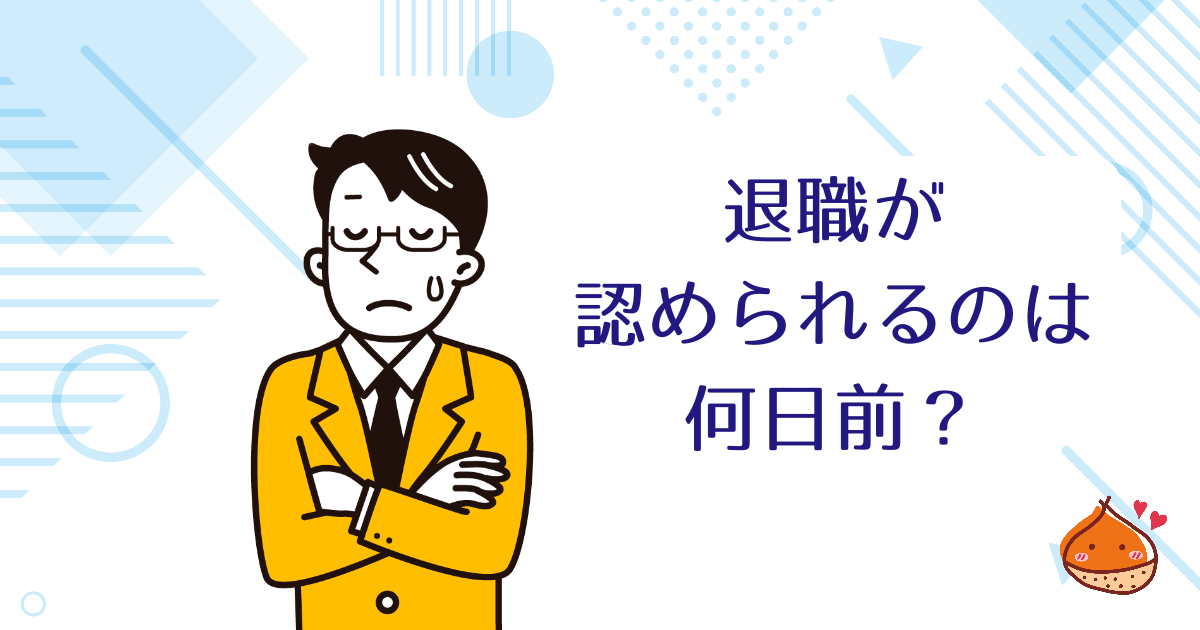退職したい気持ちが固まっても、「いつ・どう伝えればいいのか?」という疑問はつきもの。
特に就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」と書かれている場合、「本当に2週間で辞められるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、法律上の退職ルールと、スムーズに退職するためのポイントをご紹介します。
また、自己都合・会社都合の違いや、万一のトラブル時の対処法についても記載。
これを読めば、退職の大まかなコツが掴めるはずです。
法律では「2週間前」の申し出でOK(民法627条)
退職の基本ルールは、民法627条によって定められています。
期間の定めのない雇用契約(=無期雇用)の場合、退職の申し出から2週間経過すれば、雇用契約を終了できる。
つまり、正社員などの無期雇用であれば、原則2週間前の申し出で辞めることが可能です。
ただし、契約社員や期間の定めがある契約の場合は別ルールが適用されるため、契約書の内容をよく確認しましょう。
入社時の契約内容をよく覚えていない、契約時の書面等がどこにあるかわからない場合は会社に問い合わせましょう。
就業規則と法律、どちらが優先される?
多くの会社では、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申告」などと定めています。
このような規則と民法の内容が食い違う場合は、どちらが優先されるのかは議論になり、茨城労働局のサイトでは以下の判例について言及されています。
就業規則で 「退職の申し出は退職日の1ケ月前までにしなければならない」 と定めている場合ですが、先ほどの民法の規定(※)を任意規定と解して、就業規則の定めが優先するとの見解がある一方、裁判例では、民法を強行規定と解するものもあり、これによれば通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくとも退職の効力が発生することとなります。
引用:厚生労働省 茨城労働局 退職の申出があった際には
※)運営者注釈:民法627条の「期間の定めのない雇用契約(=無期雇用)の場合、退職の申し出から2週間経過すれば、雇用契約を終了できる。」を示している。
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jigyounushi_d/qa_jyametai.html(参照:2025-04-18)
上記の文章をそのまま読むと、就業規則と民法のどちらも優先されうるという見解があるということです。決まっていないんですね。
現実には会社と円満に退職するために、できるだけ早めの申し出が望ましいのも事実。残念ながら退職はトラブルになりやすい事案のひとつです。
トラブルを避けるためにも、引き継ぎや業務への影響を考えた対応を心がけましょう。
退職の伝え方とマナー
退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝えるのが基本です。
その後、書面(退職届・退職願)を提出する流れになります。
- 退職願:会社に対して「辞めたい」とお願いする形式
- 退職届:会社に辞職を通知する形式(撤回不可)
退職理由は、「一身上の都合により」で問題ありません。詳しく話す必要はありませんが、丁寧に伝える姿勢が大切です。
退職時にトラブルを避けるための配慮
退職は、人生の節目となる大切なタイミングです。しかしその一方で、会社側との行き違いや誤解が原因で、思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。
円満な退職を実現するためには、「ただ辞める」と考えるのではなく、相手への配慮がとても大切です。
退職時に気をつけたい配慮や、トラブルを避けるための実践的なポイントをご紹介します。
1. 退職の意思は「できるだけ早めに伝える」
法律では「2週間前の申し出で退職できる」とされていますが、現実的には1ヶ月以上前に伝えるのが理想的です。
突然の申し出は、会社にとって業務の引き継ぎや人員の補充の準備ができず、混乱を招きかねません。
できるだけ早めに、まずは直属の上司に口頭で伝えるようにしましょう。
退職の理由は、「一身上の都合」で問題ありません。詳しく説明する必要はなく、誠実な態度で伝えることが大切です。
2. 引き継ぎは丁寧に、わかりやすく
退職後に困るのは、あなたの業務を引き継ぐ方です。
急な引き継ぎや不十分な資料では、周囲に負担がかかってしまいます。
- 業務内容や注意点を文書でまとめる
- データやファイルは整理し、誰でも見つけられる状態にしておく
- 自分しか知らないルールやコツも書き残しておく
感謝の気持ちとともに、次の人が困らないように工夫することが、円満退職への鍵になります。
3. 感謝の気持ちは忘れずに伝える
たとえ職場に不満があったとしても、最後まで社会人としてのマナーを守ることは大切です。
- お世話になった方へ一言「ありがとうございました」と伝える
- 送別会などがあれば、誠意をもって参加する
- 最終出勤日には簡単な挨拶やお礼のメールを送る
たった一言の感謝が、相手に与える印象は大きいもの。
どんな職場でも、あなたの人生の一部だったことは間違いありません。
4. 会社とのやり取りは記録に残しておく
退職時には、有給休暇の消化や退職日の確認、離職票の発行など、重要なやり取りが多く発生します。
口頭で済ませず、メールや書面など記録が残る形にしておきましょう。口頭で言われた場合は録音をしておくと万全です。
万一、トラブルに発展したときの備えになります。
5. 感情的にならない、誹謗中傷は絶対にNG
「辞めるのだから、何を言ってもいい」
そう考えてしまうと、相手を傷つけたり、あなた自身の評価を下げたりする結果になります。
SNSで会社や上司を批判する行為も、場合によっては法的な問題に発展する恐れがあります。
最後まで冷静に、大人の対応を心がけることが、あなた自身を守ることにもつながります。
手続き上の注意点とやるべきこと
退職前後には、以下のような実務的な手続きも必要になります。
有給休暇の消化
退職前に有給を取得する権利は法律で認められています。消化したい場合は早めに相談しましょう。
社会保険・雇用保険・年金の手続き
退職後に転職先がない場合、国民年金・国民健康保険への切り替えが必要になります(14日以内)。
うっかり忘れても対処は可能ですが、早めの手続きがおすすめです。
【関連記事】退職後の手続き、14日過ぎたらどうする?について紹介しています。
引き継ぎと返却物
業務の引き継ぎや、社員証・制服・会社貸与のPCなどはしっかり返却を。上司や総務にお願いして返却品のリストをもらうと安心です。
トラブル防止のため、引き継ぎ内容を記録に残しておくと安心です。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険の給付開始時期や期間に影響があるため、退職の理由はとても重要です。
- 自己都合退職:失業保険の支給まで約3か月の待機期間
- 会社都合退職:待機期間なしで早期に受給開始、受給期間も長め
「退職勧奨」などの場合、実質は会社都合と認められるケースもあります。離職票の「離職理由」は必ず確認しましょう。
【関連記事】会社都合退職のメリット・デメリット、失業給付は増えるのかについて紹介しています。
引き止めやトラブルに遭ったら?
退職を申し出たにもかかわらず、「辞めさせない」と言われたり、無視されたりするケースもあります。
そんなときは、以下のような対処が有効です。
- 労働基準監督署に相談
- 退職代行サービスを利用する(賛否両論ありますが、すぐに辞めたい・心身ともに辛い方は利用の検討を)
- 弁護士に相談する(法律に則った退職ができ、トラブルが減る可能性があります)
まとめ
法律上、退職は「2週間前の申し出」で可能ですが、トラブルを避けるためには誠意ある対応が大切です。
- 就業規則と民法の優先度は議論になる点である
- 引き継ぎや書類の手続きなど、退職前にやることを整理する
- 退職理由や手続きに不安があれば、労働相談窓口を活用する
退職は、人生を前に進めるための一歩です。慌てず冷静に準備を進めましょう。
そしてあなたの印象は、最後の立ち振る舞いによって大きく左右されます。
円満に、そして気持ちよく職場をあとにするために、少しだけの配慮と感謝を忘れずに。
それが、これからのあなたの人間関係やキャリアにも、必ず良い影響を与えてくれるはずです。
<今回作成するにあたって参考にしたサイト>
厚生労働省 茨城労働局 退職の申出があった際には
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jigyounushi_d/qa_jyametai.html(参照:2025-04-18)
厚生労働省 確かめよう労働条件 労働条件に関する総合サイト
退職、解雇、雇い止めなど
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html (参照:2025-04-18)