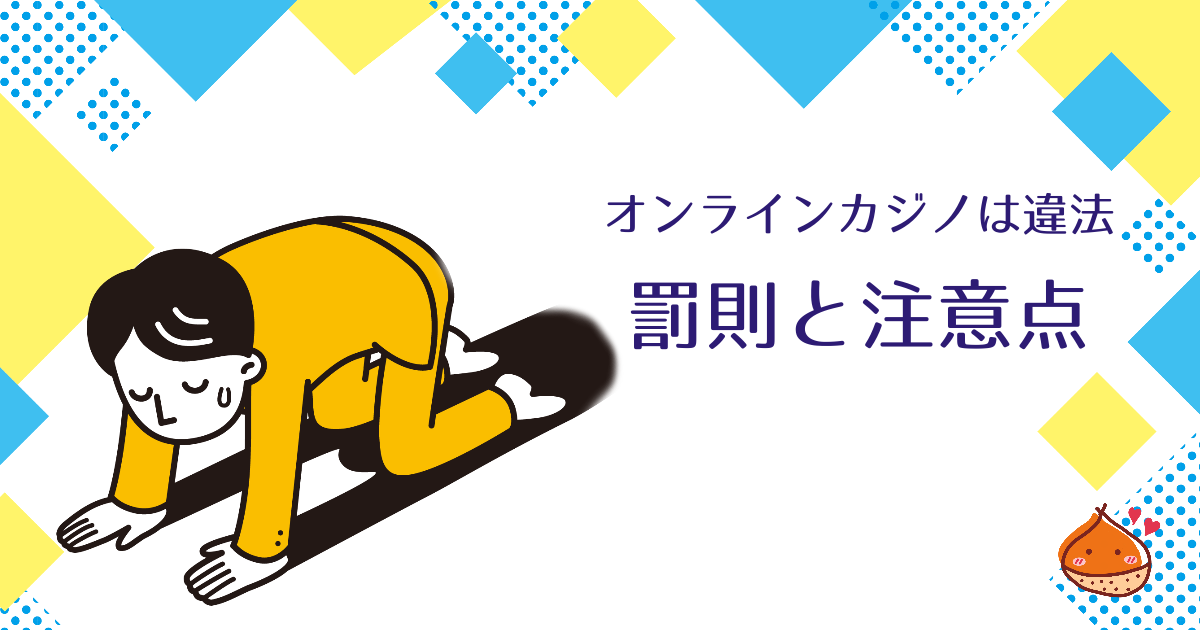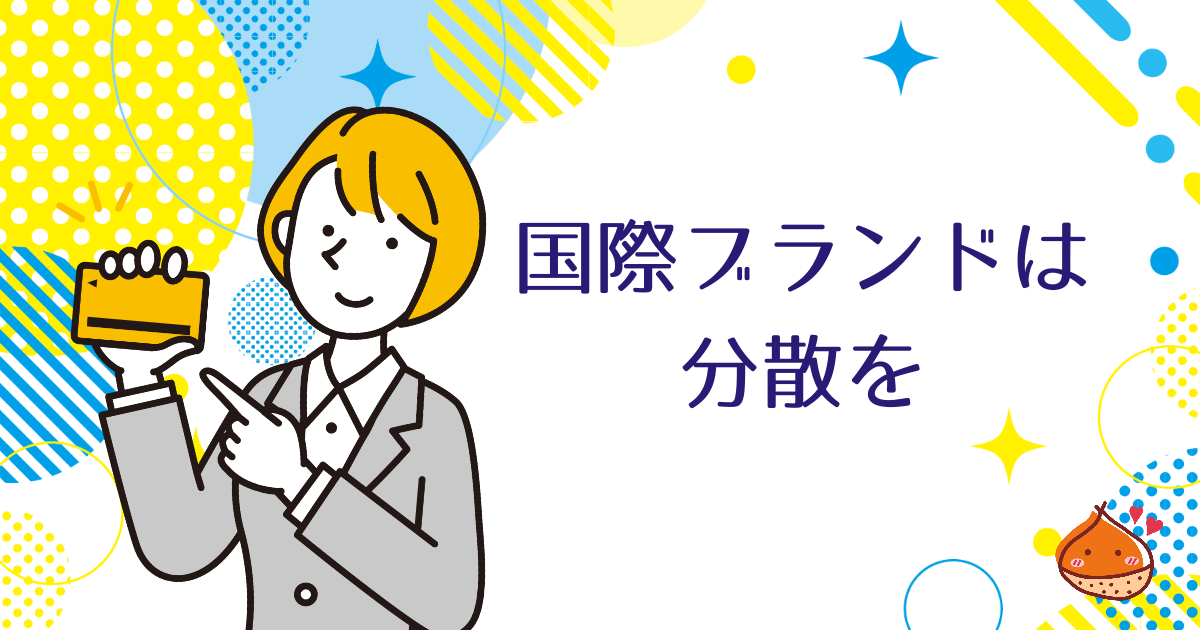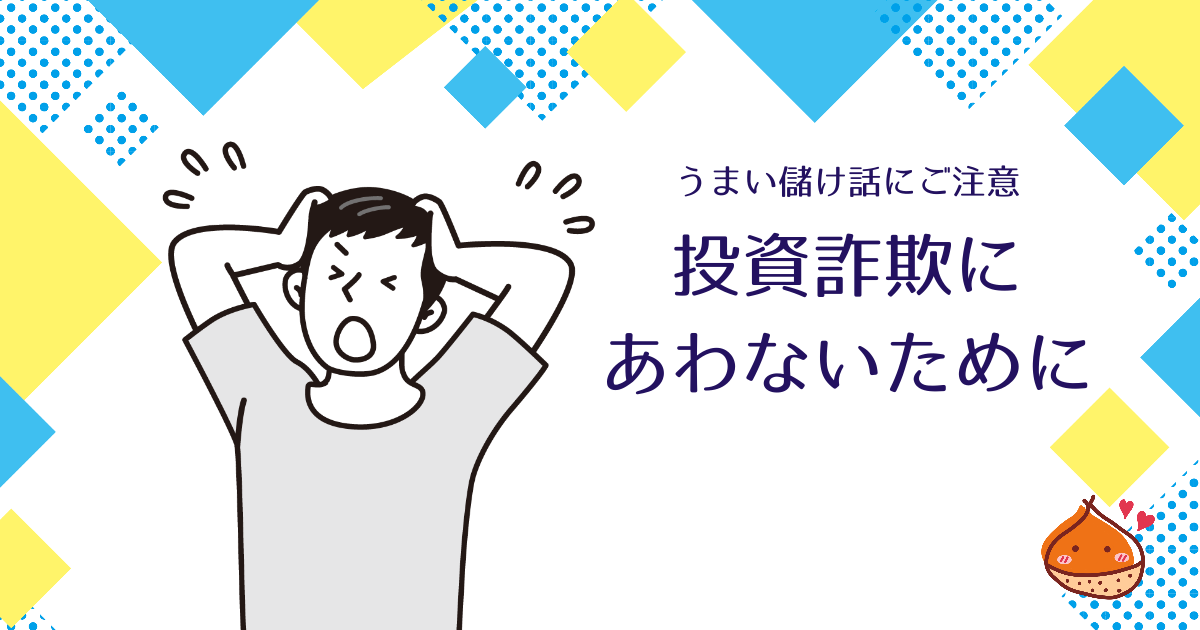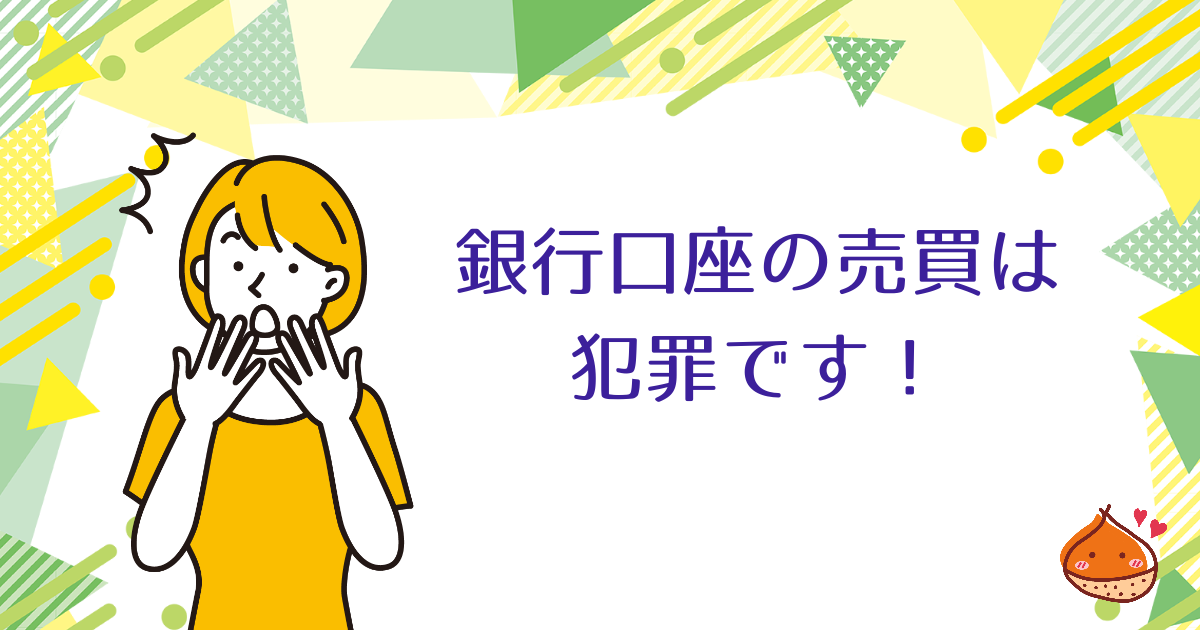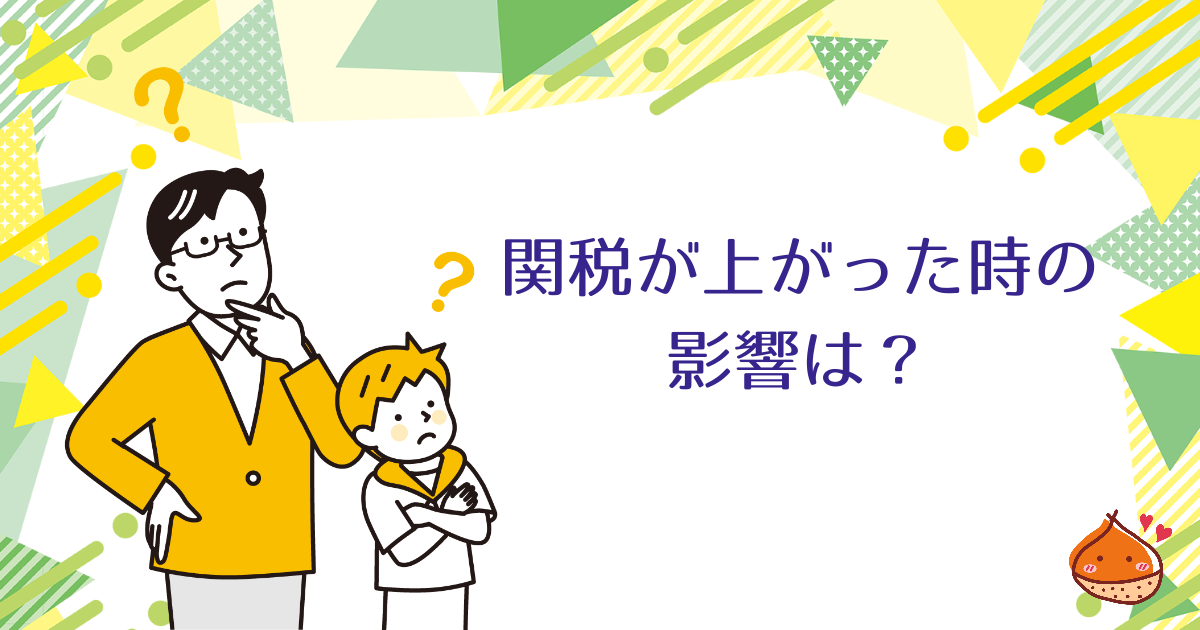
「関税」と聞くと、自分には関係のない話のように思えるかもしれません。
ですが、外国との貿易に変化があると、私たちの日常生活や家計にも影響を及ぼす可能性があるのです。
この記事では、輸出先の国の関税が上がると何が起きるのか、そして一般家庭でできる対策について分かりやすく解説します。
関税のメリット・デメリットとは?暮らしにどう影響するのかを考える
私たちが買う輸入品。その背後には「関税(かんぜい)」という仕組みが存在します。
関税は、私たちの生活にどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
そもそも関税とは?
関税とは、外国から商品を輸入する際にかかる税金のこと。
たとえば、海外から衣類や農産物を輸入するとき、その価格に一定の税金が上乗せされ、日本政府に支払われます。
関税は単なる税収手段だけでなく、「自国の産業を守る」ためにも用いられています。
今回はアメリカが関税を引き上げたので、アメリカ政府の収入が引き上げた分だけ多くなります。
「この関税誰が払うの?」となると思いますが、アメリカの場合は輸入するアメリカの企業や人が支払う仕組みになっています。
関税のメリット
① 国内産業を守る
関税をかけることで、海外の安価な商品と国内商品との価格差を縮め、国内企業を守る役割を果たします。
例えば、日本の農産物が外国産に比べて高くても、関税によって価格のバランスを取ることで、国産品が売れやすくなるという仕組みです。
② 雇用の安定につながる
国内産業が守られることで、そこに従事する人々の雇用も守られます。農業や製造業など、関税によって守られている分野は少なくありません。
③ 国家の財源になる
輸入品に関税をかけることで、政府にとっては税収が得られます。これにより、公共サービスやインフラ整備などの財源にもなります。
関税のデメリット
① 輸入品の価格が上がる
関税がかかる分、私たち消費者が支払う価格も高くなる可能性があります。たとえば関税が20%かかっていれば、1万円の商品が1万2,000円になることも。生活用品や食品など、家計に直結するケースも多々あります。
② 自由な国際貿易を妨げる
関税は「貿易障壁」とも言われ、海外企業にとっては不利な条件になります。過度な関税は他国からの反発や報復関税を招き、国際的な貿易関係が悪化する可能性も。
③ 国内の競争が減る恐れも
保護されすぎると、国内産業の競争力が落ちてしまうリスクがあります。関税で守られているからと品質や価格競争に甘えると、長期的には成長が停滞することも。
消費者にとってはどっちが得?
一概には言えませんが、消費者としては「安くて良いものが手に入りやすい自由貿易」が魅力的に感じられる一方、「自国で作られた安全なものを適正価格で買える安心感」も関税によって守られていることは事実です。
たとえば、外国産の果物が国産より安く出回ると家計は助かりますが、農家の方々が苦しんでしまう可能性もあります。関税は、このバランスをどう取るかという「調整弁」のような存在です。
関税は「守る力」と「コスト」の両面を持つ
関税は一見、私たちには関係のない話のように思えますが、実際はスーパーの値札やオンラインショッピングの価格にも影響を与える身近なテーマです。
私たち一人ひとりが「なぜこの価格なのか?」「どこの国で作られているのか?」といった視点を持つことで、モノの選び方や価値の見え方も変わってきます。
経済の仕組みに少しだけ目を向けて、より賢い消費者を目指していきたいですね。
輸出先の関税が上がると何が起きるの?
輸出企業の収益が減少する
例えば、日本の企業がアメリカに製品を輸出していたとして、アメリカが関税を20%に引き上げた場合、輸出先での販売価格はその分高くなります。
結果として、価格競争力が低下し、売れにくくなるため、日本企業の売上・利益が減る可能性があります。
国内経済にも影響が波及
輸出で稼げなくなった企業は、コストを国内価格に転嫁することがあります。
その結果、私たちが普段購入している商品やサービスの価格が上昇するケースも。
為替や株価の変動も起きやすくなる
関税が高くなると、国際的な経済のバランスが崩れ、為替レートや株価にも影響が出る可能性があります。
これがさらに、物価や投資にも波及してくるのです。
近年の経済・動向から見る関税の大まかなトレンド
1. 自由貿易の流れが基本(関税引き下げの傾向)
- WTO(世界貿易機関)やEPA(経済連携協定)、FTA(自由貿易協定)などにより、多くの国々が関税の引き下げ・撤廃を進めています。
- 日本もEUやアジア諸国との間でEPAを結び、農産物や工業製品の関税を段階的に減らす取り組みをしています。
理由
- 関税を下げることで、消費者が安く商品を購入できる。
- 輸出企業は海外市場へ進出しやすくなり、経済のグローバル化が進む。
2. ただし、保護主義の動きも一部にある(関税引き上げ)
- 特にアメリカ(例:トランプ政権時)では、中国製品に対して最大25~30%の関税を課すなど、関税を上げる政策が取られました。
- 国内産業や雇用を守ることが目的でしたが、結果的に消費者の物価上昇を招いたという批判もあります。
3. 日本の場合:関税のバランスがカギ
- 日本は食料自給率が低く、農業保護のために一部の品目(お米、乳製品など)は高い関税を維持しています。
- 一方で、製造業や輸出企業にとっては、関税が低い方がメリットが大きいため、海外との交渉で関税を下げる動きも強まっています。
4. 最近の物価上昇と関税の関係
世界的に「インフレ=物価上昇」が続いていますが、関税が高いと輸入品の価格がさらに上がるため、消費者にとってはマイナスになりやすいです。
実際、2022年以降の日本でも輸入食材や日用品の価格上昇が問題視され、「より安い輸入ルート確保」「関税見直し」の議論が強まっています。
未来のことは誰にもわからないので、慌てずに
2025年4月13日現在では、なんとなく消費者にとってはインフレがマイナスの影響を与えそうと感じていると思います。実際、お米の値段が大幅に上昇しています。
ですが、未来のことは誰にもわかりません。そのことは、心に留めておくべきです。
過去を振り返っても「予想通り」だったことは少ない
たとえば5年前、今のような働き方や生活のスタイルを予想できていたでしょうか?
AIの進化、リモートワークの普及、キャッシュレス決済の拡大など、世の中は常に予想を超えて変化しています。
未来が不確かだからこそ、焦って動いても正しい方向とは限りません。
「今できること」に目を向けて、丁寧に生きる
未来が見えないからこそ、今日を丁寧に生きることが何より大切です。
- 今の生活を見直して、少しずつ支出を整える
- 小さな成功体験を重ね、自信をつけていく
- 学びを続け、自分の可能性を広げていく
焦らず、腐らず、慌てず。未来は「準備をしていた人」にだけ、静かに味方します。
今の経済状況から見ると「賢く関税を使う」ことが重要
- 消費者目線:基本的に関税は低い方が家計にやさしい。
- 国の経済:戦略的に国内産業を保護しつつ、自由貿易を進める必要あり。
- 企業視点:海外との取引コストが下がる=関税は低い方がビジネスしやすい。
つまり、「どんな産業に」「どのタイミングで」「どんな相手国に」関税をかけるのかというバランス感覚が重要です。
家庭にできる4つの対策
1. 支出の見直しと固定費の削減
物価が上昇する兆しがあるときは、まず支出の棚卸しを。
不要なサブスクの解約や、スマホのプラン見直し、電気代の節約など、固定費を下げるだけでも大きな効果があります。
2. 国産品・地元商品を意識して選ぶ
関税引き上げの影響は輸入品や輸出に関わる部品を使った商品に出やすいです。
価格が安定しやすい国産品を選ぶことで、家計への影響を抑えられる可能性があります。
3. ポイント還元やキャッシュレス決済を活用する
買い物時には、楽天カードやPayPayなどの還元率が高いキャッシュレス決済やクレジットカードの優待特典を活用することにより、実質的な支出を減らすことができます。
【おすすめ】ポイント還元率が高い楽天カード
【おすすめ】全国10,000店舗以上で優待が受けられるエポスカード
4. 長期的な視点で「分散投資」を意識する
関税問題の影響で株価や為替が変動することもあります。
投資をしている人は、一つの資産に偏らない分散投資を心がけることで、リスクを抑えましょう。
まとめ
関税の上昇は、企業だけでなく、私たちの暮らしにも影響を及ぼす重要な経済トピックです。
ニュースを見ていると、目まぐるしく変わる情報と状況に少しげんなりしてしまうこともあるかもしれません。
疲れたら情報をシャットアウトすることも必要だと考えています。生命の危機がある場合を除いて、心身をすり減らしてまで聞くべき情報はないですから。
そして情報を得た際に、私たちにできることは――
賢く支出をコントロールすること
商品の選び方を見直すこと
日々の小さな選択が、将来の家計防衛につながります。
あかぐりは日本が大好きです。日本の農家の人がこれからも幸せに農業を続けられるように、これからも日本産の製品を買い続けたいと思います。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
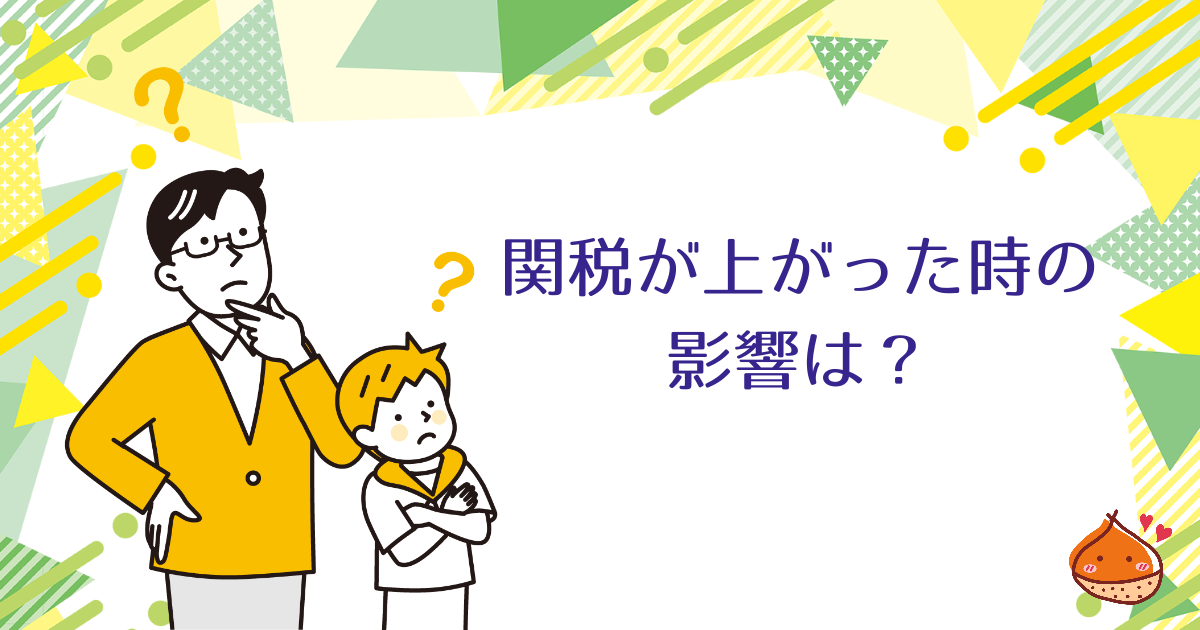
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。