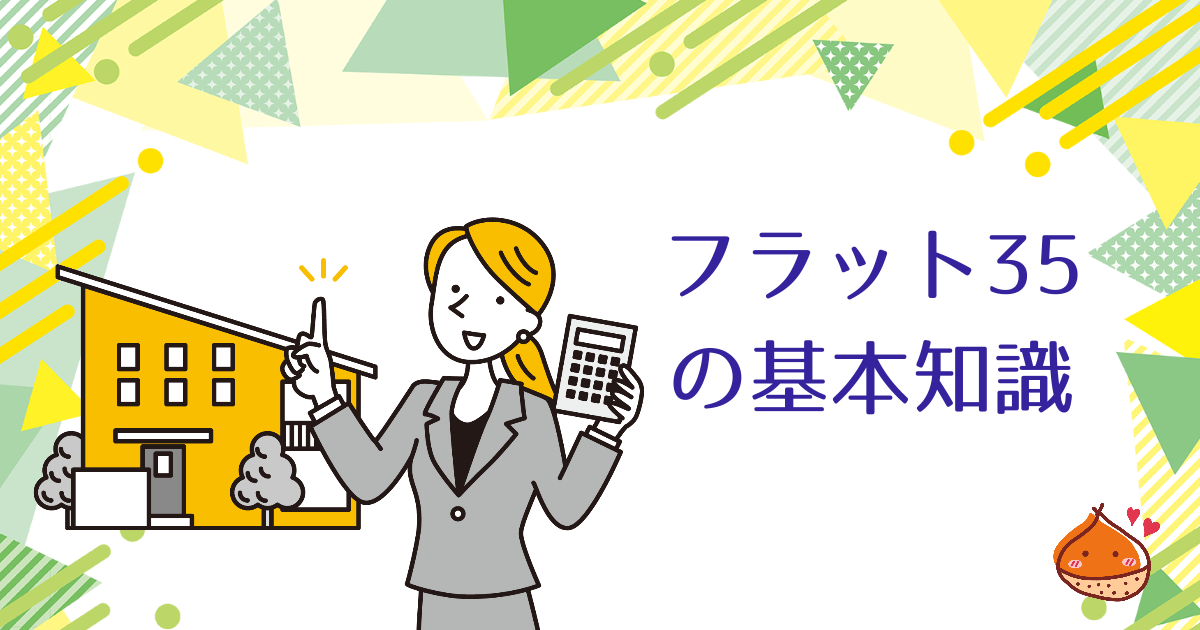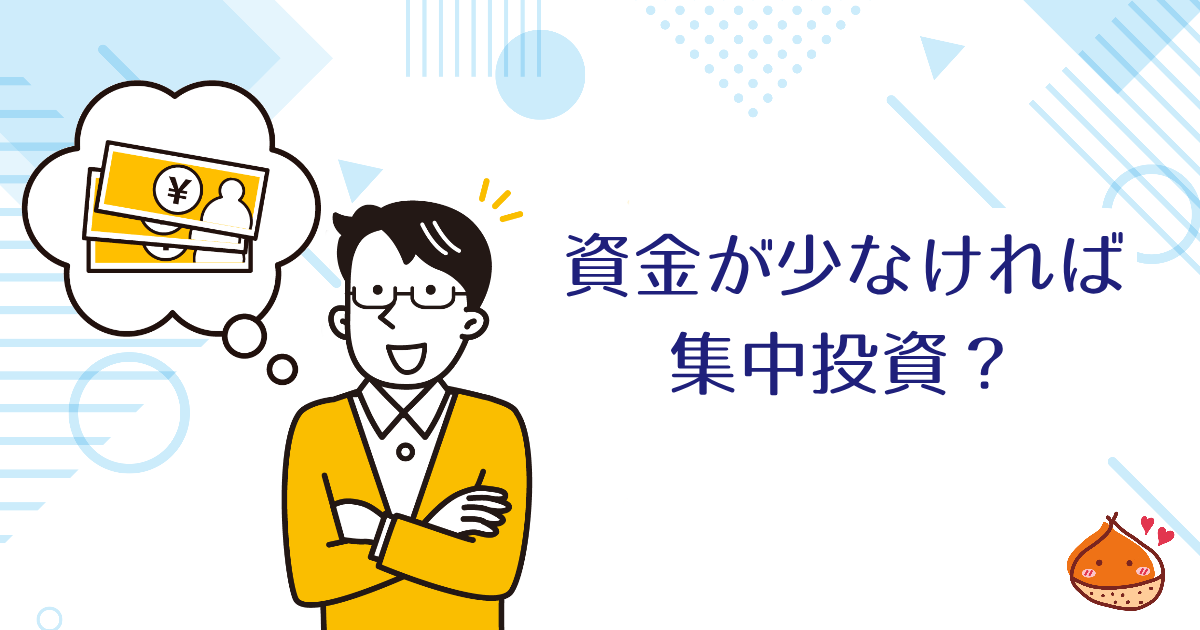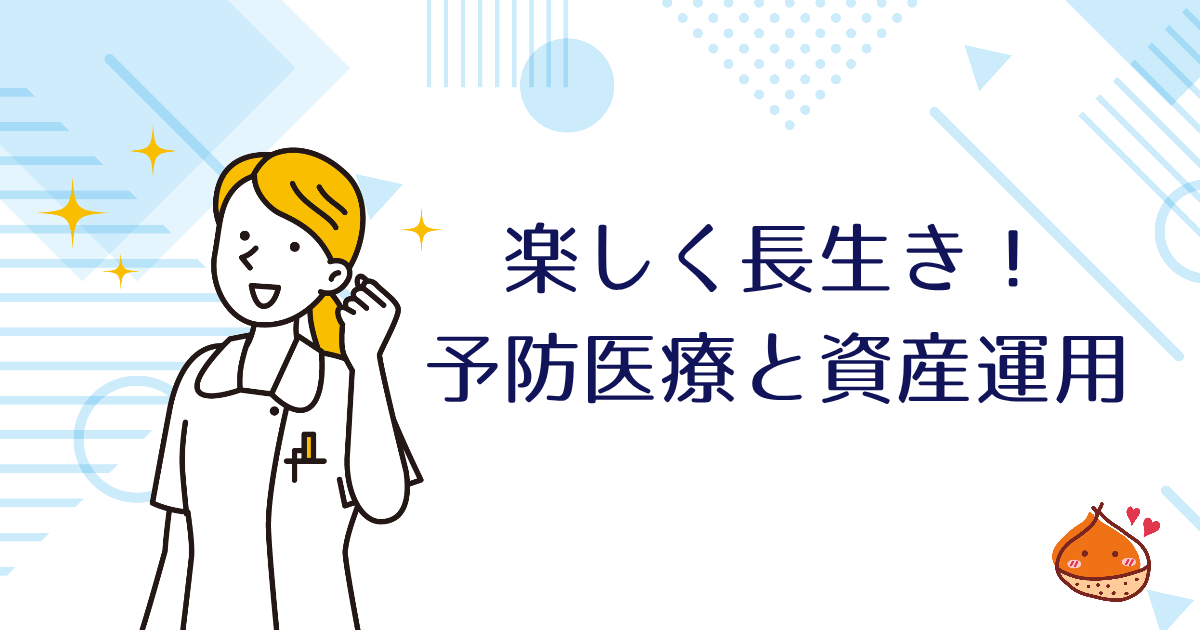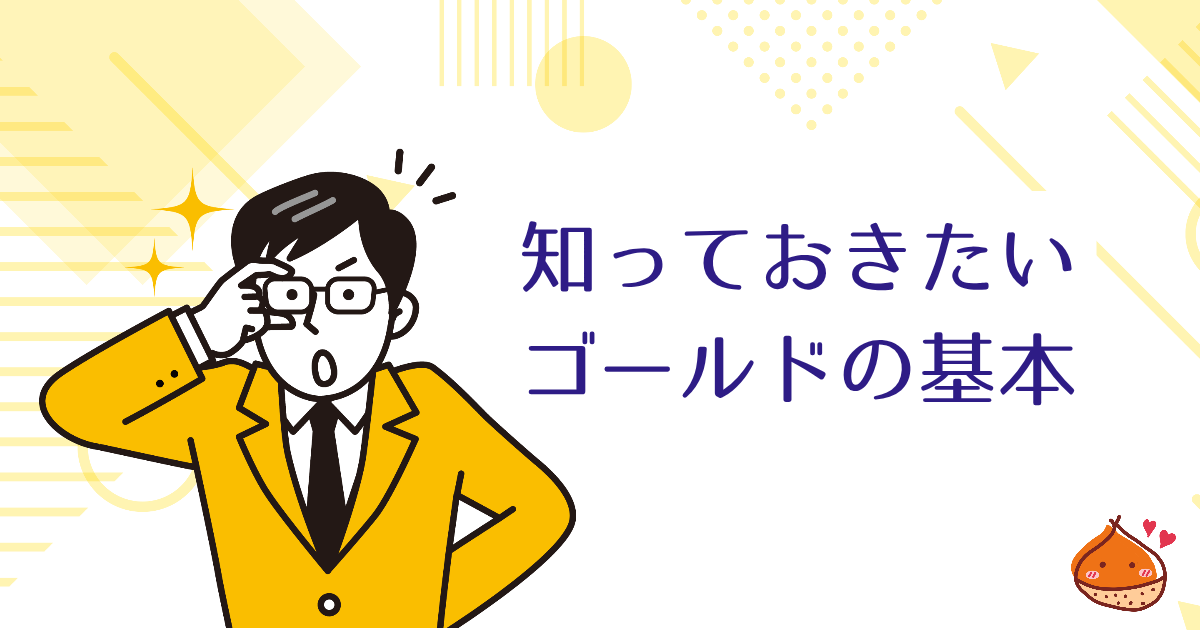
はじめに:ゴールドの注目度が高まる背景
世界的なインフレ、地政学リスク、円安…こうした不安定な時代に注目を集めているのが「ゴールド(金)」です。実物資産である金は、通貨や株式と違い、国や企業の信用に左右されないため「世界共通の価値」としての役割があります。
投資初心者の中にも「そろそろ金を持った方がいいのでは…」と思い始めている方も多いのではないでしょうか。
今回は、ゴールドについて知っておきたい基本知識を紹介します。
ゴールドのメリット6つ
インフレに強い
物価が上昇すると、お金の価値は下がりますが、金(ゴールド)の価値は物価と連動して上がる傾向があります。そのため、インフレ対策の「守りの資産」として長年利用されてきました。
世界共通の価値がある
金は国境を越えて通用する資産です。たとえば円が大幅に下落しても、金は米ドルやユーロなど、他国の通貨と換金できます。どこの国でも価値を認識されていることが、大きな安心材料です。
実物資産としての安心感
金は目に見えて手に取れる実物資産。電子データだけで存在する株式や債券と違い、「持っている」実感があり、有事やシステム障害時にも価値が保たれる点が魅力です。
流動性が高く、いつでも現金化できる
金は世界中で売買されているため、現金化が非常にスムーズです。急な資金需要があるときにも、金なら比較的すぐに売却して現金に戻せるという利点があります。
長期的に価値を維持しやすい
株価や為替が乱高下するなかで、金は数百年にわたって価値を保ち続けてきた資産です。短期で大きく増えるものではありませんが、長期的な安定性に優れています。
保険としての役割を持つ
経済危機・戦争・災害など、通常の金融商品が大きく下落するような「非常時」に備える保険的な資産としても金は機能します。特に現物で持つと「いざというとき」の安心材料になります。
ゴールドの役割は3つ「投資・投機・保険」
ゴールドは、ただ持っておけばよいというものではありません。その使い方には大きく分けて3つあります。
- 投資(長期で価値を保つ)
- 投機(短期で売買益を狙う)
- 保険(非常時に備える)
目的が違えば、選ぶ手段や保有の仕方も異なります。順番に見ていきましょう。
投資としてのゴールド
投資としてのゴールドは、「将来のインフレ対策」や「資産の安定性」を求める人に向いています。金は利息や配当を生みませんが、その価値は歴史的に長く維持されてきました。特に通貨の価値が下がった際でも、金は実物資産として一定の価値を保つため、インフレ対策に有効です。
「資産の5〜10%を金で保有するとリスク分散になる」といわれるのはこのためです。
投機としてのゴールド
一方で、金価格は世界経済や為替の影響を受けて上下します。これを利用して、短期的に売買差益を狙う「投機」として金に取り組む人もいます。たとえば「ロシア情勢の悪化により、金価格が急騰」といった動きがあれば、買っていた金を売ることで利益が出ます。
ただし、相場の読み違いによる損失リスクもあるため、投機としての金は中〜上級者向けといえるでしょう。
保険としてのゴールド
ゴールドの本領が発揮されるのは「非常時」です。大地震、戦争、経済危機などが発生したときに、現金や株式が大きく価値を失う中で、金は資産の「保険」として機能します。
たとえば通貨価値が暴落したトルコやベネズエラなどでは、金を持っていた人の方が被害を抑えられたケースもあります。国境を超えて通用するという点でも、金の信頼性は高いのです。
ゴールドの買い方:現物・ETF・純金積立など
金を買う方法はいくつかあります。
- 現物(金地金・金貨など):実際に保有できる安心感があるが、保管場所や盗難リスクに注意。
- 金ETF(上場投資信託):証券口座で手軽に売買可能。価格変動を反映するが、実物ではない。
- 純金積立:毎月一定額で金を買い続ける方法。少額から始めやすいが、手数料に注意。
ライフスタイルや目的に合った方法を選びましょう。
ゴールド投資の注意点
金は利息や配当がつかないため、資産を「増やす」目的には不向き
ゴールドは「守る」資産としては優秀ですが、「増やす」資産とはいえません。
たとえば、株式であれば年に数%の配当金が得られますし、債券なら定期的に利息収入があります。
しかし、金には利息も配当も一切つきません。持っているだけでは収益が発生しないのです。1,000万円分の金を購入して10年間保有しても、価格が変動しない限り、手元のお金は増えません。
一方で、同じ1,000万円を高配当株に投資すれば、年に3〜4%の配当収入が期待でき、10年間で数百万円の差が出ることも。
また、金の価格が下がれば当然元本割れするリスクもあります。そのため「短期間で資産を増やしたい」「収入を生みたい」という目的で金を選ぶと、期待はずれに終わる可能性が高いのです。
金はあくまで、「資産の一部を守る」用途での活用が現実的です。
短期的に金価格が下がることも
ゴールドは安全資産として知られていますが、短期的には価格が大きく変動することもあります。
たとえば、2020年のコロナ禍直後は金価格が急上昇しましたが、その後は下落と上昇を繰り返しています。2022年には一時的に円高が進行したことで、日本円で見た金価格が大幅に下落した例もありました。
「安全」と言われていても、タイミングによっては短期間で数%〜10%以上下がることもあるのが金の現実です。
仮に「来年の子どもの入学資金のために金を買っておこう」と考えても、思ったより下がってしまい売れなくなるリスクもあります。そのため、ゴールドは「短期的に確実に値上がりしてほしい」といった目的には不向きです。
急な出費に備える流動性資金としても適していません。あくまで「長期的な資産保全」としての役割が基本といえるでしょう。
売却時には課税(総合課税または譲渡所得)が発生することも 税制を確認
ゴールドを売却して利益が出た場合、税金がかかる可能性があることを忘れてはいけません。
たとえば、純金積立や金地金(インゴット)を10年前に100万円で購入し、現在200万円で売却したとします。
この差額100万円が利益(譲渡所得)となり、一定の条件を超えると課税対象になります。
保有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として課税額が軽減される特例(特別控除50万円など)がありますが、短期売買や利益が大きい場合は所得税・住民税が合計で20%超課税されることもあります。
また、金ETF(上場投資信託)のような金融商品であれば「総合課税や申告分離課税」など、別のルールが適用される場合もあります。
利益をあげた場合は、税金について確認しておきましょう。
まとめ:自分に合った「金との付き合い方」を選ぼう
金は「増やす」よりも「守る」ための資産です。株式や債券と違い、物理的な裏付けがある資産として、価値の保存やリスクヘッジの手段として重宝されます。
長期保有でインフレに備える、非常時の備えとして一部を保有するなど、自分の資産配分や目的に応じて取り入れるのが賢い使い方です。
ランキングに参加しています。ポチッとしてもらうと、とても励みになります(^-^)/
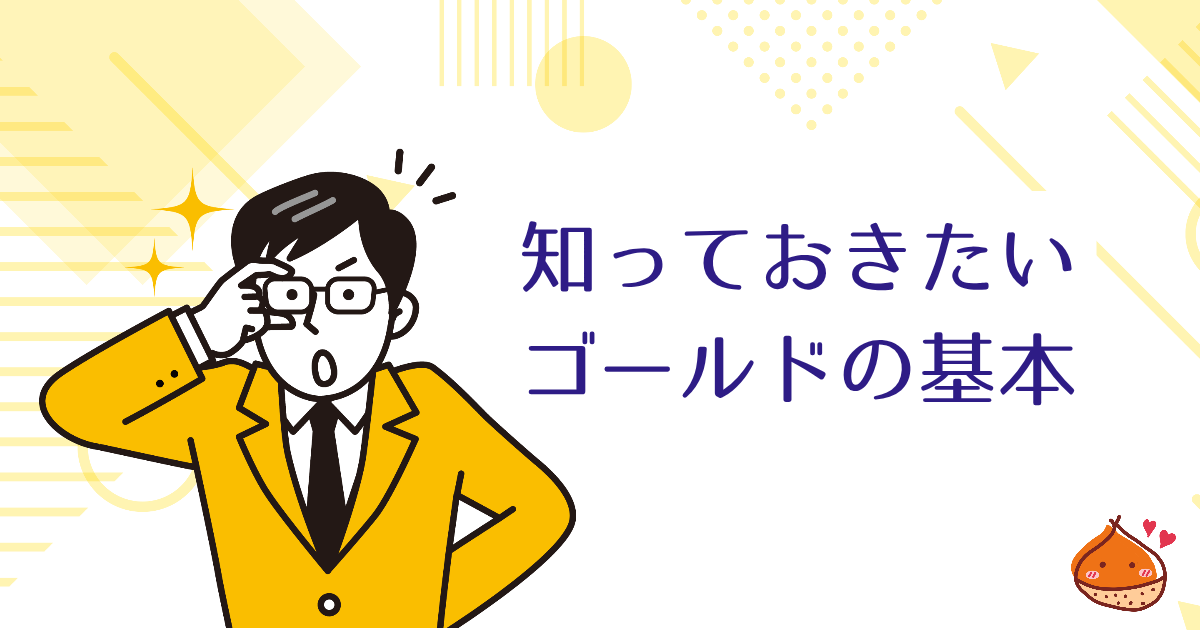
記事が気に入ったら
フォロープリーズ!
Wrote this articleこの記事を書いた人
あかぐり
クレジットカードを使い続けて10年以上。初めてクレジットカードを作る人に向けて、また、サイトに来てくれた人の経験や知識に「ちょい足し」するべく、クレジットカードの実体験とお金に関する情報を発信しています。